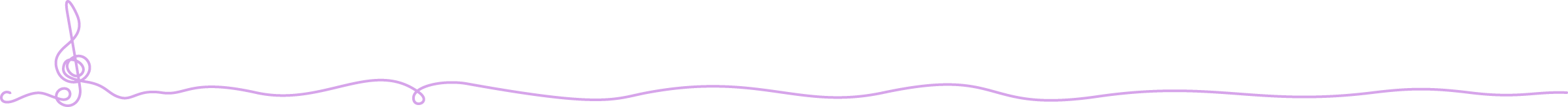名曲について知る
ロマン派の名曲(3)
今回は、「ロマン派の名曲」の第1回、第2回で取り上げられなかった、19世紀前半の作品をまず2曲、ご紹介したいと思います。そして、19世紀後半から、「後期ロマン派の名曲」のコーナーではご紹介できない作曲家の作品も3曲取り上げています。
エクトル・ベルリオーズ
- ベルリオーズ:「幻想交響曲」

クールベが描いたベルリオーズの肖像
1830年にパリで初演されたこの交響曲は音楽史上画期的なものでした。ベルリオーズはこの作品にオペラのような筋書きを与えて、物語のような音楽としたのです。それまでの交響曲は物語性を明確に打ち出すことは非常に稀でした。しかも、ベルリオーズが選んだ物語は個人的な体験も反映されたものでしたので、「幻想交響曲」は作曲家個人の経験と作曲家活動を結びつける傾向が強いロマン派らしい音楽と言えるでしょう。
この交響曲は5楽章からなっています。以下に記す物語は、ベルリオーズ自身の恋愛体験も反映しているのです。第1楽章「夢・情熱」は、心の病気を抱える若い芸術家が、一目惚れした女性に情熱を燃やしているさまが描かれています。その女性を表す主題が提示されるのですが、この主題はすべての楽章に姿を変えつつ現れるのです。第2楽章は「舞踏会」。芸術家は華やかな舞踏会で踊る恋人をみつけます。ベルリオーズは舞踏会のようすを描くために、この楽章でワルツのリズムを使用し、ハープの響きが華やかさを演出しています。第3楽章は「野の風景」と題され、夕刻に田園の広がる場所にいる芸術家のようすが描写されていきます。羊飼いたちが吹く笛の調べ(コーラングレで担当しています)を聴きながら、芸術家は希望が湧いてくるのですが、恋人がもしや裏切りはしないかという不安にもさいなまれるのです。その不安を象徴するかのように、この楽章の後半では、ティンパニによって嵐の前の遠雷が聞こえてきます。第4楽章「断頭台への行進」では、失恋してしまった芸術家は悲嘆にくれて麻薬に手を出し、奇怪な夢を見ます。夢のなかで、芸術家は恋人を殺し、死刑宣告を受けて断頭台へと引かれていくのです。恋人の亡霊が彼の前に現れますが、ギロチンが彼の首に落ちてきて、その恋人の姿も消えてしまいます。第5楽章「サバトの夜の夢」では、芸術家の葬式に集まった亡霊や魔女たちのおどろおどろしい饗宴を描いています。恋人を表す主題もこの楽章ではグロテスクな性格のものに変わってしまうのです。
この交響曲は5楽章からなっています。以下に記す物語は、ベルリオーズ自身の恋愛体験も反映しているのです。第1楽章「夢・情熱」は、心の病気を抱える若い芸術家が、一目惚れした女性に情熱を燃やしているさまが描かれています。その女性を表す主題が提示されるのですが、この主題はすべての楽章に姿を変えつつ現れるのです。第2楽章は「舞踏会」。芸術家は華やかな舞踏会で踊る恋人をみつけます。ベルリオーズは舞踏会のようすを描くために、この楽章でワルツのリズムを使用し、ハープの響きが華やかさを演出しています。第3楽章は「野の風景」と題され、夕刻に田園の広がる場所にいる芸術家のようすが描写されていきます。羊飼いたちが吹く笛の調べ(コーラングレで担当しています)を聴きながら、芸術家は希望が湧いてくるのですが、恋人がもしや裏切りはしないかという不安にもさいなまれるのです。その不安を象徴するかのように、この楽章の後半では、ティンパニによって嵐の前の遠雷が聞こえてきます。第4楽章「断頭台への行進」では、失恋してしまった芸術家は悲嘆にくれて麻薬に手を出し、奇怪な夢を見ます。夢のなかで、芸術家は恋人を殺し、死刑宣告を受けて断頭台へと引かれていくのです。恋人の亡霊が彼の前に現れますが、ギロチンが彼の首に落ちてきて、その恋人の姿も消えてしまいます。第5楽章「サバトの夜の夢」では、芸術家の葬式に集まった亡霊や魔女たちのおどろおどろしい饗宴を描いています。恋人を表す主題もこの楽章ではグロテスクな性格のものに変わってしまうのです。
ヨハン・シュトラウス一世
- ヨハン・シュトラウス一世:「ラデツキー行進曲」
ヨハン・シュトラウス一世は、息子のヨハン・シュトラウス二世が「ワルツ王」とあだ名されるのに対し、「ワルツの父」と呼ばれることがあります。19世紀の社交界を虜にしたワルツのほか、ポルカ、ギャロップなど、気軽な装いのダンス音楽を作曲し、自前の楽団で演奏したシュトラウスは、ウィーンの人々を魅了して止みませんでした。音楽家たちもシュトラウスを高く評価しており、たとえばワーグナーは19歳の時にシュトラウスの指揮する楽団を聴いて「シュトラウスは魔法の腕をもつヴァイオリン弾きで、きっすいのウィーン音楽の魂をもった天才である」と評しています。ウィーンの外でも彼の名声は轟き、フランス、イギリスなどにも演奏旅行に出かけていくほどでした。晩年の1846年には、ウィーンの宮廷舞踏会音楽監督に任ぜられています。

自分のワルツ楽団を指揮するヨハン・シュトラウス一世
栄誉に包まれた人生を送ったシュトラウス一世ですが、現在では息子の影に隠れてしまい、彼の音楽が演奏される機会はあまりありません。しかし、1848年に出版された「ラデツキー行進曲」は唯一の例外で、毎年元旦に行われるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の「ニュー・イヤー・コンサート」で必ず演奏されるために、非常に有名です。この作品はもともと、当時、オーストリア帝国の支配下にあったイタリアで勃発した革命に関連があり、この革命を鎮圧したオーストリアの将軍ラデツキーを讃えるために書かれました。つまり、ラデツキー将軍の堂々とした凱旋に相応しい、勇壮な軍隊行進曲なのです。発表直後からこの行進曲は人気があり、旧オーストリア軍を象徴する音楽となりました。しかし、20世紀になってオーストリアが帝国から共和国に変わると、軍事力の象徴だった「ラデツキー行進曲」は、「ニュー・イヤー・コンサート」の最後を華々しく飾る音楽として定着するなど、むしろ平和の象徴になっているのではないでしょうか。

自分のワルツ楽団を指揮するヨハン・シュトラウス一世
栄誉に包まれた人生を送ったシュトラウス一世ですが、現在では息子の影に隠れてしまい、彼の音楽が演奏される機会はあまりありません。しかし、1848年に出版された「ラデツキー行進曲」は唯一の例外で、毎年元旦に行われるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の「ニュー・イヤー・コンサート」で必ず演奏されるために、非常に有名です。この作品はもともと、当時、オーストリア帝国の支配下にあったイタリアで勃発した革命に関連があり、この革命を鎮圧したオーストリアの将軍ラデツキーを讃えるために書かれました。つまり、ラデツキー将軍の堂々とした凱旋に相応しい、勇壮な軍隊行進曲なのです。発表直後からこの行進曲は人気があり、旧オーストリア軍を象徴する音楽となりました。しかし、20世紀になってオーストリアが帝国から共和国に変わると、軍事力の象徴だった「ラデツキー行進曲」は、「ニュー・イヤー・コンサート」の最後を華々しく飾る音楽として定着するなど、むしろ平和の象徴になっているのではないでしょうか。
ヨハン・シュトラウス二世
- ヨハン・シュトラウス二世:「美しく青きドナウ」

ヨハン・シュトラウス二世(左)と
ブラームス
ヨハン・シュトラウス二世は、前項に書いたように、父親と同名ですが、現在では「ヨハン・シュトラウス」と言えばこの息子を指すほど有名です。しかし、父親は息子のヨハンが音楽家になることに当初は反対でした。しかし、蛙の子は蛙、幼い頃より音楽の才能を発揮していたヨハンは父親と同じ道を歩むこととなったのです。そして、弟のヨーゼフやエドゥアルトとともに、「シュトラウス王国」とも呼ぶべき音楽家一族として19世紀後半のウィーン、そしてヨーロッパ、アメリカの人々を魅了し続けました。ヨハン・シュトラウスは父の路線を継承して、ワルツやポルカといった舞曲の音楽を中心に作曲していましたが、ワーグナーやリストといった当時の進歩的な音楽家たちにも傾倒し、より斬新でシンフォニックな音楽を書いています。そして何よりも、美しい旋律を書く才能は、ブラームスのような作曲家をも魅了して止みませんでした。また、オペレッタの分野でも活躍し、「こうもり」、「ジプシー男爵」は現在でも人気の高い演目になっています。
「美しく青きドナウ」は1867年に出版されたワルツで、シュトラウスの音楽のなかでも最も知られた作品の一つです。序奏、5つのワルツ、そしてコーダという構成は父ヨハンのスタイルを継承していますが、各ワルツを彩る旋律はシュトラウスならではの流麗さを誇っています。この作品は、まさにウィーンの中心を流れるドナウ川のさまざまな情景を髣髴とさせ、ウィーン風のワルツ(「ウィンナ・ワルツ」)を代表する音楽と言えるでしょう。父ヨハンの「ラデツキー行進曲」とともに、「ニュー・イヤー・コンサート」においてもプログラムに不可欠な作品です。
「美しく青きドナウ」は1867年に出版されたワルツで、シュトラウスの音楽のなかでも最も知られた作品の一つです。序奏、5つのワルツ、そしてコーダという構成は父ヨハンのスタイルを継承していますが、各ワルツを彩る旋律はシュトラウスならではの流麗さを誇っています。この作品は、まさにウィーンの中心を流れるドナウ川のさまざまな情景を髣髴とさせ、ウィーン風のワルツ(「ウィンナ・ワルツ」)を代表する音楽と言えるでしょう。父ヨハンの「ラデツキー行進曲」とともに、「ニュー・イヤー・コンサート」においてもプログラムに不可欠な作品です。
セザール・フランク
- フランク:「交響曲ニ短調」

セザール・フランク
セザール・フランクはベルギー生まれですが、主にパリで活動した作曲家、オルガニストです。教会でオルガニストを務めたり、パリ音楽院でオルガン科教授に就任するなど、フランクの作品にはオルガン曲や宗教曲が目立ちます。そのいっぽうで、フランスの作曲家たちの器楽曲を普及させる目的で設立された国民音楽協会の会長に選出され、有名なヴァイオリン・ソナタを筆頭とする室内楽曲や交響詩の創作にも励みました。1870年代以降は、ワーグナーやリストといったドイツ系の進歩的な作曲家たちの影響を受け、最先端を走る作曲家としてパリの楽壇を牽引していきました。教育活動にも熱心で、彼の弟子たちは「フランク派」と呼ばれるほどでした。
交響曲ニ短調は、晩年の1786年から88年にかけて作曲され、1889年2月にパリ音楽院の演奏会で初演されました。3つの楽章からなっていますが、フランクは第1楽章の最初に提示される主題を、全曲を統一するための共通主題として用いています。その主題は非常に悲痛な性格のもので、その性格は第1楽章全体をも支配しているのです。コーラングレの哀調の籠もった響きが印象的な第2楽章も共通主題に基づいています。最後の第3楽章は晴れやかな長調に転じ、フランク特有のオルガンを思わせる華やかな音響が聞こえてきます。第2楽章の悲しげなメロディも回想され、作品全体を閉じるに相応しい内容を持っているのです。フランクの音楽は当時の聴衆にとっては難解なものと思われており、この交響曲が初演を迎える日も、フランクの妻は心配していたといいます。初演の演奏会から帰ってきた夫に、妻は聴衆の反応を聴きました。自作の評判について関心のないフランクは妻の質問には答えず、こう言ったそうです。「私の考えたとおりに響いてきた。」フランクらしいエピソードではないでしょうか。
交響曲ニ短調は、晩年の1786年から88年にかけて作曲され、1889年2月にパリ音楽院の演奏会で初演されました。3つの楽章からなっていますが、フランクは第1楽章の最初に提示される主題を、全曲を統一するための共通主題として用いています。その主題は非常に悲痛な性格のもので、その性格は第1楽章全体をも支配しているのです。コーラングレの哀調の籠もった響きが印象的な第2楽章も共通主題に基づいています。最後の第3楽章は晴れやかな長調に転じ、フランク特有のオルガンを思わせる華やかな音響が聞こえてきます。第2楽章の悲しげなメロディも回想され、作品全体を閉じるに相応しい内容を持っているのです。フランクの音楽は当時の聴衆にとっては難解なものと思われており、この交響曲が初演を迎える日も、フランクの妻は心配していたといいます。初演の演奏会から帰ってきた夫に、妻は聴衆の反応を聴きました。自作の評判について関心のないフランクは妻の質問には答えず、こう言ったそうです。「私の考えたとおりに響いてきた。」フランクらしいエピソードではないでしょうか。
カミーユ・サン=サーンス
- サン=サーンス:「動物の謝肉祭」
カミーユ・サン=サーンスは1835年、パリで生まれました。3歳で作曲をするなど、モーツァルト並みの神童だった彼はなんと13歳でパリ音楽院に入学しています。作曲家だけでなく、ヴィルトゥオーゾ・ピアニスト、オルガニスト、指揮者、著述家、教育者としても活躍しました。彼の好奇心は音楽に留まらず、文学、語学、考古学、天文学など多彩な分野に関心を示したのです。86年の長い生涯を送ったサン=サーンスはさまざまなジャンルに膨大な量の作品を残していますが(彼は映画音楽を書いた最初の有名作曲家とされています)、現在好んで演奏される作品の数は非常に少なく、さらなる再評価が求められる作曲家の一人ではないでしょうか。

伴奏をするカミーユ・サン=サーンス
《動物の謝肉祭》は1886年に初演されています。「動物学的大幻想曲」という副題をもっていますが、全体は14曲の小品からなる組曲の形式をとっています。楽器編成は非常に変わっていて、2台のピアノ、ヴァイオリン2,ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、ピッコロ、クラリネット、グラス・ハルモニカ、シロフォンという多彩な楽器が使われているのです。各曲はさまざまな動物の名前をタイトルにしており、音楽で鳴き声や動作などが描写されていきます。しかし、曲によってはかなり皮肉な表現が取られているものもあって、作曲者のユーモアを感じることができます。たとえば、第5曲「象」では、大きくて重たい象の歩みが表現されているのですが、そこで引用されている主題は、オッフェンバックのオペレッタ「天国と地獄」のなかの激しく華やかな踊りである「カンカン」の音楽なのです。また、第11曲は「ピアニスト」と題されています。「動物の謝肉祭」のなかに人間が入っていることもさることながら、下手なピアニストの練習を皮肉った音楽は、笑いを誘わずにはいられません。サン=サーンスの皮肉とユーモアが盛り込まれた「動物の謝肉祭」ですが、作曲者自身はこの作品を冗談のつもりで書いたようで、生前に全曲を演奏することを禁止してしまいました。しかし、1曲だけ例外を作りました。それは、ピアノの流麗な伴奏にのってチェロが美しい旋律を奏でていく第13曲「白鳥」だったのです。

伴奏をするカミーユ・サン=サーンス
《動物の謝肉祭》は1886年に初演されています。「動物学的大幻想曲」という副題をもっていますが、全体は14曲の小品からなる組曲の形式をとっています。楽器編成は非常に変わっていて、2台のピアノ、ヴァイオリン2,ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、ピッコロ、クラリネット、グラス・ハルモニカ、シロフォンという多彩な楽器が使われているのです。各曲はさまざまな動物の名前をタイトルにしており、音楽で鳴き声や動作などが描写されていきます。しかし、曲によってはかなり皮肉な表現が取られているものもあって、作曲者のユーモアを感じることができます。たとえば、第5曲「象」では、大きくて重たい象の歩みが表現されているのですが、そこで引用されている主題は、オッフェンバックのオペレッタ「天国と地獄」のなかの激しく華やかな踊りである「カンカン」の音楽なのです。また、第11曲は「ピアニスト」と題されています。「動物の謝肉祭」のなかに人間が入っていることもさることながら、下手なピアニストの練習を皮肉った音楽は、笑いを誘わずにはいられません。サン=サーンスの皮肉とユーモアが盛り込まれた「動物の謝肉祭」ですが、作曲者自身はこの作品を冗談のつもりで書いたようで、生前に全曲を演奏することを禁止してしまいました。しかし、1曲だけ例外を作りました。それは、ピアノの流麗な伴奏にのってチェロが美しい旋律を奏でていく第13曲「白鳥」だったのです。