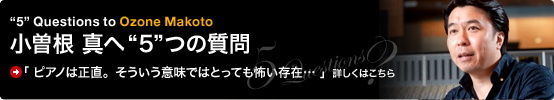この記事は2009年8月9日に掲載しております。
この記事は2009年8月9日に掲載しております。
83年にアメリカでジャズ・ピアニストとして華麗なデビューを果たし、以来多くの音楽シーンを創出してこられた小曽根真氏。近年はオーケストラとの競演でさらに音楽ファンを驚かせています。
自分の音楽そのものと言われるビッグ・バンドNo Name Horsesとの最新アルバムまで、辿られた道行きを語っていただきました。


- pianist
小曽根 真 - 父、小曽根 実の影響でジャズに興味を持ち、独学で音楽を始める。
1980年渡米。1983年ボストンのバークリー音楽大学ジャズ作曲・編曲科部門を首席で卒業。同年ニューヨークのカーネギーホールでソロ・ピアノ・リサイタルを開き、米CBSレーベルと日本人初の専属契約を結び全世界デビューを果たす。同時にグラミー賞受賞アーティスト、ゲイリー・バートン(ヴィブラフォン)のグループに参加、ワールド・ツアーを開始。この頃から作曲家としての活動も始め、ゲイリーをはじめとするさまざまなミュージシャンたちに曲を提供するようになる。2003年2月、ゲイリー・バートンとのデュオ『ヴァーチュオーシ』(Concord)で、第45回グラミー賞に初ノミネート。近年は、クラシックにも本格的に取り組み、シャルル・デュトワ、尾高忠明、井上道義、大植英次らの指揮のもと、国内外のオーケストラとガーシュウィン、バーンスタイン、モーツァルト、ベートーヴェンなどの作品を演奏している。また「第18回国民文化祭・やまがた2003」では自作のピアノ協奏曲「もがみ」を弾き振りで発表。
一方、2004年には自らがプロデュースする総勢15名のビッグバンド「No Name Horses」を結成し、翌年には「No Name Horses」のデビュー・アルバムをレコーディング。2007年には東京JAZZに「No Name Horses」を率いて参加し、『着実にこの世界に新風を送っている』(日本経済新聞)と評された。
2008年3月は、「No Name Horses」のセカンドアルバム『Ⅱ』の全国ツアーで約1ヶ月熱いステージを繰り広げた。
2009年5月には、「No Name Horses」のラテン音楽をテーマとしたアルバム『JUNGLE』のリリース。このアルバムにも参加しているラテン・パーカッションのパーネル・サトゥルニーノをゲストに7月から全国クラブ・ツア-を行い、続けて7月末から8月にかけてフランスのラロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭とスコットランドのエジンバラ・ジャズ・フェスティバルに出演予定。
精力的な演奏活動のかたわら、人気FMジャズ番組「OZ MEETS JAZZ」のパーソナリティーを務めるほか、テレビ出演や舞台音楽、ドラマ音楽を手がけるなど、ジャズの世界を超えた幅広い活動へと挑戦を続けている。
「小曽根 真」オフィシャルウェブサイト
※上記は2009年8月9日に掲載した情報です。
始まりはオルガン、オスカー・ピーターソンを聴いてピアノに開眼。

両親共に音楽をやっていましたから、もの心ついた頃からオルガンを弾いていました。5歳の時に母親から「ピアノやってみたら?」と勧められ、レッスンに行ったんですがバイエルに嫌気がさしてすぐにやめてしまった。つまんない…(笑) その頃既にオルガンであればちゃんと曲を弾けていたわけですよ。だからバイエルの単調さが我慢できなかった。学校ではモーツァルトとか聴かされて楽しくない。LP聴いて感想文書くなんてナンセンス!なんて思ったりして。
「ピアノ=クラシック」と塗りこまれちゃっているから、僕はひたすらオルガンでジャズを弾いていました。
12歳の時に初めてオスカー・ピーターソンのコンサートを観て衝撃を受け、それから僕のピアノ人生が始まったわけです。年齢的には遅いけれど鍵盤楽器は生まれた頃から弾いていましたからね。
黒鍵だけで弾きたくて、見つけた曲は「お座敷小唄」

子供心に黒鍵を弾くことに面白みを感じていて、白鍵だとドレミファソラシドとなり、つまんない。でも黒鍵だとドレミソラ、なんだかハーモニーがあって、それで見つけた曲が「お座敷小唄」!祖父がうちに来るといつも弾いて聴かせていました。(笑)
次に覚えたのが「マック・ザ・ナイフ」。これは黒鍵だけでは弾けない、ファとシの音を覚えなくちゃだめ。僕はこのキーが何の音かということではなくて、この黒鍵の隣の白を弾くと言った感覚だったんです。この曲、楽譜で見ると嫌になりますよ(笑) GフラットMajerですからね、弾きにくい!でも僕は音とメロディを鍵盤上で探しながら覚えてしまう。お陰で12-3歳くらいまで楽譜が読めなかった。
父親に「この曲覚えた!」と持っていくと、伴奏をつけてくれる。それが楽しくて仕方ない。そして父が半音上げて弾いてみろと言う。僕は音を探しながら弾く、その繰り返しでした。父は間違って弾いてもそれを正しません。「もう一度レコードを聴け」と言う。間違いを自分で見つけていきました。
10歳でトップ・ミュージシャンらと楽屋でセッション
父がジミー・スミス(注1)と友達で、僕が10歳の時に大阪フェスティバル・ホールでのコンサートに連れて行ってくれました。アート・ファーマーやケニー・バレルと言った一流の豪華メンバーで来日していましたから。終わった後に楽屋に出向いたんです。そこにアップライトピアノが置いてあり、父が「何か弾け!」と。その頃はもう既にアドリブが出来ていたので、簡単なFのブルースか何か弾いたんですね。するとジミーが伴奏してくれ連弾に…。そこへケニー・バレルがやって来て「OH!No!!」と言ってギターを出してきた、そしてイリノイ・ジャケがやって来てテナー・サックスを…。大変なセッションが始まっちゃいました。
そしてイリノイ・ジャケが「この子は日本に置いてちゃだめだ。すぐにアメリカに出してジュリアード(注2)に入れろ」と。これがアメリカという国を意識するようになった最初だったかな。
(注1)世界的ジャズ・オルガン奏者 (注2)クラシック音楽の名門 ジュリアード音楽院

最初のテキストはモシュコフスキーとバッハ

この2年後にオスカー・ピーターソンでピアノに目覚めたわけです。自宅は両親が音楽教室をやっていたから始終「軍隊行進曲」や「エリーゼのために」なんかが聞こえてきて、いつも「つんまねぇ音楽やってんなぁー。僕には関係ない。」なんて思っていた。(笑)でもピアノをやるからにはちゃんと誰かに習わなくちゃだめだとわかっていたから、母が色々人に聞いてまわって調べてくれ、神戸の灘カトリック教会にいらしたフランス人のジャン・メルオ神父(先生)につくことができました。これはとても幸運だったと思う。この先生に習いたい人たちは沢山いたらしいので。
最初に先生に「絶対バイエルやハノンはやりたくない!」と生意気に宣言、すると先生はとてもよく理解して下さり「よくわかる。確かにこれは音楽ではなく技術のエクササイズだからね」と。そしてモシュコフスキーのエチュードとバッハのインヴェンションを与えてくれました。次にソナタ集をやったかな…。この先生には1年半くらい習いました。
当時、跳び箱から落ちて左腕を骨折、治療中はレッスンに行けないのでなんとなくこれで終わっちゃいました。でもこのテキストがあるから自分でずっと練習して、あとはひたすらオスカー・ピーターソンを耳コピー…。聴いて覚えて、聴いて覚えて、その連続でした。僕はクラシックをあくまでもピアノを弾くためのエクササイズとしてとらえていましたから。
18歳でアメリカ・ボストンへ留学

その後、北野タダオ先生に師事しました。先生は僕をジャズ・クラブに連れて行ってどんどん弾かせる、実地教育ですよ。この繰り返し…。そうこうしているうちに東京に行って勉強しようかなと先生に相談したら反対されました。「東京に行くのだったらアメリカまで行けば良い!」と。そこで初めてバークリー音楽院という学校を知りました。今でこそ日本人の学生は300人くらいいますが、当時はとても少なかった。
18歳で渡米しました。神戸を出発する時、母が開いてくれた「旅立ちコンサート」に北野先生も出演して下さったのですが、「マー坊(小曽根氏のこと)は向こうに行ったらもう帰ってきいへんだろうなぁ…。」と言われて送り出されました。僕はバークリーを卒業したら神戸に戻り、父のところで演奏活動しながら、北野先生のバンドの譜面を沢山書くのだ!という夢があったから「何言ってんですか!!!僕は絶対帰ってきます。」と反論。でもその通りになっちゃった…。「先生ごめんなさい。」とアメリカから手紙を書いたことを覚えています。(笑)
ボストンには足掛け10年住みました。幸運にも向こうでデビューできたのでビザがとれたし。僕はね、ビザが取れずにアンダーテーブルで仕事をするのは絶対に嫌だった。だから最初から卒業後は日本に帰るつもりだったんですよ。ところが、とてつもない幸運の連続でゲイリー・バートンのバンドにも入れ、想像もしなかった展開になってしまいました。
音楽の醍醐味は「人とつながる」こと
ついこの間、ボストンでヤマハのフルコンCFIIISを弾いたんですが、聴きに来てくれた友人が驚いていました。彼は医者なんだけど、東大の学生時代、オケでコントラバスを弾いていたんです。僕の演奏を聴いて、「ピアノ一台でどうしてこんなオーケストラのような音が出るの?こんな音聴いたのは初めてだ!」と。
おそらく僕は、ピアノという楽器をピアノでありながらオーケストラという捉え方をしているんじゃないかと思う。ピアノの中にすべてがあるんですよ。ここがティンパニ、ここがピッコロ、ここにはフレンチホルン…とね。
所謂ピアノ協奏曲と呼ばれるものはショパンにしてもモーツァルトにしてもピアニスティックです。
でもガーシュインなんかは結構ピアノがオーケストラの鳴りになっている。僕自身の音楽はいつもそんなカンジなんです。基本的にオーケストラしかりビッグ・バンドしかり、アンサンブルが好き。音楽やっていて何が一番面白いかと言うと「人とつながる」こと。これが一番大事、大切なことなんですね。
僕の音楽に対する信頼と愛情が集結して出来上がったのが「Jungle」

ビッグ・バンドをやり始めた最初の頃は、よくお客さまから「もっとピアノが聴きたかったのに」という意見をいただいていました。それはきっと、“ビッグ・バンドのスタイルを小曽根真が書くとこうなりますよ”的なもので、従来のかくあるべきといった型にどこか押されていたからだと思う。
今回録音したアルバム「Jungle」は、“小曽根真がビッグバンドの音楽を書きました”から“小曽根真の音楽をビッグバンドでやりました”に変わったんです。僕の頭の中で鳴っている音を書いてみるとビッグバンドになってしまう….。No Name Horses の4作目までこれが出来なかったんですね、ビッグバンドの音楽が大好きだっただけに。その証拠(?)に今回のツアーではもっとピアノが聴きたかったという声はありません。逆にお客さまはとても喜んでいらして、楽しんでいるのがわかるんです。メンバーもすごく楽しんでいる。活きています。

「Jungle」は誰にも遠慮せず、自分自身に聞こえてきた音を譜面にして、片っ端から出来たものをPDFにしてメンバーに送りました。今回のアルバムは本当に難度が高くてキツイから練習しておいてもらわなくてはならない。2-3週間前からさらってもらいました。
リハーサルは1日だけ。1曲1時間、9曲を仕上げました。翌々日からスタジオに入って録音開始。4日間で録り終えました。事前の練習がなかったら絶対に出来ませんでしたね。ピアノとベース、ドラム、パーカッションはそれぞれブースに入ってますが、管セクションはみんなで1部屋。誰か一人がミスするとそれで終わり…。だからすごいプレッシャーだったと思います。
本当にこのメンバーに感謝!です。僕の音楽に対する信頼と愛情、そしてバンドのみんなに対するそれぞれの愛情が集結してこのアルバムが出来上がったのだと心からそう思います。ぜひ聴いて下さい!

Textby 伊熊よし子
※上記は2009年8月9日に掲載した情報です。