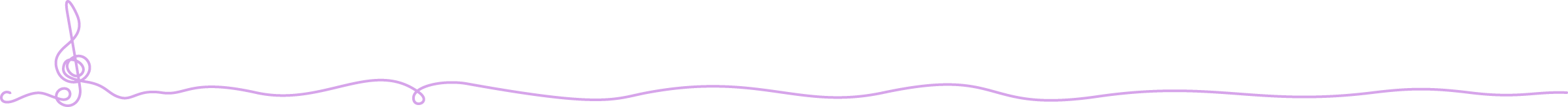名曲について知る
古典派から初期ロマン派にかけての名曲
今回は古典派から初期ロマン派にかけての名曲です。この時代を代表する作曲家はハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、そしてシューベルトですが、ここではこの4人以外の作曲家の作品を取り上げます。この時代は音楽を受容する層が貴族たちだけでなく、都市の市民たちにも飛躍的に広がり始めた時期で、それと同時に音楽家たちの社会的な地位も徐々に向上していきました。
クリストフ・ヴィリバルト・グルック
- グルック:「聖霊の踊り」

クリストフ・ヴィリバルト・グルック
クリストフ・ヴィリバルト・グルック(1714~1787)は18世紀後半にオペラ作家として国際的に有名な作曲家でした。彼は18世紀前半までのオペラが、歌手の名人芸を披露するだけの場となってしまったことを反省し、劇としての迫真性を回復し、そのために言葉を明確に伝えるために旋律の作曲法を工夫すべきであると主張したのです。彼はその理想を実現すべくオペラの作曲に励んだために、「オペラの改革者」と言われています。そんなグルックのオペラのなかで最も有名なのが1762年にウィーンで初演された「オルフェオとエウリディーチェ」です。単なる歌手の技巧のひけらかしでなく、劇の迫真性に音楽が寄与するという、グルックの改革の理念が端的に示されたオペラなのです。
「聖霊の踊り」はこのオペラの第2幕で踊られるバレエのための音楽で、オペラから切り離されて単独で演奏される機会も多いものです。原曲は弦楽合奏の静かな伴奏にのって独奏フルートが美しい旋律を歌い上げていくというものですが、そのメロディが余りに美しいためか、フリッツ・クライスラーがヴァイオリンとピアノのために編曲するなど、さまざまな編曲版によっても知られています。
「聖霊の踊り」は、オルフェオが死んでしまった恋人のエウリディーチェを取り戻すべく地獄へ旅立ち、楽園に憩う聖霊たちによって踊られます。ソロとして使用されたフルートにとってはやや低い音域で書かれているため、華やかさには欠けているかも知れませんが、むしろそのために醸し出される味わいは無類のものです。一度聴いただけで覚えられるほどに簡素ながら、聖霊たちの優雅な踊りを髣髴とさせるこの曲ほど、グルックの様式が明確に示された例はないのではないでしょうか。
「聖霊の踊り」はこのオペラの第2幕で踊られるバレエのための音楽で、オペラから切り離されて単独で演奏される機会も多いものです。原曲は弦楽合奏の静かな伴奏にのって独奏フルートが美しい旋律を歌い上げていくというものですが、そのメロディが余りに美しいためか、フリッツ・クライスラーがヴァイオリンとピアノのために編曲するなど、さまざまな編曲版によっても知られています。
「聖霊の踊り」は、オルフェオが死んでしまった恋人のエウリディーチェを取り戻すべく地獄へ旅立ち、楽園に憩う聖霊たちによって踊られます。ソロとして使用されたフルートにとってはやや低い音域で書かれているため、華やかさには欠けているかも知れませんが、むしろそのために醸し出される味わいは無類のものです。一度聴いただけで覚えられるほどに簡素ながら、聖霊たちの優雅な踊りを髣髴とさせるこの曲ほど、グルックの様式が明確に示された例はないのではないでしょうか。
ルイジ・ボッケリーニ
- ボッケリーニのメヌエット

ルイジ・ボッケリーニ
イタリア、ルッカ生まれのルイジ・ボッケリーニ(1743~1805)は当代随一のチェロ奏者として国際的に知られた存在です。持ち前の名人芸をたっぷりと駆使したチェロ協奏曲や、弦楽五重奏曲など、作曲家としては主に器楽曲をたくさん残しています。そんなボッケリーニの音楽のなかで、おそらく最も有名なものが「ボッケリーニのメヌエット」です。このメヌエットは様々な編曲版でも演奏されていますが、もともとはヴァイオリン2部、ヴィオラ、チェロ2部からなる弦楽五重奏曲ホ長調作品13-5(または作品11-5。1775年出版)の第3楽章です。おそらく、この楽章、とりわけ最初のメロディは、作曲者がボッケリーニであることを知らなくても、多くの人が聞き覚えのあるものではないでしょうか。
このメヌエットは、古典派のメヌエットとしては非常に軽快で、ふわふわと空中を浮いているかのように漂うような旋律を持っています。ボッケリーニは一般に微妙なニュアンスに溢れた音楽を得意としていましたから、この曲はそうした彼の長所が遺憾なく発揮されていると言えるでしょう。また、優雅で明るい曲調が、ほの暗い短調の部分によって影を落とされるという点も、ボッケリーニの特徴の一つです。この明と暗の対比は、ボッケリーニが主にスペインで活動したことと関連があるのではないでしょうか。
このメヌエットは、古典派のメヌエットとしては非常に軽快で、ふわふわと空中を浮いているかのように漂うような旋律を持っています。ボッケリーニは一般に微妙なニュアンスに溢れた音楽を得意としていましたから、この曲はそうした彼の長所が遺憾なく発揮されていると言えるでしょう。また、優雅で明るい曲調が、ほの暗い短調の部分によって影を落とされるという点も、ボッケリーニの特徴の一つです。この明と暗の対比は、ボッケリーニが主にスペインで活動したことと関連があるのではないでしょうか。
ジョアッキーノ・ロッシーニ
- ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲
ジョアッキーノ・ロッシーニ(1792~1868)は19世紀初期を代表するオペラ作家の一人です。その彼が最後に書いたオペラが1829年、パリで初演された「ウィリアム・テル」でした。原作はドイツの文豪フリードリヒ・シラーの同名戯曲です。舞台は14世紀初頭のスイス。悪代官ゲスラーの圧政に苦しむスイスの民衆を解放すべく立ち上がった英雄ウィリアム・テルの活躍を描いています。反骨心に富む猟師テルが、ゲスラーの奸計によって、最愛の息子の頭に載せた林檎を弓矢で射落とさなければならない場面はことに有名です。

ピアノを弾くリストを囲むロッシーニ(リストのすぐ後ろ)、デュマ、ユゴー、パガニーニ
このオペラは全4幕のグランド・オペラで、ロッシーニ円熟期の傑作ですが、あまりに長大なためか舞台にかけられることはほとんどありません。しかし、序曲はオーケストラの演奏会において不可欠なレパートリーとして定着しています。この序曲は4部分からなります。チェロの四重奏で始まる最初の「夜明け」は、悲しげな旋律に満ちており、スイス民衆たちの苦しみを表しているかのようです。続く「嵐」は雨が徐々に降り出し、激しい嵐になっていくさまを巧みに表現しています。そして嵐が止んだ後、第3部の「静けさ」では、イングリッシュホルンの独奏によりのどかな田園風景が描写されています。そして、最も有名な部分である最後の「スイス軍隊の行進曲」は圧政からの解放を告げるかのような、歓喜に満ちた勇ましい行進曲です。この序曲は、ロッシーニの序曲で基本となっていたソナタ形式によらず、互いに関連のない4つの部分をつなぎ合わせたもので、苦悩を克服して歓喜にいたるオペラの粗筋を明確に予告するものとなっています。オーケストレーションの巧みさもたいへん印象的です。

ピアノを弾くリストを囲むロッシーニ(リストのすぐ後ろ)、デュマ、ユゴー、パガニーニ
このオペラは全4幕のグランド・オペラで、ロッシーニ円熟期の傑作ですが、あまりに長大なためか舞台にかけられることはほとんどありません。しかし、序曲はオーケストラの演奏会において不可欠なレパートリーとして定着しています。この序曲は4部分からなります。チェロの四重奏で始まる最初の「夜明け」は、悲しげな旋律に満ちており、スイス民衆たちの苦しみを表しているかのようです。続く「嵐」は雨が徐々に降り出し、激しい嵐になっていくさまを巧みに表現しています。そして嵐が止んだ後、第3部の「静けさ」では、イングリッシュホルンの独奏によりのどかな田園風景が描写されています。そして、最も有名な部分である最後の「スイス軍隊の行進曲」は圧政からの解放を告げるかのような、歓喜に満ちた勇ましい行進曲です。この序曲は、ロッシーニの序曲で基本となっていたソナタ形式によらず、互いに関連のない4つの部分をつなぎ合わせたもので、苦悩を克服して歓喜にいたるオペラの粗筋を明確に予告するものとなっています。オーケストレーションの巧みさもたいへん印象的です。
カール・マリア・フォン・ウェーバー
- ウェーバー:「舞踏への勧誘」作品65

ウェーバーを描いた切手
カール・マリア・フォン・ウェーバー(1786~1826)は、「魔弾の射手」をはじめとするオペラによって、19世紀初頭のドイツ語オペラを推進した作曲家として有名です。しかし、ウェーバーは非常に優れたピアニストでもあり、ピアノのための作品を多く残しています。4曲のピアノ・ソナタなども、古典的な形式のなかにロマン的な色彩を盛り込んだ点が魅力的ですが、やはり彼の魅力は小品で発揮されているのではないでしょうか。ウェーバーが作曲したピアノのための小品のうち、圧倒的に有名なのが「舞踏への勧誘」(1819年)です。
この作品はいくつかの短いワルツがメドレーのようにつなぎ合わされるという構成をとっています。そして、ワルツに先立ち、ゆっくりとしたテンポの序奏が置かれています。この序奏では、紳士が一緒にワルツを踊りましょうと淑女を誘い、彼女は初めははにかみがちでしたが、徐々にうち解けていって紳士の申し出を受けるというようすが描写されていきます。そして、ワルツが始まり、二人の華やかなダンスが繰り広げられるのです。そしてワルツが終わって二人が挨拶を交わす場面を描写した静かなコーダとなります。ワルツが余りにも華やかに終わってしまうので、コンサートではここで曲がお終いだと勘違いしたお客さんが拍手喝采をしてしまうということがよく起こるそうです。
この「舞踏への勧誘」は、オリジナルのピアノ独奏版よりも、ベルリオーズによる管弦楽編曲版のほうでむしろ知られています。確かに絢爛豪華なオーケストレーションを伴う編曲版は原曲の性格を強調した素晴らしいものです。しかし、華麗な演奏技巧を駆使した原曲のピアノ独奏版にも捨てがたい魅力があるのも確かなことでしょう。また、描写的な要素をもち、序奏とコーダを伴う小ワルツの連なりという構成は、19世紀におけるワルツの手本となっています。
この作品はいくつかの短いワルツがメドレーのようにつなぎ合わされるという構成をとっています。そして、ワルツに先立ち、ゆっくりとしたテンポの序奏が置かれています。この序奏では、紳士が一緒にワルツを踊りましょうと淑女を誘い、彼女は初めははにかみがちでしたが、徐々にうち解けていって紳士の申し出を受けるというようすが描写されていきます。そして、ワルツが始まり、二人の華やかなダンスが繰り広げられるのです。そしてワルツが終わって二人が挨拶を交わす場面を描写した静かなコーダとなります。ワルツが余りにも華やかに終わってしまうので、コンサートではここで曲がお終いだと勘違いしたお客さんが拍手喝采をしてしまうということがよく起こるそうです。
この「舞踏への勧誘」は、オリジナルのピアノ独奏版よりも、ベルリオーズによる管弦楽編曲版のほうでむしろ知られています。確かに絢爛豪華なオーケストレーションを伴う編曲版は原曲の性格を強調した素晴らしいものです。しかし、華麗な演奏技巧を駆使した原曲のピアノ独奏版にも捨てがたい魅力があるのも確かなことでしょう。また、描写的な要素をもち、序奏とコーダを伴う小ワルツの連なりという構成は、19世紀におけるワルツの手本となっています。
ニコロ・パガニーニ
- パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調作品7

ニコロ・パガニーニ
ニコロ・パガニーニ(1782~1840)は、19世紀前半を代表するヴァイオリン奏者です。その演奏は、彼以前の演奏者たちが誰も考えつかなかったような華麗な技巧に満たされていたと言われ、その人間業とは思えないアクロバティックな技巧のせいで、「パガニーニは悪魔からヴァイオリン演奏を習ったに違いない」という噂が立てられたほどでした。パガニーニの名声があまりにも高かったために、ライヴァルのヴァイオリン奏者たちは彼の技巧を模倣しようとやっきになっていたらしいのですが、パガニーニは自作の楽譜を他人には公開しなかったと言われています。
パガニーニが作曲したヴァイオリン協奏曲は6曲が現存しています。そのなかで1826年の第2番は、終楽章のロンド「ラ・カンパネッラ(鐘)」の主題に基づいて、後にフランツ・リストがピアノ独奏曲を作曲したことでたいへん有名です。リストは若い頃にパガニーニの演奏を聴いて夢中になり、「ピアノのパガニーニ」を目指して精進したと言われています。原曲の協奏曲は、パガニーニの超絶技巧が余すことなく発揮された難曲の一つで、リストが心を奪われたというのも頷ける話ではないでしょうか。
パガニーニが作曲したヴァイオリン協奏曲は6曲が現存しています。そのなかで1826年の第2番は、終楽章のロンド「ラ・カンパネッラ(鐘)」の主題に基づいて、後にフランツ・リストがピアノ独奏曲を作曲したことでたいへん有名です。リストは若い頃にパガニーニの演奏を聴いて夢中になり、「ピアノのパガニーニ」を目指して精進したと言われています。原曲の協奏曲は、パガニーニの超絶技巧が余すことなく発揮された難曲の一つで、リストが心を奪われたというのも頷ける話ではないでしょうか。