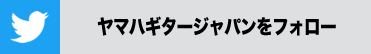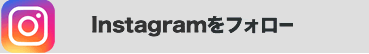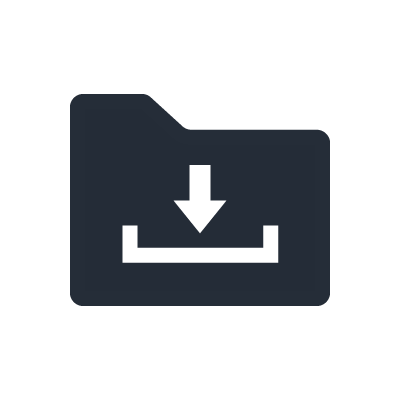匠の作法Vol.1 MLB選手も愛用するミズノのグラブとヤマハギターの職人対談

匠の作法Vol.1 MLB選手も愛用するミズノのグラブとヤマハギターの職人対談
たしかな技術と強いこだわりを持った職人たちの手によって、進化を続けてきたヤマハギター。一流の職人たちのものづくりに対する哲学は、たとえつくるものが変わっても、共通する部分が数多くあるのではないでしょうか。
アコースティック、クラシック、エレキなど、日本産ハイエンドギターを担当するヤマハの職人・鈴木唯弘氏と、MLBの選手をはじめ、数限りないグラブを手がけてきたミズノのクラフトマン、伊藤則史氏。ともに最上級の作品をつくり続けてきた二人の対談は、素材へのこだわりや、主役である使用者への思いなど、ギターとグラブという垣根を越えて、繰り広げられました。
音楽と野球。世界中にいるプレイヤーを支え続けてきた二人
ヤマハ・鈴木唯弘(以下、鈴木):今日はお会いできて嬉しいです。私自身が中学時代に野球をやっていたこともあり、お話できるのを楽しみにしてきました。
ミズノ・伊藤則史(以下、伊藤):野球経験者でいらっしゃるんですね。私は、ほかの分野のものづくりに携わっているクラフトマンの話を聞くのが、とても好きなんです。こちらこそ、今日はよろしくお願いします。

(左)ヤマハ 鈴木唯弘 (右)ミズノ 伊藤則史氏
鈴木:先ほど作業場を見学させていただきましたが、それぞれの工程ごとにクラフトマンの方がグラブと向き合い、完成させていく様子に、とても興奮しました。
伊藤:グラブの製造工程は、材料である牛の革の選定から最後の仕上げまで、多岐にわたるのですが、各クラフトマンには時間をかけてすべての工程を経験してもらい、一通りできるようになってもらいます。いわゆる「多能工」ですね。自分がいま携わっている工程が、グラブ全体に、そしてほかの工程にどういった影響を与えるかをすべて把握したうえで、作業にあたっているわけです。

鈴木:それはギターでも同じですね。ギターづくりは、使用する材料を決めてボディーをかたちづくる「前工程」と、棹(ネック)の取りつけや仕上げを施していく「後工程」に分かれています。もちろん、そのなかでさまざまな工程があるのですが、職人たちはすべてを学んだうえで、一つひとつの作業にあたっていきますから。
なぜ、職人に? そして、その醍醐味とは?
鈴木:伊藤さんは、どういった経緯でミズノのクラフトマンになられたのですか? 私は、小さいころから木を使ったものづくりが好きで、林業高校に進み、ギターづくりに携わるようになりました。もう20年ほどギターをつくり続けています。
ギターという楽器は、構造自体はすごくシンプルなのですが、多くの人々に愛される美しい音を奏でることができる。さらにその音色は、一つひとつのパーツの素材や加工方法、組み合わせによって、驚くほど変化します。ギターづくりに携わるなかでそのおもしろさ、奥深さにどんどん魅了されていきました。いまでも、設計者がつくったギターの図面に対して、「こうしたほうがよりよい音が出せるんじゃないか」と提案しながら、日々模索しています。

伊藤:私は小学校時代からずっと野球をやっていて、将来も野球関係の仕事に就きたいと思っていたんです。転機は高校1年生の終わりでした。野球部の友人たちが「プロパー」ではなく、「別注」のグラブを購入していたんです。
グラブを手づくりしている人たちがいること、そしてそういった仕事があることを、そのときに初めて知りました。その友人に影響されて自分も別注のグラブを購入したのですが、そのグラブに初めて手を入れたとき、まるで何かが降りてきたように、「あ、自分がやりたいのはこれだ!」と心が決まったのです。野球部の監督からは、大学でも野球を続けることを薦められていたのですが、自分としては一刻も早く、グラブづくりをしたかった。ミズノの入社試験を受け、今日、みなさんにお越しいただいたこの波賀工場というグラブ製造専門の工場に入社してから、2018年の3月で丸26年になります。

鈴木:この仕事をしていて、一番の喜びを感じる瞬間、あるいは逆に苦しいと感じるのはどのようなときでしょうか。私は不思議と、苦しい思いはほとんどないんです。自分の感性で素材を選び、最終的に満足のいくギターが完成したときのやりがいや充足感が、圧倒的に大きいんですよね。
さらに、そうやって手塩にかけてつくりあげたギターが、実際に使われているのを見ると、代えがたい喜びを感じます。ある有名なミュージシャンがNHKテレビ『紅白歌合戦』出演時に演奏するギターを、私たちで手がけたことがあるんです。テレビの画面のなかで、自分たちのつくったギターが使われていて、その音を全国の人たちが聴いてくれている……。私自身は音楽をつくることはできませんが、自分がギターに込めた思いも含めて、表現していただいているような気分になりました。
伊藤:私も苦しいという思いはありません。そしてやはり、プロの選手であっても少年の選手であっても、自分たちがつくったグラブを使ってプレイしている姿を見るのが、何より嬉しいです。テレビでも、雑誌でも、あるいは近所のグラウンドであっても、ミズノのグラブは、見ればすぐにわかります。そういう光景に出会えることが、一番の喜びです。
「数あるグラブメーカーの中から、ミズノを選んでいただきありがとうございます」という気持ちですね。

伊藤:そのうえで、気をつけていることが、2つあります。ひとつは、自分ひとりの力で成し遂げたことではない、と肝に銘じること。1人の力でできることは限られています。グラブは、材料の調達から完成品の出荷まで、チームのみんなで力を合わせた結果なんですよね。それは自分に言い聞かせるとともに、一緒に働く仲間にも言うようにしています。その謙虚さが、よりよいものづくりにつながると信じています。
あくまでも、主役は使用者
鈴木:なるほど、おっしゃる通りだと思います。もうひとつはなんですか?
伊藤:当然かもしれませんが、どれだけ使う方の立場になれるか、ということですね。具体的には、選手が望んでいる使い心地に、いかにフィットさせることができるか。自分がいいと思うこだわりも重要ですが、選手が求めているものから離れてしまっては意味がない。「我」を入れすぎることなく、ある意味では、自分をどれだけ消せるかが重要になると思います。一方で、そこまでいっても消せないものが、本当のこだわりや魂なのでしょうね。
鈴木:使う方のために、ということは、私もつねに考えています。ギターは、温度や湿度などの環境によって、音色が大きく変化します。私たちのギターを手にしてくださった方の演奏環境はわかりませんが、それでもできるだけベストな音が鳴ってほしい。素材を吟味し、最高の「鳴り」になるよう手を尽くすときは、演奏者のことをいつも頭に思い浮かべています。
伊藤:選手のみなさんの意見や要望に対応するためには、技術を磨くだけでなく、それを理解するための感覚や感性も磨いていかなくてはなりません。そのために、私は革を噛んだり舐めたりすることもあるんですよ(笑)。
選手が使用して革がなじんでいく過程で、どういう状態になっているのか。跳ね返ってくる弾力や、馴染み方を歯や舌で確かめるんです。選手が求める微妙な感覚のちがいを具現化していくためには、こういった努力も欠かせません。

鈴木:素材を知ることは、ものづくりにおいて重要なポイントのひとつですよね。ギターの場合、木の種類によって音が変わるのは当然ですが、それぞれの木が持っている「顔」も、音に影響を与えるんです。木目が詰まっていると高音が伸びたり、逆に幅が広いと芯のある音になったり。
もちろん、見た目が綺麗であることも大切です。それらを理解したうえで、「最終的にこういう音が鳴るようにしたい」と考えながら、1本のギターに使う材料の組み合わせを決めていきます。良質な木材であればいい、ということでもなく、すべてのバランスを考えなければ、上質な音にはなりません。
さらに、木を加工していく際にも、細心の注意が必要になります。ちょっとした削り方ひとつで、音がまったく変わってしまいますから。

伊藤:よくわかります。木と同じように、天然皮革は種類によって質感がまったく異なりますし、一枚の革のなかでも、場所によって柔らかさが全然ちがう。ですから、革のどの部位をグラブのどこに使うのか、どういった組み合わせで使うのか、つくりはじめる前から仕上げまでイメージします。
しかし工程を踏めば踏むほど、革には大小さまざまなストレスがかかってしまう。ですから私は「いかに革に不要なストレスを与えずにつくり上げるか」にこだわっています。同じ柔らかさの革であっても、ストレスがかかりすぎて、しわくちゃになってしまったがゆえの柔らかさと、素材のいい状態をキープしながら成形できたときの柔らかさは、まったく異なります。
素材が本来持っている魅力を保ち、その特長が死んでしまうようなストレスを極力避けていくわけです。ほかの人が見てもすぐにはわからない、つくった人間と使う人間の感覚の世界の話かもしれません。
技術を学び、そして伝えていくこと
鈴木:そうした感覚や技術を先輩方から学び、そして次の世代に継承していくことも重要ですよね。伊藤さんはどうしていらっしゃるのですか。
伊藤:最初に「多能工」の話をしましたが、いまの時代は生産性も向上させる必要があるので、1つの工程の技術だけにこだわることは、昔よりも難しくなっています。クラフトマン全員がすべての工程を学んだほうが、全体の生産力は上がりますからね。それでも、1つの工程に何年も従事して、繰り返し作業するなかでこそ掴める発見は、大事にすべきだと思っています。
自分の経験からいえば、1、2年で作業をこなせるようになっても、3年、5年と経つうちに、それまで体験したことのない感覚が出てくる。力の入れ方から道具の持ち方まで、いろんな発想や改善策が思い浮かぶようになる。さらに、ほかの人の作業を見るようになって、視野が広がっていくわけです。そういったことを共有できるように、誰かが壁にぶつかっていたらチーム全体で勉強会を開くなど、いろいろな工夫をしています。

伊藤氏がグラブづくりに使用している道具
鈴木:新しい発見は、いつまでもありますよね。私が作業しているすぐ隣に、大ベテランのギター職人がいるんです。その方の作業と自分の作業を見比べると、同じことをやっているように思えても、体の使い方、ノミの持ち方が全然ちがう。学び、つねに改良していかなくてはならないと思っています。

鈴木氏がギターづくりに使用している道具の一部
鈴木:また、先輩だけでなく、後輩からも学ぶ瞬間はあります。それぞれが自分の感覚をもとに創意工夫していますから、後輩の作業を見ていて「あ、こんなやり方もあるんだ」と初めて気づくこともある。教える立場でありながら、教わる立場でもあることを実感します。
伊藤:結果は一緒なのにアプローチがちがうということは、よくありますよね。私もいまでも後輩から学ぶことがあります。人を観察すれば、気づきがいっぱい出てくる。そういう目をもっていないと、ものづくりの進歩、進化はないんだろうな、と感じます。
変わっていく時代のなかでも、変わらない思い
鈴木:進歩、進化でいうと、将来の目標や理想のグラブなどはありますか? 私の場合は、いつか機械をまったく使わず、自分の手ひとつでギターをつくってみたいという思いがあります。これは、先ほど伊藤さんがおっしゃられた「我」、エゴなのかもしれませんが、自分の感覚だけを頼りに、腕一本でやってみたいと思うんです。
伊藤:選手によって求められるものがちがいますから、理想のグラブを語るのは難しいですが、ものづくりをしている以上、納得することはありません。むしろ納得して、気持ちや情熱、探究心が出てこなくなってしまったら終わりだと思っています。ですから、これからもずっと、どうすればよりよい製品ができるのかを考え続けていくでしょう。それこそが、われわれの存在意義だと思います。
テクノロジーがどんどん進化して、いまは3Dプリンターが登場しましたが、「グラブをつくれるものならつくってみてほしい」という気持ちでいます(笑)。少なくともいまの段階では、選手の感覚を具現化するのは、機械では難しいはず。選手が最初にグラブを手にはめたときに、少しでもダメだと思われたら、もう二度とつけてもらえないこともあります。そのときに納得してもらうための微細な感覚を、諸先輩方は長い歴史をかけて積み重ねてきたんですよね。

鈴木:そうですね。技術的には、ギターも3Dプリンターで一通りはつくれるでしょう。でも、その先の「演奏者にとってベストな音をどこまで表現できるのか」といったことについてはまだわからないなと感じます。
伊藤:一方で、もしかしたら機械によって、感覚の世界も緻密に実現できるようになるかもしれない。そうしたら私は素直に、「やっとできたんだ!」と喜ぶと思います(笑)。ものづくり全体が新たな段階に入っていくので、面白いとさえ感じるでしょう。
ものづくりは決まったレールが敷かれていない、茨の道だからこそ楽しいし、学びつづける喜びがある。「ああ、生きているな」という思いさえ抱きます。感覚を研ぎ澄ませていくことで、自分自身がどんな境地に立てるのか、ギターを含めたすべてのものづくりがこれからどうなっていくのか、すごく期待しているんです。
取材・文:宮田文久 写真:倉科直弘
プロフィール
鈴木唯弘
1971年生まれ。1990年に株式会社飯田製作所(現・株式会社ヤマハミュージックマニュファクチュアリング) 入社。アコースティックギターを中心に、使用木材の選定、ボディーの形づくりや組み立てなど、「前工程」と呼ばれる製造工程を中心に担当。ヤマハのハイエンドクラスのギターづくりを支えている。
伊藤則史
1973年生まれ。1992年に株式会社ミズノインダストリー波賀入社(現ミズノテクニクス株式会社 波賀工場)。試作開発課課長。多岐にわたるグラブ製造過程を統括しながら、「プロパー」(スポーツ店などで販売されるモデル)の開発や、「別注」といわれるオーダーグラブの製作を担当。さらに、MLBの選手たちを中心とした、プロユースのグラブを手がける。