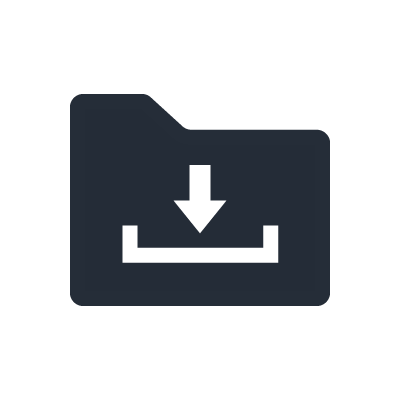海津幸子(かいづ・さちこ)

優雅なたたずまい、好奇心あふれるライフスタイルで独自の世界観を醸し出す、才気あふれるピアニストであり、多彩な活躍を続けるエレクトーン奏者・海津幸子さん。演奏活動のほかに、プロデュース的な活動もこなし、多くの人を惹きつけて止まない。
—オペラの伴奏、コンチェルトの演奏、そして、新作委嘱作品の演奏とアルバム制作など、幅広く活動されています。
どうもひとつのことだけやっているのでは、閉塞感を感じてしまってダメなんです。例えば、私はオペラが大好き。どうしてかと考えると、総合芸術として、音楽も美術も演出も含めてトータルでどう見せるか聴かせるか、バランスのいいところを見つけるのが大好きなんです。トータルして見ていくのが好きというのと、エレクトーンが好きというのは、似ているかもしれませんね。
—海津さんは、エレクトーンとはいつ頃出会われたのですか?
私は、ガシガシのクラシックのピアノ科卒業ですが、中高一貫校でオーケストラに入って朝から晩までフルートを頑張っていましたし、音大時代は合唱サークルに所属して伴奏を頼まれるようになり、声楽家とのお付き合いが多かったんです。エレクトーンを初めて弾いたのは、大学を卒業する頃、足繁く通っていたウィリアム・ウーさんの声楽研究所で。当時はオペラでエレクトーンを使い始めたばかりで、平部やよいさんや加曽利康之さんが演奏するのを他人事として見ていました。それが、あるコンサートの本番直前に、「鍵盤だから弾けるでしょう? 足使わなくてもいいから」とだまされて(笑)、演奏したんです。でも、触ってみたら面白かった。当時はHS型が発売されたばかりで、シンセサイザー的な機能が凝縮されていて「このボタンは何?」「エディットって何?」という好奇心が先に立ったんです。
—ピアノとエレクトーン、それぞれの楽器に対するスタンスは?
やはり、私の場合、ピアノでインプットされている部分が多いですが、自分の想いをアウトプットするには、エレクトーンとピアノがあるからあきないでやっているのかと思います。どっちも自分のツールとして大事だし、好きです。音楽を表現するのはツールである楽器ではなくて、人間。そういう意味では、ピアノだったら基本的に表現だけを追求すればいい。しかし、エレクトーンは音楽と向き合う準備のためにアレンジやレジスト作りもあります。とくに、STAGEAになってできなかったことができるようになっちゃうとそれを追求したくなるでしょ。演奏している間もどこか客観的に、レジストはうまくいっているかとか見極めなくてはいけない。でも、それは音楽に向き合うということとは方向が違う…。そこをどういうふうにやるかというスタンスは、最近ようやくできてきたかもしれない。これは要るけれど、これは要らないと迷わずにいけるようになってきたかなあ。
—最近とは、意外です。何かきっかけがあったのですか?
まず、震災があって、音楽をやっていて、なんの役にも立たないと考え…。その後、アメリカやイタリアに行く機会があり、そこで多くの人が気にかけてくれ、ありきたりですが、絆というものを感じました。イタリアでは交通事故に遭って怪我をしてしまったのですが、実は、幼年期からこれまでで、あのときが一番自分の時間が持てたんです。いろいろなことを考えたり、感じたりできました。リセットできて、どうやって生きていくかは自分の意志でセレクトしていけるし、セレクトしていくべきだと思えたんです。命拾いして怖いものはないし。今までやってきた音楽を取り込み、どう発信していくか考えました。エレクトーンの長所を最大限生かせる形で使いたい。私なりにやってきた経験とか、周りのアドバイスに耳を傾けていろんな意見を取り込む体勢を作り、若い人が出ていく場を作りたいと考えています。
—今後は、どのような活動をお考えですか?
オペラをやっていきたいです。そういうときにエレクトーンは欠かせない。また、同好の士を集めたエレクトーン伴奏によるコンチェルトのコンサートを立ち上げて8年になりますが、コンチェルトを演奏してみたいソリストはすごく多い。アンサンブルの楽しさをわかってもらいたくてピアノを習っている子どもたち向けのエレクトーン伴奏もしています。合わせるのは難しいですが、こちらが盛り上げると子どもも盛り上げてくるんですよ。ダンサーとのコラボレーションでは、我々が想像もつかないアイディアが出てくる。それをよーく聞いていると「それって、あり」とか発見できるんですね。インスパイアされつつ、自分の思っているものと違うものができていいんです。そんなふうにお友だちがいっぱいいるのは面白い。お友だちを作ることでエレクトーンの可能性が出てくると思うんです。
—最後に、海津さんにとってエレクトーンとはなんでしょう?
エレクトーンとは、90歳になってもお友だちでずっといると思いますね。自分の片腕、自分を表現するもののひとつのツールとして、一生のお友だちだと思います。