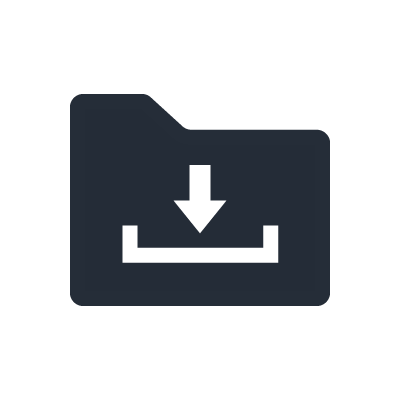菊地友夏(きくち・ゆか)

バレエ、ミュージカル、オペラの演奏やサックス、ヴォーカル、ピアノとの共演などなど、幅広いフィールドで自身の表現の場を求めて活動する菊地友夏さん。その積極的な活動の原動力とは?
—エレクトーンとの出合いは?
母がヤマハ音楽教育システム講師をしていて、2歳から音楽教室に通いはじめました。母の勧めと、父も趣味で音楽をやっていますが、エレクトーンのほうが総合的な音楽の力がつくんじゃないかと勧めてくれて、ジュニア科専門コースに入る時に、エレクトーンを選びました。創作コースに通って、演奏研究会に通って、JOCにも…。ジュニアエレクトーコンクールやアンサンブルと、ザ・エレクトーンっ子でした。国立音楽大学も電子オルガン専攻です。
—クラシック専門で?
そうですね。小さい頃からロックやポップスはあまり聴かず、高校時代もオーケストラ部でクラシック。担当はチェロで、楽器を持って歩いていると、チェロが歩いていると言われていました。当時より、今のほうが仕事に関係なくいろいろな音楽を聴いているかもしれません。妹もエレクトーンをやっていて、家には音楽が普通に流れていましたし、特別な感覚もなく、音楽が生活の一部でした。
—エレクトーンを仕事にしようと思ったのはいつ頃ですか?
音楽を仕事に、という小さな覚悟をしたのは中学2年生の頃でした。それまで当たり前だった音楽をすることが実は特別なことで、仕事にしないのなら音楽は趣味になってしまうんだ、と感じとって。私はエレクトーンしかできないから迷いはありませんでした。といっても、大学4年までは目の前のことに精一杯で、将来のことを考える余裕はなかったですね。4年間を終えて、何かわからないけど頑張ったという自信をつけて、学生生活最後にいろいろ周りを見はじめ、エレクトーンで演奏したいと思いました。
—何かきっかけがあったのですか?
卒業するかしないかというときに、バレエをやっている叔母に誘われて東京シティ・バレエ団の『カルメン』(台本・構成・演出・振付:中島伸欣)を観に行って、衝撃を受けてしまって。音楽も生演奏で、ビゼーの曲をいろいろ組み合わせて使っていました。舞台を見てこんなにも感動したのは初めてでした。こういう時間、こういう空間を作る側に立ちたい! 私ができるとしたら、エレクトーン演奏しかないと。その後、東京シティ・バレエ団の小林洋壱さんにホームページからコンタクトをとって、お会いできたんです。エレクトーンの話をして、フレッシュコンサートを見にきてくださって。それからしばらくは何もなかったのですが、エレクトーンシティ渋谷でコラボレーションさせていただきたい、という企画を持ち込んで、それが実現し、回を重ねています。
—バレエとの共演のほか、いろいろな演奏活動を積極的に行っていますね。
ブライダルの仕事は事務所に所属してシフトで行っています。卒業してから、バーやカフェでピアノの生演奏を募集しているところに行って、エレクトーンを弾かせてほしいと言いD-DECKを持ち込んだり、自主企画では、王子の北とぴあプラネタリウムでコンサートを行ったり…。群馬のアマチュアミュージカル劇団「アラムニー」を家族で観に行って感動し、打ち込みだった音楽を私に生で弾かせてほしい、と売り込んで。最初は、3時間の長尺を一人では無理と言われたのですが、録音だったらやりません、と。演奏を聴いてもらって、1年くらいして認めていただけるように。これまでに3作をやりました。
—ミュージカルのアレンジ、演奏は大変なのでは?
ミュージカルに関していうと、一つの舞台の中でいろいろなジャンルの曲があります。クラシックっぽいもの、ジャズっぽいものロックもあったりして。そのどのジャンルにもエレクトーンはいい感じに対応できます。また、ミュージカル音楽はバンドに型がないんですね。オーケストラだったものに、エレキギターが入ったり、ドラムが入ったり。エレクトーンがそういうミュージカルの形態にすごく合っているんです。シンフォニーで弾いていてもエレキギターが入っていける。簡単にできるし、ここがもうちょっとほしいと思ったら、無理なくルールもなく加えられる。自分の表現としてできます。なんでもありで一人で作れるのはいいところですね。
—相手のいる仕事ですから、音楽や演奏の力だけではやっていけません。
企画とかマネージメントは昔から好きだったんです。資料作ってチラシ作ってという作業が好きで、学生時代には生徒会をやったり学級委員をやったり…。そういうのが楽しくて。大学ではマネージメントコースの聴講もしていました。
—これからも活躍を期待しています。最後に、菊地さんにとってエレクトーンとは?
自分が表現できるツールの一つですね。こういうことをやりたいと思った時に、エレクトーンが自分で表現できるツールになる。やはり、『カルメン』を見た時の衝撃が原動力です。あの時自分が感じた"現実世界じゃないみたいな空間"。難しいですけれど、お客さんがそう思ってくれるような空間を目指したいです。