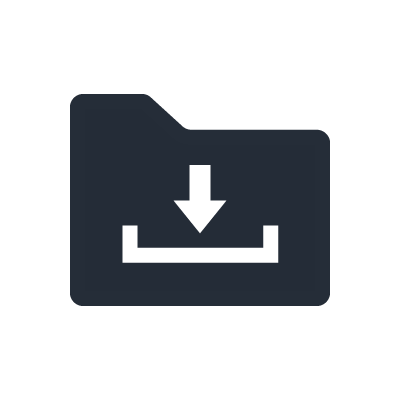森俊雄(もり・としお)

ドイツ・ハンブルクで開催されたインターナショナルエレクトーンフェスティバル’85でグランプリに輝いた森俊雄さん。現在は、日本のミュージカル界を支える音楽家として、第一線で活躍しています。これまでの足跡に加え、これからの展望もうかがいました。
—北海道小樽に生まれ、ヤマハ音楽教室のご出身。小中学校ではスポーツ少年だったとか。
運動能力は小・中学校の頃が絶頂でしたね。サッカー、バスケ、バレー、バドミントン、テニスをこなし、スポーツが大好きだったんです。高校に入って音楽の道を行こうと決め、勉強は必要最低限でエレクトーンにかじりついて練習していました。高校2年の終わりに音大の作曲科に行きたいと思ったのですが、受験科目を考えると私立のピアノ科しか選択肢がないと。コンクールと並行して1年間だけは浪人していいという条件で桐朋学園大学受験に臨みました。
—その結果、インターナショナルで見事グランプリ、受験も合格されました。
ドイツのコンクール開催日程と桐朋の課題曲の発表がほぼ同じ時期で、コンクール後にひと月遅れで課題曲に取り組みました。見ていただいていた桐朋の教授に内緒でコンクールに出たのがばれて、破門されてしまい大変でしたが、課題曲のショパン《バラード2番》が自分に合っていてよかったです。初見の問題がショパンのエチュードのような難解な曲で、入学してから知りましたが、初見は一番の成績だったと。ショパンと初見に助けられましたね。
—ピアノ科の4年間は、森さんにどのような影響を与えましたか?
最初の先生と合わず、後半から小川京子教授がレッスンをしてくださり、ピアノの弾き方からすべて、徹底的に一から直されました。「なんでそんなに一生懸命弾くの? メゾピアノ以上で力を入れてはダメ」「ピアニシモが一番力を使うのよ」と瞬発力を発揮するのは力ではないということを教えられました。また、楽譜どおりではなく、楽譜から自分で発想を膨らませて、「今のあなたがどう感じているかを込めて弾きなさい」と教えてくれました。音楽を考えるうえでいつも指針となっている言葉です。小川先生は偏見のない方で、エレクトーンのコンサートにも来て「続けなさい」と言ってくださった。小川先生の存在は大きいです。
—大学卒業後はエレクトーンプレイヤーになりました。
小川先生には「ピアニストになりなさい」と言われていましたし、学生時代にデビュー前のDEENのオーディションに行き、ビーイングの社長さんに、ソロピアニストとしてオケをバックにデビューしてみないかと誘われたのですが、どうしてもエレクトーンプレイヤーになりたかったんです。
—森さんがミュージカルの世界に入るきっかけとなったのは?
プレイヤーだった2001年に宮本亞門さんからオリジナルミュージカル『くるみ割り人形』の楽曲のオーケストラアレンジをしてくれる人がいないかという依頼がヤマハ音楽振興会にあって。実は、オーケストラアレンジをしたことはなかったのですが、チャンスかなと思って受けました。6日後締め切りで、自己流で書いてオケ入れの朝に提出したのですが、それを亞門さんも作曲家も気に入ってくれて。オケメンバーからも歓声があがったんです。これはいけるかな、と思いました。このミュージカルで初めてピアノとエレクトーン演奏も担当して楽しかったです。これがきっかけですね。その後、最初は2年に一度依頼があって、そのうち1年に一度くらいに依頼が増えていくのですが、ターニングポイントは、2014年と2016年の宝塚OG版の『シカゴ』でした。どんどんミュージカルの仕事が入ってきて、プレイヤーを辞めたのもこのあとです。
—森さんは稽古ピアノもされていますが、どういう仕事なのですか?
『シカゴ』のOG版はもちろん、米倉涼子ブロードウェイ公演時も担当しました。稽古ピアノは歌唱指導から、リハーサルを常に見ながら音楽をつくる役目です。演出がつくと演奏が変わり、歌い方も変わります。歌い手が相談してきたら瞬時に返さなくてはいけません。歌い間違いを確認したり、指摘したりもします。ブロードウェイではミュージカルができあがる過程を見ている稽古ピアノの人が本番の演奏を担当するのが普通です。日本でもそうしてほしいという演出家や作曲家も増えていて、『スィーニー・トッド』『The PROM』など本番も演奏しました。2022年秋に再再演される日生劇場『ジャージー・ボーイズ』の初演から弾き振り、再演からは稽古ピアノも担当しています。
—ミュージカルでエレクトーンを弾くことも。
オーダーはキーボードなのですが、マニピュレーターがつかないときに、自分が音作りしやすいのでELC-02を持ち込んでいます。音色や奏法は、ソロで弾くエレクトーンとはまったく違うと言っていいと思います。キーボードはオケの一員として、足りない部分をサポートするのが役割です。よく混ざりながら埋もれない音色作りが重要です。ティンパニが入っているのに、パーカッションの手が足りないのでこの部分を弾いて、とか。さっきまで本物が鳴っていたのですから、プレッシャーです。奏法では、演奏は歌うためのリードなのでタッチトーンは使いません。立ち上がりのはっきりした音が欲しい、という歌手の指摘があります。ここが改善された音色が搭載されるともっと普及するのではないかと思いますね。
—オケの一員としての演奏で心がけていることは?
全部の音をよく聴くことでしょうか。最初の『くるみ割り人形』で、指揮者に合わせるオケとのタイミングが全然理解できなくて悩みました。今でも格闘しています。同じ鍵盤でもピアノだとオケが合わせてくれるので、気持ちよく弾けるのですが。オケの一員になって間近で生楽器の音を数多く聴き、経験して、混じってやっていくうちに培われたことは大きいですね。現場で聞こえてくる生楽器の音は日々違うんです。ある日は弦がよく聞こえる。また別の日は木管がなんでこんなに聞こえるんだろうとか。それによって自分の集中も変わってくるし、サポートも工夫します。『ジャージー・ボーイズ』のあるシーンで、主役ともう一人が手をタッチするきっかけがあるのですが、毎回違うんですよ。役者はそのときの感情で演じるから、合わせるのがすごく難しい。生演奏の醍醐味であり、恐怖ですよね。
—今後の活動は? さらに、5年後、10年後はどんなことをしていたいですか?
2023年も2月に日生劇場で行うミュージカル『バンズ・ヴィジット』の弾き振りの予定が入っていて、5月にも日本初演のミュージカルでエレクトーンを弾く予定です。また、新しいプロジェクトを今年から立ち上げて、音楽監督として2023年4月、12月に公演を行う予定です。音楽監督として参加している『恋するブロードウェイ』では、いまや人気絶頂の松下洸平や海宝直人、2022年ミュージカル『ピピン』で主役を演じる森崎ウィンといったスターが旅立っていきました。それとは違い、人前に初めて出る素人の子たちを育て、歌って踊るポップなステージを作っていきたいと考えています。そして、5年後、10年後は、以前から目標にしていた“映画の劇伴の仕事”に携わっていたいと思っています。
—森さんにとってエレクトーンとはなんでしょう?
自分を豊かにしてくれる楽器、イメージどおり再現できるし、試して、やり直すことができる。エレクトーンだとアウトラインがその場でダーッとできてしまうので、イメージを作るには最適の楽器です。
【2022年6月インタビュー】