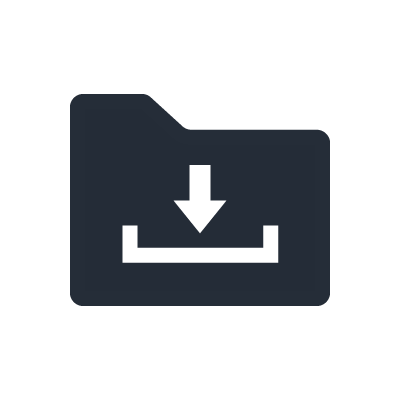海津幸子(かいづ・さちこ)

ピアニストでエレクトーン奏者の海津幸子さんは、好奇心の塊のような音楽家。ピアノと同じ鍵盤楽器ながら全く別の楽器ともいえるエレクトーンに興味を持ち、バイリンガルで道を切り拓いてきました。素地ができてきた今だからこそ、次のフェーズへ向かうときと語ります。
—十数年前になりますが、イタリアの演奏旅行で事故に遭われて大怪我をされて、その後ご自身に変化はありましたか?
3カ月間イタリアで過ごし、リセットできたことは貴重な体験でした。いつも忙しくしていて、周りの友達には(止まったら死んでしまう)回遊魚だ、マグロだとか言われて過ごしていましたが、そのために見えていない部分があったな、と痛感したんですね。とくに仕事関係以外の方たちとの出会いが印象に残っています。ベッドに寝たきりだったので読書が楽しみだったのですが、ローマの航空会社のカウンターにいらした方が、見ず知らずの私にたくさん本を持ってきてくださった。日本から見舞いに来てくれた父と交わしたちょっとした会話で、私の入院を知り、たまたま入院していた郊外の病院にその方も入院されたことがあって、ご主人の実家に行く途中に寄っていただきました。東洋人が一人で心細いだろうとおっしゃって。その後その方とはお会いできていないんですけれど、いただいた恩を自分の周りの方たちに別の形で返して、回していきたいなという気持ちがあります。
あとは、事故の前は運動に全く興味がなかったのですけれど、3カ月寝たきりだと筋肉がすっかり落ちてしまって、体が資本だと実感しました。まずは乗馬を始めました。ただ、時間が取れなくなって、いつでもできるランニングをすることに。現在は、私のおっちょこちょいで転倒して骨折をしてしまいしばらく無理ですが、朝日とともに家を出て走る気持ちの良さ! 体を変え、心も養った10年間でした。
—音楽活動やエレクトーンへの取り組みで変化は?
大好きなエレクトーンや音楽、その周りの人たちから恩恵を受け、学び、出会いがあって、そのなかで私が培ってきたことを、エレクトーンの世界で自分が何らかの形で貢献できないかという思考が芽生えました。なかでも後進への思いは強くなってきています。
—どのような若い演奏家に期待しますか?
この楽器ならではのアーティスティックなものを作ろうという視点で、世の中に打ち入るような演奏家を応援したいですね。私たち世代は、一人ひとりがアーティスティックな部分で勝負する覚悟をもって、謙遜しながら、協調しながら、クラシックの世界に挑み、地味だけれども演奏を続けてきて20年経ちました。もう素地はできています。私たちとはスタートラインが違うんです。新しいことに挑み、多くがわかってくれなくても2人でも「いいね」と言ってくれたら大成功。凹まずに続けていけるメンタルを持ってほしいと考えています。若い人たちに指導するときも、「きれいに演奏して、それだけでいいの? それで人が感動できる?」とあえて投げかけます。想定外からくると「おっ」と思うところからも感動はある。ピアノやバイオリンのような市民権はまだ得られていませんが、クラシックの音楽界で、エレクトーンは生楽器以上に可能性は大きいと思うんです。突き抜けた若い人たちが出てくるのが楽しみです。
—そのために若い人が学ばなければいけないことは、なんでしょうか?
クラシックの常識的なことはベースとして学ぶべきですが、自分が創意工夫していく姿勢、新しいことを考える発想力が必要で、それは手本がないので学べるものではないですね。いろいろなものを見たり聴いたりということなんじゃないでしょうか。音楽に対しては謙虚ではなければいけないけれども、自分がこの世界の中でどういうふうに動いたらいいか、はみ出すくらいアグレッシブに考えてほしいし、実行してほしいと思っています。
—海津さんご自身の活動は?
もちろん、まだ世代交代をしたいというわけじゃないですよ。次のステージを目指していきたいですね。コンチェルト・コンサートというシリーズを続けていますが、ピアノ・コンチェルトって、音大のピアノ科を出ていても、指導ができない先生が多いんです。オーケストラと協演できるのはわずかな人だけで、体験していないから。でも、エレクトーンでコンチェルトできますよ、と広げていきたい。しかも、エレクトーンはオーケストラとは別のアンサンブルができますよ、と。例えばエレクトーン2人とピアノ奏者、そのサウンドは大オーケストラのサウンドですが、実は3人の室内楽的なアンサンブル。オケ以上に緻密なアンサンブルができるはずです。コンチェルトって対話と協調というのがすごく明確にできている曲が多く、一体感を味わいやすい。音楽家同士1回合わせればお互いがわかります。「オケよりもアグレッシブにきてくれるね、いいね」と言ってもらえるし、こっちも気持ちがいい。オケを超えた表現で、聴いてくださる方も納得してくださる演奏が必要ですし、それを目指していきたいですね。
【2024年7月インタビュー】