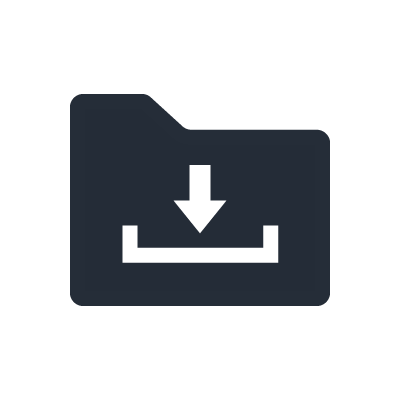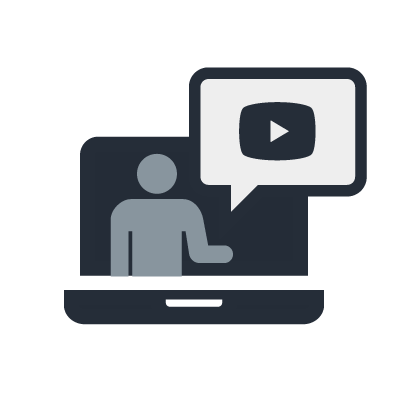Virtual Circuitry Modeling 技術によるオーディオエフェクトの開発
~ ADD-ON EFFECT シリーズからPorticoプラグインエフェクトの開発まで~
VCM 技術とはどう言うものかをデジタルミキシングコンソール用のエフェクト「OpenDeck」を例に解説するとともに、RND 社とのソフトウェアエフェクト開発の経緯とPortico プラグインエフェクトについて紹介いたします。

1. VCM技術の歴史

ヤマハにおける物理モデル技術(自然の音響現象や電子回路の挙動をソフトウェアなどによりモデリング・エミュレーションすることにより楽音合成やオーディオエフェクト処理を行う技術の総称)による製品の系譜は1993年のVL1/Virtual Acoustic Synthesizer(以下VA音源)まで遡ることができます。当時、物理モデル概念による電子楽器商品は他にほとんど例がなく、VL1は実質的に世界で最初の商用物理モデルミュージックシンセサイザーでした。VL1での物理モデルは音響現象のモデリングを行っていたのでVA音源と言う技術名称を与えていました。

研究開発センター Dr. Kこと国本利文率いる「K’Lab」の設立は実質的にはVA音源の開発を始めるための開発チームの編成を行った1987年と言うことになります。当時はK's Labと言う呼称はありませんでしたが、国本はこの時から現在までヤマハの中での物理モデルによる電子楽器開発・オーディオ信号処理開発をまとめる立場であり続けています。
VL1においてもエフェクト部は部分的に電子回路モデリングによる原理を採用しており、その後も物理モデル概念による電子楽器、VP1(弦楽器の物理モデルに基づく)、AN1x(アナログシンセサイザーの物理モデル)、EX5/7(VL、ANのアルゴリズムとそれ以外にも物理モデルのアイデアを盛り込んだシンセサイザー)などの開発を経ながらヤマハ・K's Labの中で物理モデル技術が育まれていきました。2004年に発売されたデジタルミキシングコンソール用オーディオエフェクト(ADD-ON EFFECTS)からVCMと言う技術呼称が与えられるようになり、スタジオで使用されるようなアナログのアウトボードエフェクトやギターアタッチメントなどの物理モデル技術によるデジタルでの再現によって様々なオーディオエフェクト処理が開発・製品化されるようになって来ました。現在ではシンセサイザーMOTIF XS/XFやエレクトリックピアノCPシリーズなどにも多数のVCM技術によるエフェクトが搭載されています。
次章では当初デジタルコンソール用追加エフェクトとして発売し、この度VSTプラグインエフェクトとしても発売することになったVCMエフェクトの中から、「OpenDeck」について技術や開発過程を紹介することでVCM技術について概観します。
2. VCM技術とOpenDeckの開発
OpenDeckの開発を始めた当初、ヤマハ・K's LabではVCM技術によりアナログの電子回路をソフトウェアでモデリングすることで音の良いコンプ、音の良いEQを再現できるようになりつつあり、これらについては言わば「つぼは押さえた」と言える状況でした。そして、次のターゲットを探していてテープへの録音再生のエミュレーションと言う課題に行き着きました。アナログ録音時代の音楽制作の環境や手順を考えるとき、マイクロフォン、ミキシングコンソール、アウトボードエフェクトと並んで録音再生機が大きな位置を占めるのは論を待ちません。当時の状況を今思えば、磁気テープに録音、再生すると言う作業は沢山の楽器を録音したり、全く別のタイミングで録音した複数のオーディオソースを再生・ミックスするための「必要悪」のようなものでした。しかし、テープの録音再生によりいい具合に歪んだりコンプ感が付与されたりにじんだ音になった楽器やヴォーカルの音、こうしたものは当時の楽曲、商業音楽の持つ音楽性の核のようなものでした。それゆえ今日でもリズムトラックだけはアナログのテープに一回「プリント」してからDAWに取り込む、と言ったエンジニアリング手法はデジタル技術中心の現在の音楽制作では一種「ポピュラーな裏技」として定着した感すらあります。
図3にテープレコーダーでの録音・再生の原理を示します。このようなテープへの録音・再生のモデリングはテープへの録音再生機が作られていた当時に基本的には分かっていました。(それなしに録音再生機を作れる訳はないのです)そのモデルのデジタルでの実現は、VCM技術を用いることで、録音アンプから録音ヘッドで起きている現象の再現や、磁気テープからの再生と再生ヘッド以後のNAB規格などで規定される再生EQアンプなどの特性の再現など、要素としては色々あるものの難しいものではありませんでした。したがって図3はアナログテープでの録音・再生原理でありで、かつVCM技術によってOpenDeckに作りこまれたテープレコーダーのモデルのブロック図的表現でもあります。

モデルが出来上がれば測定です。残念ながら開発の当時(2002年頃)においても録音スタジオではデジタルのDAWによる録音再生が主流になって来ており、状態の良いアナログのプロフェッショナルなレコーダーはどんどん減りつつありました。それに加えてアナログのレコーダー特有のアジマスやEQの調整に長けたエンジニアもまた減りつつある状況もありました。こうした状況の中、音楽的に優れたアナログのレコーダーを最高のメンテナンスの状態でキャプチャー(測定)できた我々は幸運だったと言えます。
VCM技術によるモデリングでは録音アンプも再生EQも個別にコンポーネントで再現しているので、録音と再生の機種を変えるのは簡単でした。VCM技術を説明するとき、よくコンポーネントレベルでのエミュレーションをしているという話をしています。実際にはマクロレベルのコンポーネントとデバイスレベルのコンポーネントのエミュレーションと言う対立した概念があり、必要に応じた「ミクロ」さのレベルでのエミュレーションをしています。つまりアンプ単位で十分ならアンプをコンポーネントとしてエミュレーションし、ダイオードやトランジスターのレベルのコンポーネントのエミュレーションが必要ならそれを採用する。一般的にはモデリングによるエフェクトと言いながら一番上の「オーディオエフェクト」と言う一番「マクロ」な塊をいきなりエミュレーションしてコンポーネントのレベルには降りてないものが普通ですが、ヤマハ・K's LabのVCM技術ではケースバイケースで効率とクオリティーによってどのレベルのエミュレーションを行うかを吟味して決めています。
開発において難しかったのは、テープへの着磁やその磁場からの信号の再生の過程が非常に曖昧であり測定が難しいこともあり、モデリングが完成してもそこに実際のテープレコーダーの特性を入れ込む過程が曖昧にしか見えてこないことでした。何を持って必要な「特性」とし、どこにその「特性」のためのパラメーターを入れ込めばいいのか?そして出来上がったモデリングのパラメーターはどうやって物理的な特性と言うより音楽的なサウンドをリアルのテープレコーダーに近づけて行き、それにより実機のような音楽性が得られるようにするのか。開発を始めると、はたと考え込むところが多々ありました。
結局、こうした問題は人間技で解決されて行きました。特性データを技術的に咀嚼してモデルに入れ込む我々信号処理技術者の技とコンサルティングエンジニアの耳の能力を頼りにした膨大な時間をかけた調整作業によって、最終的には4機種のプロフェッショナルレコーダーを参考にした4つのデータセット、Swiss70/Swiss78/Swiss85/America70にまとめられました。特性的に本物と同じものになることよりも必要なのは音楽的な機能性が同じことであり、原器の音の「おいしいところ」がデジタルでも再現されることを目標にチューニング作業が進められました。
一つの例として録音から再生までの振幅周波数特性を示します。図4は現実の4種のアナログテープレコーダーの録音再生特性です。図5にはそれらをVCM技術のOpenDeckにおいて再現した様子を示します。振幅周波数特性の細部までが再現されています。(実際のOpenDeckではテープによる録音再生過程の様々な非線形性もモデリングしていますので、このデータはOpenDeckの特性のごく一部をとらえたものとお考え下さい)

最終的にはコンサルティングと評価の役割でプロジェクトに参画いただいたサウンドプロデューサーの遠山淳氏をして「次世代への貴重なライブラリー」となっていると言っていただける出来になりました。VCM技術によって、リズム楽器などをまとめるのに重要な役割を果たす「テープコンプ感」のみならず、録音バイアスを本来の設定からずらすことによる倍音の制御など、様々な音作りができるプラグインエフェクト「OpenDeck」が完成しました。録音と再生のレコーダーを個別に選ぶことができる機能も好評価でした。スタジオでの音楽制作ではトラックダウンの録音に使ったレコーダーとマスタリングスタジオでの再生に使われるレコーダーが違うことは普通であり、それが再現できることによる音楽の表現の幅は現場にも素直に受け入れられました。

こうしたVCM技術によるオーディオエフェクトはヤマハのデジタルミキサー用のADD-ON EFFECTSシリーズとして2004年に発売されました。この他にはComp276やEQ601のようにレコーディングエンジニアの赤川新一氏に監修をいただいたエフェクトもあります。これらもその音楽性によって非常に高い評価を得ています。図6はヤマハのデジタルミキサーの様々な情報を管理できるPC上のアプリケーションソフトウェアStudio Manager上のOpenDeckとComp276です。
3. RND社とのコラボレーション
VCM技術の特性の再現性や音楽的な力については様々な評価活動やDM/0シリーズやPM5D、M7CLユーザーの皆様、エンドーサーからの情報で確かな手応えとして感じられました。しかし、我々ヤマハ・K's Labの技術がいかに良くても簡単に世間が納得してくれるものでもありません。世の中に我々が持っている技術力を、音楽性の高さを証明するためには我々自身が何か非常に高い目標を達成する必要性があるように思われました。それはどのようなものであるべきか?
一つ、間違いなく王道の方法としてあるのは、アナログの有名な機材をエミュレーションすることです。それも誰もがやっているものではなく、どこのベンダーもまだエミュレーションを成し遂げていない、それでいて有名な「あの機材」であることが望ましい。社内での色々な議論の中でNeve氏のRND社が発売しているアナログのアウトボード、Porticoシリーズが候補として挙がりました。しかしNeve氏は今までアナログ一筋で仕事をして来ており、生半可なことでデジタルの音響処理が得意なベンダーと組むとは思えませんでした。その時、一つの情報がもたらされました。Neve氏がデジタルでの技術開発にも興味を持ち始めていると。兎にも角にもRND社を訪問しRupert Neve氏とミーティングをすることになりました。

2007年のある夏の日、我々はNeve氏の私邸を訪ねました。我々の技術力を証明するためにRND社のイコライザーとコンプレッサーをエミュレーションしたいと言う熱意を伝えるとともに、我々には大いなる準備がありました。K's Labではその頃、アウトボードやコンソール搭載の古今のイコライザーをつぶさに研究し、どんなアナログのイコライザーでもエミュレーションできる技術を蓄積しつつあったのです。それは技術と言うよりノウハウや知見と言った方がいいもので、実際のところ世界中のあらゆるEQをスイッチ一発で模倣する「サンプリング技術」などと言うのは存在し得ない、と言うのもその知見の教えるところでした。ビンテージEQの特性をデジタルで再現する、と言う所業は「一つのソフトウェアによる特性のキャプチャリングによっての再現可能」と言うことにはならない。ノウハウによって個別最適された手法で手間隙をかけて初めて可能になる、と言うのが我々の得ている結論でした。
我々はNeve氏の自宅書斎でのミーティングでVCM技術とその周辺の事情について説明をしました。その時、VCM技術でなし得ることの一つの例として、Neve氏開発の60~70年代のイコライザーの特性を再現するための技術をK's Labでは既に確立していることを説明しました。また我々が、33609などのビンテージコンプレッサーに固有のフィードバック方式コンプレッションをデジタルできちんと再現できる数少ないベンダーであることも説明しました。Portico5043の仕様を見ると、Neve氏がフィードバック方式のコンプレッサーのサウンドにこだわりを持っていることが想像されたためです。そして実際そのミーティングではNeve氏は現状の多くのプラグインエフェクトでのフィードバック方式コンプレッサーへの不満を表明していました。また、我々にとってモデリングは仕事の半分であり、K's Labでは音楽的なサウンドを得るためのフィッティングやチューニングに多くの労力を割いていることについても説明しました。
これらの準備と説明が功を奏して、その日の夕方、Neve氏から我々にヤマハ・K's Labと協業したいとの意思表示がありました。後で分かったことですが、RND社にはそれまでにも幾つかのプラグインエフェクト開発を業とするベンダーからのアプローチはあったそうですが、それらはことごとく拒絶していたそうです。我々がRND社とのコラボレーションを行うチャンスを得られたのは、K's Labの技術やアナログ機材の測定データ的な再現に長けていたと言うことだけではなく、我々が音を第一考えて仕事をしている、ということを理解してくれた結果でした。それなしにはヤマハ・K's LabがRND社との協業と言うフェーズに進むことはなかったでしょう。
4. Porticoのイコライザ・コンプレッサーのモデリング
VCM技術を使ったモデリングの作業は大きくはイコライズやコンプレッションのような機能の実現とアンプやトランスによる音の味付け(我々は「音味」と呼んでいます)の実現の2つに分けられます。多くの場合は機能の実現がまず先行します。
Portico 5033 Equalizerの「フィルター」としての(言い換えるなら伝達関数の)特長は何と言ってもNeve氏得意の独特なシェルフフィルターの特性にあります。 図8、図9、10はNeve氏が60年代後半に開発した有名なNEVE1073とRND社のPortico 5033のローシェルフの振幅周波数特性を示します。Neve氏のこの時代の大きな功績にシェルフフィルターの振幅周波数特性の肩の部分にオーバーシュートを上手にあしらうことによりシェルフの周波数特性を理想形にうまく近づけてまとめる、ということがありました。Neve氏はこのような周波数特性の実現をこの時代から他社に先んじて設計に取り込んでいて初期の1073からFocusrite ISAイコライザーへと引き継がれて行きました。後にこうした特性はSSL社の4000シリーズなどにも大きな影響を与えましたが、Porticoではこの美点がより近代的な回路技術の中に昇華され実現されています。Neve氏のここでのこだわりは大きく言えばシェルフでは台形状の振幅周波数特性の形が理想であると言うことになります。オーバーシュートを注意深く設定すると理想特性に近い振幅周波数応答が得られるわけです。そしてそのオーバーシュートが周波数の設定によって微妙に変化をする、という二次元的な特性変化を持っており、ここまで周到に振幅周波数応答を扱えることこそがNeve氏の匠の真骨頂と言えます。


Portico 5033のローシェルフを実現する4次のフィルター伝達関数にここまでの作りこみがなされていた訳ですが、それをデジタル領域で近似するのはVCM技術を用いれば難しいことではありませんでした。ローシェルフの特性、図9(オリジナル)と図11(VCM技術でデジタルで実現したもの)を示しますので見比べてみてください。
Neve氏にこのようなシェルフフィルターの特性の意味を伺うと、60年代は特にそうですが2トラックにミックスされた状態の音楽コンテンツをイコライザーで操作することでミックスバランスを変える必要があったため、と言う逸話を話しておられました。ステレオミックスされた状態でギターやベースやドラムのバランスを変えるためにこのようなシェルフの特性が作り込まれ、それは現代の音楽シーンにおいてもミックスバランスを変るため、あるいは個別の楽器音の音作りをするための切れ味のいいツールとなっています。そういう時代を超えた普遍性をあの時代に作り込めた才能にはただただ敬服するしかありません。
さて、Portico 5043 Compressorにおいて特にユニークなのはFBというスイッチです。これはコンプレッサーのゲイン制御方式を切り替えるものです。コンプレッサーというのは、主に音量を検出してゲインリダクション量を算出するコンポーネントと、実際入力信号に対してゲインリダクションを与える(つまり入力信号をコンプレスする)コンポーネントからできています。コンプレッサーの制御方式とは、この二つのコンポーネントの関係をフィードフォワード方式にするかフィードバック方式にするかということです。Portico 5043は、FBがオンの時にはフィードバック方式で動作し、オフの時にはフィードフォワード方式で動作します。
実は現代的なコンプレッサーにはフィードフォワード方式が多く、ビンテージコンプレッサーはフィードバック方式がほとんどです。これは、1970年代中盤に開発されたVCAチップによってフィードフォワード方式のコンプレッサーが簡単に構成できるようになったためです。dbx 160などの現代的なコンプレッサーはフィードフォワード方式ですが、それより古い時代に開発されたUREI 1176やTELETRONICS LA-2Aといったコンプレッサーはフィードバック方式になっています。この制御方式の違いは音の違いにも現れます。コンプレッサーの音質は様々な要因で決まりますが、制御方式もその一つです。フィードフォワード方式はナチュラルでサラッとした効きであり、フィードバック方式は粘りが出て腰のある音になります。
Portico 5043のFBスイッチも、やはりNeve氏の深い見識の賜物と言えるでしょう。かつてNeve氏が60年代後半に開発したNEVE2254を始めとするコンプレッサーはフィードバック方式です。現代的なフィードフォワードコンプレッサーの音の良さも、ビンテージコンプのフィードバック方式の良さも知り抜いたNeve氏だからこそ、それらを切り替える機能を実装したのだと思います。

VCM技術では、この制御方式を切替える機能も正確にモデリングしています。図14、15は、実物とモデリングのアタック波形を比較した図です。(図では少し分かりづらいのですが)FBがオンの時の、オーバーコンプによるエンヴェロープ波形の微妙なへこみまで正確に再現していることが分かります。 このようにPorticoのイコライザーやコンプレッサーの基本特性(挙動)の部分のモデリングは比較的早期に完成し、Neve氏にオリジナルハードウェアと比較して確認、納得いただけました。後は音味の完成が仕事としては残りました。

5. アンプ・トランス部分のモデリングとプラグインエフェクトの完成
Portico 5033/5043の入力段と出力段のアンプやトランスは、Porticoの音味を形成する重要な部分であり、モデリングにおいても欠かせない部分です。これらはEQ/コンプレッサーをバイパスにしても信号が通る部分なので、Porticoをラインアンプとして使用した場合にもサウンドがより音楽的になるという効果があります。このアンプやトランスの持つサウンドこそがNeve氏のサウンドの土台を成す部分であり、その上に音楽的な効きを持つEQやコンプレッサーが組み合わされたものが、Portico 5033/5043であると言えるでしょう。
アンプやトランスのモデリングでは、回路図だけでなく、Neve氏から提供していただいたドキュメントが非常に役に立ちました。そこにはNeve氏の設計思想をまとめた文書も含まれていました。つまびらかにはできませんが、そこにはNeve氏の設計技術とその意図、そして音に対するこだわりが書かれており、”良い音”を追求しようとする尽きせぬ情熱が込められていました。
アンプ回路やトランスの設計もまた、Neve氏の技術力と、音楽や音に対する深い造詣の結晶であると言えるでしょう。その本質は、”音楽的な歪みの形成”と言えます。アンプ回路の設計とトランス自体の設計はそれらの絶妙なバランスによって、サウンドが音楽的になるように構成されています。例えばアンプ回路はディスクリート回路であり、最終段はプッシュプルであるけれどもクロスオーバー歪みが出ないような回路的な工夫が凝らされています。これによってピュアーなサウンドが得られるということは、長年に渡る音を第一とする設計の経験から、Neve氏が得た知見によるものでしょう。

また、音響機器・オーディオ機器メーカの中でもオーディオトランス自体の設計を自分で行う開発者は稀有であり、そこにNeve氏のサウンドの秘訣があります。それは、Neve氏がトランスメーカー設計者としてそのキャリアをスタートしたことにより彼が得た「魔法」のようなもので、彼の設計になる製品は初期のNEVE社製品から現在まで、必ず自らの設計によるトランスが採用されています。そしてPorticoにもNeve氏の設計によるトランスが、入力段にも出力段にも搭載されています。しかしそれは、古いトランスの焼き直しではなく現代的なサウンドに合うように新たに設計されたもので、トランス周辺の回路にも工夫が凝らされ、トータルで音楽的に作用するように設計されています。
このように、Neve氏の技術の結晶たるアンプ回路・トランス・周辺回路とそれらのバランスで、Porticoのサウンドの土台はできています。Neve氏はそのサウンドを、「"depth and perspective"が重要」と表現します。そして"depth and perspective"は、一流のアナログ機材が持つ"sweetness"だとも。それにより音の余韻感を大切にすることや、録音環境がきちんと再生音に再現されることなども挙げておられます。そうしたことこそがPorticoをはじめとするアナログ機材の開発でNeve氏が大切にしている部分であり、Neve氏のサウンドの核とも言うべき部分なのです。
したがって単に周波数特性が似ているということだけではなく、その"sweetness"をデジタルフォーマットで実現することが我々K's Labの仕事で最も大切なことのひとつでした。アンプやトランスのモデリングを通して、Porticoの持つ"depth and perspective"を実現することに我々は力を注ぎました。当初、それまでのVCMエフェクト開発の中で作られたアンプやトランスのモデルを使って、Porticoのアンプ回路やトランス及び周辺回路をモデリングしてみましたが、なかなかPorticoの音は完全には表現できませんでした。それは、それぞれのモデルにそれぞれの機材のキャラクターが反映されており、Porticoのサウンドの方向性とは異なっていたからでした。そこで我々は、VCM技術によるたくさんのモデルやパーツと、新たに案出した技法を全てテーブルに広げ、ひとつひとつをコンサルタントと共に音質評価をして、Porticoの音を表現できるモデルを一から組み上げ直し、パラメーターを追い込んで行きました。試作・調整しては評価してまた試作する、という作業を繰り返した結果、作って捨てたパーツは30個以上になっていました。
そして最後にはNeve氏に100%納得していただける音を実現することができました。その完成度をオリジナルと比較しつつ、Neve氏は次のような文で評してくれました。
“The behavior and response are identical. The performance and the sonic signature are accurately captured.”