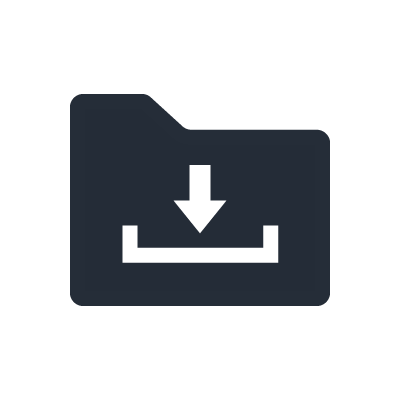開発ストーリー
Neoユーフォニアム・チューバ設計者
松隈 義彦 Yoshihiko Matsukuma

これまでウィーンフィルハーモニー管弦楽団のメンバーとウィーン式楽器の開発を手がけたほか、音響研究部門にも携わりサイレントブラスの開発者でもある。現在は金管楽器設計者として主にチューバやユーフォニアムの設計を担当している。
Neoを開発したきっかけを教えてください。
何人かの演奏家たちから偶然同じ時期に、当時のヤマハの金管楽器にもっと太くて柔らかく、なおかつ吹奏時に適度な抵抗感がある中で力をかけていった先に「音色」や「表現の魅力」が出せる楽器が欲しいとリクエストされたのがきっかけでした。開発にあたっては何度かイギリスにも行きましたが、まずは実際にどのような人がどのように演奏しているのかを確かめ、CDを聴くだけではわからない「音の振動」を肌で感じ、それを楽器の仕様にどう活かせばよいかを考えました。まず日本で試作品を作り、その後仕上げのため、評価をしてくれるアーティスト、試作品を改造できる技術者、それと道具やパーツの全てが揃っているドイツのヤマハ・アトリエ・ハンブルグに赴き、改良を繰り返し行いました。
イギリスではどのような発見がありましたか?

まずは一般の人の演奏レベルですね。彼らの演奏に対する思い入れがどこにあるのか、音色なのか音量なのか、それとも速いパッセージを吹くことなのか、どんなことを醍醐味に感じて演奏しているのか、たとえばチューバ奏者が下半分の音域を吹くことにプライドをかけているとか、イギリスで演奏している人の一般的な実状を見ることがきました。普段日本にやってくるアーティストは有名人ばかりですが、そういった人は腕前が良いのでどんな楽器であってもある程度吹けてしまい、逆に参考にならない面があります。たとえば、どの音をはずしやすいかを知らないと問題点を把握できないので、はずさずに吹ける人の音や意見だけを聞いていては役に立ちません。イギリスで実状を知ることができたのはたいへん意義深かったですね。日本のスクールバンドとは違い、イギリスのバンドは一団体に子どもからお年寄りまでいて、若い人たちは自分のバンドの年長者を見て育っているという環境・雰囲気があるのを、知識では知っていたものの、改めて実感できるのは大きいことでした。
開発のエピソードを聞かせてください。
楽器開発そのもので大きな役割を果たしてくれたのが、アトリエ・ハンブルグにいる技術者のトーマス・ルービッツとエディー・ファイト。彼らは技術的な考え方を共有できる仲間です。プレーヤーからの要求への対応をどのようにするか、例えば「音色上のメリットはあるが、音程でのデメリットがあるかもしれない」ということを技術者と設計者が同じレベルで話せるということは非常に重要なことです。また、YEP-642Sが完成したときに、ヨーロッパチャンピオンシップで優勝したスティーブン・ウォルシュ氏が「イギリスの伝統的なユーフォニアムの最高峰の楽器」という言い方をしてくれました。「伝統的」と認めてもらえたのは、こちらが望んでいた通りで嬉しかったですね。
楽器を設計する上でのこだわりはありますか?

Neoに関して言えば、音色と抵抗感のバランスですね。やろうと思えば、かなり強い抵抗感をもつ楽器を作ることは可能ですが、それをあるところで止めて音色自体が固くなりすぎないようにする、そのバランスです。
他にも全体の音域の吹奏感・抵抗感のバランスの良さ、音のつながり具合、そして音程の良さ。そういうのは昔の楽器にはなかったものが実現できていると思います。
楽器の設計は計算、それとも感覚?

最後は勘ですね。管の太さはある程度計算しますが、管の厚みは製造方法のために計算することはあっても、音のためにはあまり役にはたたない場合があります。例えば複数の楽器を試奏してもらうときにプレーヤーの音を聴き表情を見るのですが、最後に意見を聞いたとき、実際に出ていた音と本人が口で言うことにギャップがある場面があります。また、海外のプレーヤーの言葉をメールを通して現地のスタッフからもらい、その意味を勘違いすることもあります。それを避けるためにも、できることなら現地で音を聴いて、表情を見て、その音を聴いている周りの人の意見も聞きながら自分で考えています。 言葉だけを聞いていると絶対に誤解を招くものです。実際に言葉で発する単語に意味はなくて、仮にプレーヤーが他社の楽器を吹いて「こういう音がいいんだ」と言ったときにも、その音を自分の耳で聴ければ設計図のイメージが沸いてきます。それに対して板の厚みをどうしようかという勘が0.1mmの範囲で働くので、逆にそれを計算しろというのは無理ですね。
楽器の設計者に必要だと思うことはありますか?

「理屈」と「感性」の両方で分かることが必要だと考えているので、一方だけ詳しくなっても役にたたないと思っています。その両方が見えてくると先程の板の厚みの話にもなりますが、ある音色を聴くと頭の中でスペクトルが浮かび、部品を見てもレントゲンで撮ったように、透き通った楽器が想像できます。するとそれを改善するために「あと何ミリ変えましょう。」と言える。
「理屈」と「感性」の両方を常に橋渡しをしながら自分のものにしていき、どちらかに偏ることなく両方を取り込もうとすることを心がけたい。そうあるべきだと思っています。設計者はプレーヤーの音を聴いて設計図が頭に浮かばなければなりませんし、図面を見たらいい音が出るかどうか分からないといけない。感性でしか言えないことと、理屈でしか言えないことがリンクされた先に「目指すべき楽器がある」と信じています。