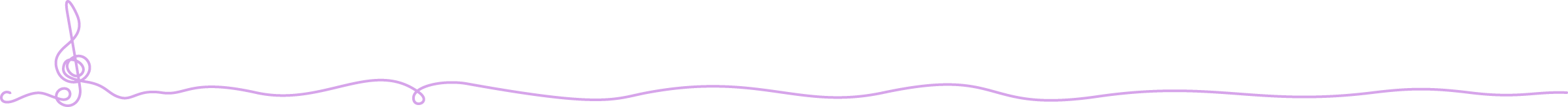音楽史について学ぶ
19世紀の音楽
古典主義からロマン主義へ
18世紀の最初の四半世紀時代におけるロマン主義音楽には、まだ多分に古典主義的な形式性が残されていたとはいえ、やはり、古典主義音楽とは違ったある種の味わいが感じられます。たとえばメンデルスゾーンの交響曲は、古典的なソナタ形式にしたがってまとめられてはいるものの、主題とその展開、オーケストラの響き、あるいはその色彩的な使いかたなどにより、楽しさに満ちた雰囲気が醸し出されており、これは古典派時代の音楽にはなかったものといえます。形式性はしっかり守られているものの、その形式性の中には、極めて個人的な情緒が盛り込まれており、それが聞く人の心に訴えかけてくるのです。

メンデルスゾーン
富裕な銀行家の子に生れ、幼時から正統的な音楽教育を受けて、17歳で早くも有名な《真夏の夜の夢》序曲を書き上げたメンデルスゾーン(F. Mendelssohn, 1809-47)の作品には、古典主義とロマン主義の混合した要素が強く示されています。古典主義とするには、その旋律や和声法にあまりにもロマン性が強く、ロマン主義とするには、音楽語法が定型的であり過ぎます。シューマンやショパン、あるいはベルリオーズ、リストといった人々のような自己主張的なロマンティシズムも認められません。それはもしかしたら、彼の育ちの良さからくる環境的なものに由来するのかもしれません。

シューベルト
その点では、シューベルト(F. Schubert, 1797-1828)にも同じことがいえます。《未完成》をはじめとする交響曲や多くの器楽曲、それに600曲にものぼるドイツ・リートなどに見る彼の音楽性は、豊かな抒情性に満ちてはいるものの、語法としては古典主義的な要素から、それほど抜け出ていません。ただ、絶妙な転調技法によって、音楽にそこはかとない情緒性を与えることにかけては、ずばぬけたうまさを見せています。
ドイツ・リートはシューベルトの歌曲において、初めて様式的な確立が行われたと考えられています。リートという言葉自体は古い時代から多声的な歌曲を意味するものとして使われてきたものですが、音楽史でリートという場合には、主として、シューベルトにはじまり、シューマン、ブラームス、ヴォルフ、マーラー、R.シュトラウスと受け継がれていく歌曲について使われることがほとんどです。モーツァルトやベートーヴェンの歌曲も、もちろんリートですが、シューベルト以後のそれとはややニュアンスの違ったものと考えられています。
歌曲そのものは、詩に音楽がつけられたものという点では、リートもリート以外も、形の上ではまったく同じといえます。では、リートをリート以外の歌曲と区別しているものは、何でしょうか? リートの特色は、詩と音楽が真に一体となることで、そこにまったく新しい世界が生み出されるところにあります。詩を読むことにより、作曲家の心の中には、一つのイメージが生まれます。そのイメージは、文学の世界から生じたものとはいえ、作曲家の心の世界にあるということでは、音楽の世界に属するものです。しかし、その音楽的イメージは詩の作者と共有するものであり、詩のもつ文学的内容もしくは文学的イメージが、音楽的内容もしくは音楽的イメージへと振り替えられたものだともいえます。つまり、それによって、詩の内容がさらに深められたということになります。
こうした態度で詩を扱い、それにピアノ伴奏をつけるという形で、リートができあがります。その際、当時のドイツ・ロマン主義の詩人たちによる詩に音楽づけをしたことで、詩を通して、その精神が音楽にも反映されていったのです。そこで、これまでには見られなかったような独自の世界が、ドイツ・リートによって作り上げられることとなりました。いってみれば、ドイツ・リートというのは、"詩によって語られたきわめて個人的な世界が、小さな宇宙としてまとめられた音楽"ということができます。
このリートの世界と同じようないきかたをしているのが、その頃、ピアノ作品で盛んに作られていた性格的小曲とよばれている小品です。シューベルトが創始したとされる《即興曲》や《楽興の時》、あるいはメンデルスゾーンが作りはじめた《無言歌》のような作品がそれにあたります。形式にあまりこだわらずに、きわめて個人的な情緒の世界をごく短い作品にまとめたこの形は、その後の作曲家にも広く利用され、それに標題音楽的ないきかたも加えられて、19世紀のピアノ音楽の中心的な曲種となっていったのです。
ドイツ・リートはシューベルトの歌曲において、初めて様式的な確立が行われたと考えられています。リートという言葉自体は古い時代から多声的な歌曲を意味するものとして使われてきたものですが、音楽史でリートという場合には、主として、シューベルトにはじまり、シューマン、ブラームス、ヴォルフ、マーラー、R.シュトラウスと受け継がれていく歌曲について使われることがほとんどです。モーツァルトやベートーヴェンの歌曲も、もちろんリートですが、シューベルト以後のそれとはややニュアンスの違ったものと考えられています。
歌曲そのものは、詩に音楽がつけられたものという点では、リートもリート以外も、形の上ではまったく同じといえます。では、リートをリート以外の歌曲と区別しているものは、何でしょうか? リートの特色は、詩と音楽が真に一体となることで、そこにまったく新しい世界が生み出されるところにあります。詩を読むことにより、作曲家の心の中には、一つのイメージが生まれます。そのイメージは、文学の世界から生じたものとはいえ、作曲家の心の世界にあるということでは、音楽の世界に属するものです。しかし、その音楽的イメージは詩の作者と共有するものであり、詩のもつ文学的内容もしくは文学的イメージが、音楽的内容もしくは音楽的イメージへと振り替えられたものだともいえます。つまり、それによって、詩の内容がさらに深められたということになります。
こうした態度で詩を扱い、それにピアノ伴奏をつけるという形で、リートができあがります。その際、当時のドイツ・ロマン主義の詩人たちによる詩に音楽づけをしたことで、詩を通して、その精神が音楽にも反映されていったのです。そこで、これまでには見られなかったような独自の世界が、ドイツ・リートによって作り上げられることとなりました。いってみれば、ドイツ・リートというのは、"詩によって語られたきわめて個人的な世界が、小さな宇宙としてまとめられた音楽"ということができます。
このリートの世界と同じようないきかたをしているのが、その頃、ピアノ作品で盛んに作られていた性格的小曲とよばれている小品です。シューベルトが創始したとされる《即興曲》や《楽興の時》、あるいはメンデルスゾーンが作りはじめた《無言歌》のような作品がそれにあたります。形式にあまりこだわらずに、きわめて個人的な情緒の世界をごく短い作品にまとめたこの形は、その後の作曲家にも広く利用され、それに標題音楽的ないきかたも加えられて、19世紀のピアノ音楽の中心的な曲種となっていったのです。