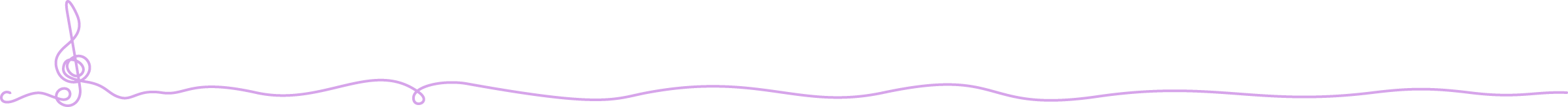音楽史について学ぶ
19世紀の音楽
その後の歌劇界
歌劇の国イタリアでは、19世紀前半のロッシーニらの活躍のあとを継ぐようにして、ヴェルディ(G. Verdi, 1813-1901)が現れます。ヴェルディは、ドイツで楽劇を創始したワーグナーと同じ1813年の生まれです。ワーグナーが歌劇作曲家として名声をあげ、1845年に《タンホイザー》を上演したのと相前後して、ヴェルディは1851年に《リゴレット》を発表し、歌劇作曲家としての名声を確立していきます。この2人の作曲家は、その後も、一方は伝統的なイタリア歌劇の世界を代表し、他方はドイツ歌劇、特に楽劇という新しいジャンルにおいて、それぞれの道をほぼ並行して歩んでいくことになります。

ヴェルディ
ヴェルディはその長い生涯を通じて歌劇を一貫して書き続けました。イタリア歌劇の伝統となっている旋律中心主義的ないきかたを守りながらも、声楽の扱いに工夫を見せ、旋律の美しさやオーケストラの効果的な使用などにより、歌劇にいっそうの劇的迫力を与えることに成功しています。ヴェルディの歌劇作品にはなによりもまず、見る楽しさ、聴く楽しさが盛り込まれており、その点ではあくまでもイタリア歌劇の伝統を守っているといえます。
このヴェルディの後半生の活動と平行するようにして、イタリアにはヴェリズモ(現実派歌劇)とよばれる新しい傾向が生れてきます。ヴェリズモとは、現実生活に材をとった歌劇のことです。現実から遊離しがちなロマン主義への、いわば反動として生じてきたものといえます。代表的な作品には、マスカーニ(P. Mascagni, 1863-1945)の《カヴァレリア・ルスティカーナ》やレオンカヴァロ(R. Leoncavallo, 1858-1919)の《道化師》などがあり、いずれも男女の三角関係をテーマとして、最後は殺人で幕切れになるという生々しさが特徴でした。この後に出るプッチーニ(G. Puccini, 1858-1924)も同じ傾向を見せ、《ボエーム》《トスカ》《蝶々夫人》など、同時代的な現実生活に材をとった数々の名作を発表しました。プッチーニの歌劇の特色は、登場人物の描写やその情緒表現に巧みだったことで、それは前記の作品中の主人公であるミミやトスカ、あるいは蝶々夫人の舞台を見ればよくわかります。
この時期、フランスでは抒情歌劇とよばれるメロドラマふうの作品が盛んに作られていました。おもな作品には、トマ(C. L. A. Thomas, 1811-96)の《ミニヨン》、グノー(C. Gounod, 1818-93)の《ファウスト》、サン=サーンス(C. Saint-saens, 1835-1921)の《サムソンとデリラ》などがあります。そうしたなかで、ビゼー(G. Bizet, 1838-75)の書いた《カルメン》はずばぬけた面白さで、今なお歌劇場のレパートリーとして、常に上位を占め続けています。
このヴェルディの後半生の活動と平行するようにして、イタリアにはヴェリズモ(現実派歌劇)とよばれる新しい傾向が生れてきます。ヴェリズモとは、現実生活に材をとった歌劇のことです。現実から遊離しがちなロマン主義への、いわば反動として生じてきたものといえます。代表的な作品には、マスカーニ(P. Mascagni, 1863-1945)の《カヴァレリア・ルスティカーナ》やレオンカヴァロ(R. Leoncavallo, 1858-1919)の《道化師》などがあり、いずれも男女の三角関係をテーマとして、最後は殺人で幕切れになるという生々しさが特徴でした。この後に出るプッチーニ(G. Puccini, 1858-1924)も同じ傾向を見せ、《ボエーム》《トスカ》《蝶々夫人》など、同時代的な現実生活に材をとった数々の名作を発表しました。プッチーニの歌劇の特色は、登場人物の描写やその情緒表現に巧みだったことで、それは前記の作品中の主人公であるミミやトスカ、あるいは蝶々夫人の舞台を見ればよくわかります。
この時期、フランスでは抒情歌劇とよばれるメロドラマふうの作品が盛んに作られていました。おもな作品には、トマ(C. L. A. Thomas, 1811-96)の《ミニヨン》、グノー(C. Gounod, 1818-93)の《ファウスト》、サン=サーンス(C. Saint-saens, 1835-1921)の《サムソンとデリラ》などがあります。そうしたなかで、ビゼー(G. Bizet, 1838-75)の書いた《カルメン》はずばぬけた面白さで、今なお歌劇場のレパートリーとして、常に上位を占め続けています。

ワーグナー
ドイツでは既に触れたように、ワーグナー(R. Wagner, 1813-83)が登場します。彼の初期の作品は歌劇と題されていましたが、1859年に書いた《トリスタンとイゾルデ》から楽劇と称されるようになりました。楽劇とは、要するに総合芸術という意味です。台本となる文学、それにつけられる音楽、舞台装置などの美術、登場人物の演技など、そのすべてが総合されて、ひとつの芸術作品へと結集していくのが楽劇でした。そのために、ワーグナーはみずから台本を作成し、作曲をし、演出から指揮に至るまですべてを1人で行い、最終的には楽劇を上演するにふさわしい劇場として、バイロイト祝祭劇場を建設するに至ります。
ワーグナーはこの楽劇を書いていく上で、さまざまな工夫をみせています。その1つに、楽劇としての劇的進行を円滑にするためのライトモティーフの使用があります。また、従来の歌劇のようにアリアや重唱ごとに音楽に切れ目が生じるのを避けて、無限旋律といわれる途切れることのない旋律作法を導入しました。この無限旋律のために、必然的に主和音に終止する機能和声の方法は避けられることになり、そこに半音階法的な調性のあいまいさが生じて、近代音楽の発生にきわめて重要な影響を与えることになります。
19世紀、ことにその後半において、もう1つ歌劇界で特筆すべきことは、オペレッタの作品が盛んに作られたことです。パリでは、オッフェンバック(J. Offenbach, 1819-80)が出て《天国と地獄》を書き、ウィーンでは、ワルツ王として有名なヨハン・シュトラウス(子)(J. Strauss, 1825-99)が《こうもり》《ジプシー男爵》を書いて人気を集めました。また、ロンドンにはサリヴァン(A. S. Sullivan, 1842-1900)が出て、《ミカド》そのほかの作品を書いています。
ワーグナーはこの楽劇を書いていく上で、さまざまな工夫をみせています。その1つに、楽劇としての劇的進行を円滑にするためのライトモティーフの使用があります。また、従来の歌劇のようにアリアや重唱ごとに音楽に切れ目が生じるのを避けて、無限旋律といわれる途切れることのない旋律作法を導入しました。この無限旋律のために、必然的に主和音に終止する機能和声の方法は避けられることになり、そこに半音階法的な調性のあいまいさが生じて、近代音楽の発生にきわめて重要な影響を与えることになります。
19世紀、ことにその後半において、もう1つ歌劇界で特筆すべきことは、オペレッタの作品が盛んに作られたことです。パリでは、オッフェンバック(J. Offenbach, 1819-80)が出て《天国と地獄》を書き、ウィーンでは、ワルツ王として有名なヨハン・シュトラウス(子)(J. Strauss, 1825-99)が《こうもり》《ジプシー男爵》を書いて人気を集めました。また、ロンドンにはサリヴァン(A. S. Sullivan, 1842-1900)が出て、《ミカド》そのほかの作品を書いています。