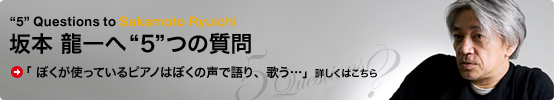この記事は2009年4月13日に掲載しております。
この記事は2009年4月13日に掲載しております。
子供時代のピアノとの思い出からNYの生活まで、「今」の坂本氏をひも解いていきます。


- pianist
坂本 龍一 - 音楽家。1952年生まれ。78年『千のナイフ』でデビュー、同年YMOに参加。
YMO散開後、数々の映画音楽を手がけ、作曲家としてアカデミー賞を受賞するなど世界的な評価を得ながら常に革新的なサウンドを追求している。1999年制作のオペラ「LIFE」以降、環境・平和・社会問題に言及することも多く、9・11同時多発テロをきっかけに、論考集「非戦」を監修。自然エネルギー利用促進を提唱するアーティスト団体「artists’ power」を創始した。2006年六ヶ所村核燃料再処理施設稼働反対を表明し「stop-rokkasho.org」を開始、2007年7月には有限責任中間法人「moreTrees」の設立を発表し、温暖化防止についての啓蒙や植樹活動を行うなど活動は多岐にわたっている。また、06年新たな音楽コミュニティの創出を目指し「commmons」を設立。1990年より米国、ニューヨーク州在住。
「坂本 龍一」オフィシャルウェブサイト
※上記は2009年4月13日に掲載した情報です。
ぼくの使っているピアノは、ぼくの声で語り、歌う。これがピアノのすばらしいところ。

「人間はいかにかよわいものか、ぼくたち人類が住む地球-生物が生きることができる環境が存在している地球は、なんと珍しい惑星なのだろうか。膨大な氷と水が作り出す想像を絶するその質感に圧倒され、さまざまなことを考えさせられ、大きな衝撃を受けました」
坂本龍一が、前作から約5年ぶりに新譜「out of noise」をリリースした。これは内外のさまざまなジャンルのミュージシャンと共演した意欲作で、多彩な「音」「響き」が登場する。とりわけ印象的なのが、北極圏で採集した「氷の音」が用いられていること。曲名もストレートに「ice」。これはゴムボートで氷山に接近し、海中に水中マイクを垂らして録音したものである。
彼が大きな衝撃を受けたという北極圏への旅は、イギリス人アーティストが10年前に始めた地球温暖化の最前線である北極圏を体験するというプロジェクトで、科学者やアーティストが参加するもの。新譜の制作中に声をかけられ、アルバム制作をいったん中断して旅に出た。そのときはこの旅が直接アルバムに影響を与えるとは思わなかったが、帰国後あまりの衝撃の大きさに、拾ってきた膨大な音を置いていく作業に時間を費やすようになった。

「旅に関しては、何かを発表するとか発信するという義務はなく、個人の自由裁量に任されています。ですから事前に準備することなく、水中マイクとポケットに入る小さな鈴だけを持って行きました。その場に行って、全身全霊で音を聴き、空気を感じ、見たものから自分が何を感じるかを大切にしたかったからです。すごい寒さのなかでオーロラを見、イヌイットの暮らす家を訪ね、7分の1しか表面に出ていないのにものすごい重量感を感じさせる氷山に囲まれ、その色のないモノトーンの世界で自分の内面とひたすら向き合う大切さを学びました」
坂本龍一はアフリカが大好きだという。赤道直下のきびしい環境。しかし、そこに暮らす人々は生命感あふれ、過酷な環境を生き抜く力を備えている。北極圏とはまったく相反するきびしさのなかでたくましく生きている。
「両極端の宇宙的なものがむきだしになっている世界を見ることで、ぼくのなかに多くの衝撃と感動が蓄積されてきました。今回北極圏で拾ってきた音は、どういう音楽になるのかといろんな組み合わせを考慮し、まさにひとつひとつ音を置いていった感じ。たとえば、このシャツにはこのジャケットが合うだろうか、いやこっちのシャツのほうが似合うだろうと洋服を選ぶときのような感覚ですね」
「out of noise」は写真やエッセイ、曲に関する詳細な文章が掲載されたフルアートワークCDと、シンプルなパッケージレスCDの2種が用意され、個人の好みに合わせて買うことができるという新しい試みが施されている。

そんな坂本龍一がピアノの音に惹かれたのは、ピアノ好きの叔父の影響が大きい。自宅にはピアノがなく、その叔父の家にいってはピアノを弾き、膨大なコレクションのレコードを聴き、音楽に浸った。
「ぼくはピアノの“響き”が好きなんです。録音された音や機械から出てくる音ではなく、ナマの音の響き。ホールに響き渡る音にもっとも関心があります。当時からJ.S.バッハの音楽が好きでした。さまざまな音楽を聴いていましたが、ほとんどの鍵盤作品は右手がメロディを担当し、左手は伴奏を担う。ぼくはサウスポーのため、そういう曲を聴くと左手がおろそかにされている感じを受け、納得がいかない(笑)。でも、バッハの作品は両手が対等に扱われ、主従の関係は成り立たない。そこが大いに気に入りました」
彼は、バッハ好きが高じてグレン・グールドを愛するようになる。いまでもグールドのバッハは特別な存在だ。さらにモーツァルトやベートーヴェン、ショパン、シューマン、ブラームス、ベルクなどを好むようになるが、不思議なことにシューベルトだけは「まったくわからない」と語る。ピアノ・ソナタも即興曲もダメ。唯一、歌曲だけは聴いている。
「シューベルトは肌に合わないという感じ。ぼくはミュージカルもオペラも芝居も苦手なんですよ。舞台芸術というのが性に合わないんですね。自分でオペラを作っているにもかかわらず。ニューヨークに住んでいるから、いろんなエンタテインメントがあっていいですねとよくいわれるけど、まったく見にいかないですね。ぼくは完全な引きこもり。意外ですか。自宅からまったく出ないんで、たまに町に出ると新しい店ができたりして景色が変わっている。季節も変わったりして(笑)。引きこもりながらいろんなことを考えているわけです。無にはなれないですね」

将来は緑の多い静かな田舎に住みたいと願っているが、いまはニューヨークという大都会のなかでまったくひとりになれるため、その状態が気に入っている。
「ドア一枚で外界と完全に遮断されるわけ。こういうアーティストは結構あの町には多く、同じ感覚をもった人と会ってたまに情報交換するとすこぶる新鮮でね(笑)。ニューヨークって、プライヴァシーが守れるところなんですよ。逆に東京は忙しすぎて、ぼくは自分を見失いがちになる。住みたくないですねえ」
叔父から影響を受け、彼は子どものころからピアノを習うようになるが、エチュードが嫌いで練習嫌いになってしまう。高校生になったとき、ずっと個人レッスンをズル休みしていたら、先生から電話がかかってきて「あなたは、もう来週からレッスンに来なくていいから」と破門になってしまった。
「ヤッターっていう感じでした。もう練習しなくていいんだって、うれしくてね。でも、中学2年のときにレコードでブダペスト弦楽四重奏団の演奏するドビュッシーとラヴェルの作品を聴いて、これまでまったく聴いたことのない音楽に出合って深い感銘を受け、すぐさま楽譜を買ってきてピアノで弾いたりしていたんです。好きな音楽を弾くのだけは大好きで、何時間でもピアノに向かっていました。小学生時代からベートーヴェンの第九をピアノで弾いていましたから。その意味で、ソルフェージュは大切なんですよ。子どものころからソルフェージュを学んでいると、演奏だけでなく、作曲するときにも役に立つ。ピアノの先生は、できる限り早い時期に子どもたちにソルフェージュを教えるべきですね」
学生時代には、彼自身も生徒をもってレッスンをしていたことがある。
「練習嫌いにならないように、音楽嫌いにならないように、好きな音楽を弾いていいよというレッスンをしていました。ロックを弾く子にはこのほうが自然な指遣いになるんじゃない、フレーズがこのほうがつながるよ、などといっていましたが、なにしろこの先生がズル休みの名手なんで、次第に生徒がいなくなってそのうちだれも来なくなった(爆笑)」
趣味は読書や映画を見ること。最近は、バッハ以前の時代の音楽を聴くことにたまらない魅力を感じている。 「古楽のジャンルを聴くのが非常に新鮮。頭のなかが切り替わる感じ。古楽器の響きがまたいいんですよ。ぼくが子どものころにはこういう音楽の録音などはほとんどありませんでしたからね。やはり、ひとつひとつの音の響きに魅せられます。もっともっといろんな響きを聴きたくなりますし。また、古楽を聴いて部屋に引きこもろうかな‥‥」
Textby 伊熊よし子

※上記は2009年4月13日に掲載した情報です。