
 この記事は2009年12月14日に掲載しております。
この記事は2009年12月14日に掲載しております。
私はタダでお洒落をする名人なんですよ、と笑顔で語るハイドシェック氏。フランスの伊達男にふさわしいダンディズムを漂わせながら、日本の温泉が大好き!とインタビュー当日も終始スタッフを笑わせつつ、独自の音楽に対する美学を熱心に語って下さいました。


- pianist
エリック・ハイドシェック - 1936年フランス北部の古都ランスを代表するシャンパン王シャルル・エドシック家に生まれる。
名ピアニスト・名教師として名高いコルトーに才能を見出され、6歳より本格的な勉強をはじめ、8歳でエコール・ノルマルに入学。1952年パリ国立音楽院に進学し、54年に首席で卒業。
1955年パリ・シャンゼリゼ劇場でのリサイタルでピアニストとしての地位を確立。その後、ケンプやルービンシュタインに認められ世界的な名声を得る。コルトーには、その死の年(62年)まで指導を受け続け、その直伝の個性を優先する演奏法は、現在も彼の中で脈々と息づいている。個性喪失的傾向に傾いている時代風潮の中で極めて貴重な存在であり、各地に熱心な支持者を持っている。
これまでに100枚以上の録音を残しており、日本では特に愛媛県宇和島でのライヴ録音が大ベストセラーとなる。06年廃盤となっていな宇和島ライヴ録音が再発売され、再びベストセラーを記録。
08年、初来日より40周年を記念して行われたサントリーホールでのリサイタルは大盛況となった。
「Eric Heidsieck」Official Website(仏語)
※上記は2009年12月14日に掲載した情報です
演奏はタピストリーを織るようなもの。ひとつひとつ細やかに感情を込めて織り込んでいくのです。

フランスの古都、シャンパンの産地として有名なランス出身のハイドシェックは、粋で洒脱で色彩感に富むピアノを奏でることで知られる。1960年代にはフランス音楽界きっての個性派として輝かしい演奏を聴かせたが、その後しばらく沈黙の時代を迎え、80年代に再びエネルギッシュな音楽を聴かせるようになった。
現在は、ソロ、夫人との2台ピアノの演奏、オーケストラとの共演、作曲、教育、ロン=ティボー国際コンクールの審査員など、幅広い分野で活躍。来日も多く、日本のファンも非常に多い。さらに弟子入りを希望する人があとを絶たず、マスタークラスなどもいつも満員だ。
「教育というのはとても大切な分野です。特に子どもにとっては。私も子どものころからすばらしい先生に出会い、音楽が大好きになるような教育を受けてきました。練習も苦痛ではありませんでしたし、ピアノに向かうことに大いなる喜びを抱いていました。
いま、私のところに日本の先生たちが多く勉強にやってきますが、彼女たちが日本に戻って次に生徒たちに接したとき、あっ、先生変わったな、と思ってもらえたら最高です。それは単に技術的に向上するという意味ではなく、その先生の音楽に対する態度が変わったと感じてもらえればうれしいのです。
私の経験からいうと、いい教えを受けた人はいい音楽を奏でるようになるからです。もちろん、短期間のマスタークラスを受けたからといって、すぐに上達するわけではありません。要は、気持ちの問題です。音楽に心を捧げる、その思いが強くなるという意味です」

ハイドシェックは80年代にリヨン音楽院で教鞭を執っていた。そのときにも、生徒たちにテクニック上のことのみならず、自身のモットーである「音楽を愛すること」をさまざまな方法で伝えた。
「しばらく沈黙の時代があったといわれていますが、その間もずっと勉強は続けていたんですよ。教えることも多く行っていましたし、作曲もしていました。そして80年代に入って、モーツァルトのピアノ協奏曲の全曲演奏に取り組みました。カデンツァ(終止の前に挿入される奏者の自由に任された部分)の作曲に魅せられていましたので、これに長い時間をかけていたのです。
その後、ベートーヴェンのピアノ・ソナタの全曲演奏に全力を傾けました。私はひとつのことに熱中するタイプで、ある作曲家の作品に取り組むと、とことんそれを追求したくなり、どこまでも突き進む癖がある。ですから、何がなんでも全曲演奏をしなくては、と考えてしまうのです。なぜなら、モーツァルトもベートーヴェンも、その作品を1曲弾いただけでは見えてこないことも、全曲通して弾くことにより明確に見えてくるわけです。作曲家の人間性の多様性が浮き彫りになりますし、より作曲家に近づくことができる。こんなすばらしいこと、やめられますか。途中でやめられるわけがありませんよ(笑)」

ハイドシェックの実家はシャンパン王として知られる名門。ただし、彼自身は気取りも気負いもなく、きさくなキャラクターと自然体の演奏を特徴としている。
「確かに恵まれた子ども時代を過ごしましたが、私の時代は戦争があった。その苦難や苦悩はいまでも忘れません。明るく見える曲でも、楽譜の奥に秘められた影の部分を読み取るようになったのは、この体験がものをいっています。
私自身は元来楽天的な性格ですが、人間の影の部分を必ず見ますね。作品に関してもそうです。想像力を最大限働かせて作曲家の意図するところ、真の意図を探し出すわけです。それを聴いてくれる人たちに届けるのが、ピアニストとしての私の使命だと思っていますから」
ハイドシェックは、「演奏はタピストリーを織るようなもの」と語る。ひとつひとつこまやかに感情を込めて織り込んでいく。そして いま、そのタピストリーを織る先に見えているのがJ.S.バッハの「平均律クラヴィーア曲集」。昔からグレン・グールド、エドヴィン・フィッシャーの録音を聴き続けてきたが、いまようやく自分の「平均律」を演奏したいと願うようになった。
「もちろん家では長年演奏していますよ。でも、いまはステージで演奏したい。《イタリア協奏曲》も《パルティータ》も弾きたいと思っています。バッハは学生のころ、拍をしっかり刻んで規則正しく弾くように弾いていましたが、実はそれはとんでもないまちがいだと気づいた。当時は筋肉を鍛えるために練習しているようなところもありました。

バッハは拍を意識せずに、波が打ち寄せたり引いたりするように動きを持って演奏しなければならない。潮の満ち引きと同じです。月の満ち欠けに従い、潮は規則正しく満ち引きが行われますが、そのなかで波は一定ではなく自然でなめらかで自由です。フレーズを大きくとらえ、波のように少し浮いたような感じで自由に演奏する。自然な息遣いで、呼吸するように弾くことが大切。それに気づいたとき、私のなかでバッハがより大きな存在を占めてきたわけです。いまバッハを弾かずしていつ弾く、という感じ。ほら、もう指の先までバッハがきているのが見えるのです(笑)」

パリの自宅ではヤマハのピアノで練習しているのだが、実はこのピアノ、購入時にちょっと変わったエピソードがある。というのは、1997年の日本ツアーの折、仙台で練習するピアノがなく、ヤマハの店頭に置いてあるピアノを貸してもらった。短時間のつもりが、熱中する性格ゆえ店頭で演奏に没頭してしまい、我を忘れて20分以上弾き続けた。それほどこのピアノが手に合っていたのである。
「そのときは息子が一緒でしたので、私はこんなピアノを探していたんだよ、と彼に伝えたところ、息子はすぐにお店の人と交渉。そのピアノを購入することができるようになったんです。しかも、展示品だから安くするといわれた。でも、その後3カ月かかって船でパリに輸送され、たまたま自宅の前の家が工事中で、クレーンで私の家まで吊り上げて運んだため輸送代がものすごく高くなってしまった。結局、安いんだか、高いんだか(笑)。でも、このピアノは12年間弾いているけど、とても弾きやすい。私のバッハはこのピアノから生まれるんですよ」
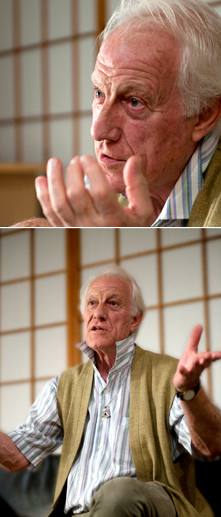
ハイドシェックには何度もインタビューをする機会があるが、いつも彼は全身を使って自身の考えを表現。手を大きく広げたり、立ち上がったり、歌を歌い出したり、「紙と書くものを貸してくれ」といって音符や絵を書き出したり。顔の表情もすこぶる豊か。俳優のように表情を幾重にも変えながら、早口で大きな声で話す。そしてジョークを連発。その話の流れは、あたかもハイドシェックの演奏そのものを連想させる。
ピアノに向かい、作曲家の魂に寄り添うよう楽譜に忠実に、真摯な思いで演奏するが、その音楽からはひとつのストーリーが描き出される。ウイットとユーモアが見え隠れし、情感豊かな音楽が紡ぎ出される。彼がタピストリーを織るという表現をしたことが思い出され、そのこまやかな表現と繊細さ、優雅さの裏に息づく作曲家が意図したドラマチックな物語に心を奪われていく。
「私はフランスで生まれましたが、ドイツの血をひいています。ですからドイツ系の作曲家や作品への理解が自然にできるのです。もちろん音楽には国や民族は関係ありませんが、私は子どものころからドイツ的な物の考えかたをする人間でした。5歳から20歳までコルトーの助手を務めていたパスクール・ド・ゲラルディに師事しましたが、彼女は大のベートーヴェン好きで、ベートーヴェンに関しては何でも知っているような人でした。
私は8歳のときにベートーヴェンのピアノ・ソナタ第1番を持っていったのですが、そのときに彼女はとても熱心に演奏を聴いてくれました。そして終わると、こういったのです。まあ、この子はベートーヴェン弾きね、って。でも、当時の私はベートーヴェン弾きというのが何を意味するのかわからず、それ、何のこと? って聞いたんですよ(笑)。それ以来、私はベートーヴェンを愛し、ずっと弾き続けているというわけです」

その後、ヴィルヘルム・ケンプからもベートーヴェンをはじめとするドイツ・オーストリアの古典派の作品を学んだ。
「ケンプはとても明るい人でした。ベートーヴェンの作品を教えてくれるときも、各々の作品に光を見出していた。作品のなかに潜む光に惹かれていたんです。いつもそれを追求し、私にも探究するようにいいました」
アルフレッド・コルトーはケンプとは異なり、影を愛し、暗いものが好きだった。
「ケンプとコルトーは性格的にまったく逆でした。私はいつもこう思ったものです。コルトーはそういう性格ゆえ、フランス作品に宿る、色彩感あふれる輝かしい響きに魅せられたのではないかと。影を愛しているがゆえに、まばゆさに惹かれたのではないかと思っていました」

そんなハイドシェックは、いつも獅子座に因んでライオンのネックレスをしている。これがエネルギーの基なのだろうか。
「昔、妻がイスラエルで買ってきてくれたものなのですが、太ったためかはずせなくなってしまった。私は日本の温泉が大好きなんですが、温泉にもはずさないで入るため、変色してしまったんですよ。えっ、お守りかって。いやいや、ネクタイ代わりですよ」
以前、そのネックレスの下に藍染の綿のスカーフをしていてとても粋だったため、「そのスカーフ素敵ですね。フランス製ですか」と聞いたところ、「何いってんだよ、きみ。これは日本製だよ。祇園の温泉でもらった手ぬぐいさ。そう、そんなに似合っている? 私はタダでおしゃれをする名人なんだ」との答えに、その場に居合わせた全員が大爆笑。
個性的な演奏と個性的なキャラクター。リサイタルにはいつも熱心なファンが大勢詰めかける。彼は音楽の喜びを与えてくれるからだ。次なるバッハにも期待したい。
Textby 伊熊よし子

<取材協力:東京日仏学院>
※上記は2009年12月14日に掲載した情報です





