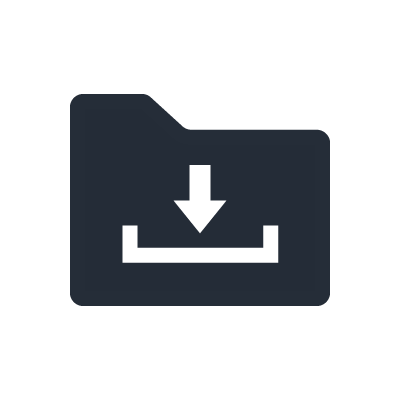マチュー・デュフォー氏 イデアルに出会う!
ヤマハフルート[アルティザンとアーティスト交流の軌跡]
米国でヤマハはチャレンジャーの立場。 「自分たちの楽器を見てもらいたい」 という気持ちが常にあった。
──デュフォーさんにとってヤマハの田中さんは、フルート・テクニシャンとして今では欠かせない存在になっています。そもそもお二人はどのようにして出会われたのか。まずはそこから聞かせてください。
デュフォー 私がシカゴ響にいたとき、グランドラピッズ(ミシガン州)のヤマハに勤務していた彼とシカゴで会ったのが最初でした。あれは2005年か6年? 大昔のことで忘れてしまった(笑)。
田中 2006年です。同僚がヤマハを使っているシカゴ響のトランペット奏者に会いに行くというので私もついて行き、そこで前からお会いしてみたいと思っていたデュフォーさんに名刺を渡して挨拶することが出来たんですね。
ご承知のように、特にアメリカではボストンのフルートメーカー数社の存在が大きく、我々ヤマハはチャレンジャーという立場です。「自分たちの楽器を見てもらいたい」という気持ちが常にありましたから、デュフォーさんにもぜひ吹いてみてもらいたいと打診したら、即快諾をいただいた。グランドラピッズからシカゴまでは車で4時間ほどの距離です。
デュフォー ケイスケは人柄が明るく、押しつけがましくなかった。すぐにシカゴのオーケストラホールや私のアパートに来てもらい、様々なモデルを試しました。ヤマハを吹くのは学生時代以来のことだったけれど、私は常に新しい楽器を試し続けています。それであるとき、素晴らしいゴールドフルートに出会い……あれはいつだった?
田中 ハンドメイドモデルの「イデアル」が形を現し始めた時期の2008年ですね。その楽器をとても気に入っていただき、そこからデュフォーさんの細かな希望に沿って楽器を調整して行く作業が始まりました。デュフォーさんはゴールドフルートを吹いていらしたけれど、「音自体はシルバーの方が好きだ」とおっしゃったのを覚えています。嬉しかったのは「シカゴには良いテクニシャンがいない。こっちに住まないか?」と言っていただいたこと。
デュフォー でも実現しなかった。
田中 その後、日本の本社に帰国することになり、アメリカのスタッフにデュフォーさんのケアを引き継ぎました。と言っても、ヤマハはチームで動いていますから、日本の我々とデュフォーさんのリレーションシップは続きながら今日に至っているわけです。


「自分の音色に恋をしてしまった」
──シカゴ響でイデアルを試したとき、最初にどんな感想を持ちましたか?
デュフォー メカニックがとても安定していること。非常に信頼できる楽器だと思いました。また、響きは柔軟で音色に幅がある。一番注目したのは音程の良さです。音域による音程のバラツキがほとんどない。楽に他の楽器に合わせられます。
その後、私の希望を入れた細かな調整を経て楽器がほぼ完成形に近くなったとき、シンフォニーホールで吹いた時の印象はよく覚えていますよ。音色に恋をしてしまうくらい自分の音に惚れ込んでしまったのです。以来、その印象はずっと変わりません。
田中 そうしたデュフォーさんのコメントやら評価は、逐一日本に入って来ていましたから、まさに「やったぁ!」という気分でしたね。
というのも、イデアルは今までのヤマハフルートには無かったモデルなんです。アンドラーシュ・アドリアンさんと一緒に開発しましたが、アドリアンさんだけでなく、タイプの異なる様々なフルーティストにも選択してもらえるよう、楽器のキャパシティを大きく拡げることが開発の最大のコンセプトでした。ですから、発売に前後して早々とデュフォーさんから高い評価をいただいたことは、私たちには非常に心強く、励みになったのです。
デュフォー 第一印象からこれほど自分に合っていると思った楽器は他にありません。たいてい、良いと思っても必ずどこかに不満があるものです。
田中 それまでアメリカで私は、「ヤマハは2番吹きにはいいが、1番吹きにはちょっと」というフルーティストたちの声をしばしば耳にしていました。万人が吹いてフルートらしいサウンドが出る楽器を作ろうと思うと、どうしても平均的な楽器にならざるを得なくなる。そうした限界を一気に拡げたいという思いが私たちにはあり、息をさらに入りやすくしたり、ある程度の抵抗感を持たせるために楽器をヘビーにしたりと、アドリアンさんらと文字どおり丁々発止のやりとりを交わしながら、イデアルのスペックを決めていったという歴史があります。
──デュフォーさんは以前、本誌のインタビュー(383号・2013年7月号)で、ヤマハの「中庸」の良さを語っておられます。
デュフォー 「中庸」というと、以前はネガティブな意味になり、「キャラクターが不足する」ことを意味しました。しかし今では製作技術が飛躍的に発展し、個性を持った楽器でも、演奏家の影が薄くならないような楽器を作ることが出来るようになった。どんな人が吹いても自分自身の音を見つけることができる、そんな楽器が私にとって本当の意味での「中庸」な楽器であり、真に優れた楽器です。
田中 狭い中庸ではなく、吹き手のイマジネーションをどの方向にも拡げられるという大きな中庸ですね。
デュフォー 吹く人が好きか嫌いかにお構いなく、一つの色や音を強要するような楽器もあります。そんな楽器では音のテクスチャーを変えるのは難しい。音色は楽器がつくり出すものではなく、自分の頭がつくり出すもの。それに効率よく柔軟に反応してくれるのが、良い楽器なのです。
銀のオフセットモデルのイデアルを提案され……
──14金のイデアルを使っていらっしゃいますが、先日の東京と大阪のリサイタル(7月27日ヤマハホール/29日大阪・阿倍野区民センター)では、銀のイデアルを使われたとか。

デュフォー 材質に全くこだわりはありません。自分の楽器にちょっとした不具合が生じ、代わりとしてケイスケが提案してくれた銀のイデアルがたまたま良かったから使ったまで。明るく柔軟に、とても良く響く楽器でしたから。
多くの人がゴールドフルートに魅力を感じるのは、それが「金」だからじゃないのかな。高価でゴージャス、というメンタルな部分が大きいのでは。銀のフルートで始めれば、いつかは金のフルートを吹いてみたいと夢見ます。それが現実になったとき、楽器が良いか悪いかよりも光り輝く材質に目を奪われてしまう。銀のネックレスより、金のネックレスの方がよく見えるのと同じ。もちろん両者の音質には違いがあり、ゴールドフルートの方が密度の高い重量感のある音が出るのに対し、シルバーフルートは、より明るく柔らかい音が出るとは言えます。
田中 例えばデュフォーさんが、「もう少し立体的なサウンドが欲しい」と思ったようなとき、デュフォーさんには材質がどうというアイデアはないわけですね。それを考えるのがこちらの役目。「だったらシルバーも一度試してみたらいかがですか」と。そこから私たちは、また新たな知見を得ることが出来るわけです。そうしたいろんな選択肢を提供できる阿吽の呼吸のようなものは、やはりアーティストとの長年のリレーションシップの中で培われるものだと思います。
──リサイタルで使われた銀のイデアルは、オフセット仕様だったそうですね。
デュフォー 生まれて初めてオフセットのフルートを吹きました。これもケイスケの提案でした。
それまで、35年以上のフルート生活で私が手にして来た楽器は、すべてインラインの楽器です。しかし正直に言うと、左手のポジションにいつも何かしら違和感を感じていたことは否めない。人それぞれに手の形や大きさは違いますが、私の場合、てのひらは大きい割りに指は長くありません。インラインだと手をやや曲げて構えないといけない。それが手に微妙な緊張を生みます。左手人差し指のキーにコルクを貼ることを勧めてくれたのもケイスケでした。
田中 デュフォーさんのためにカスタマイズすると言っても、出来ることと出来ないことがあります。キーを伸ばすことは出来ませんので、コルクを提案させていただいた。
開演5分前のトラブル
──テクニシャンからご覧になったデュフォーさんは、どんなタイプのお客さんですか
田中 要求をイメージではなく、具体的にクリアな表現でおっしゃる方ですね。ただしそのレベルがとてつもなく高いので、解決するのはいつも容易ではないのですが。
デュフォー 自分でも些細なことにこだわり、細かなことを言う人間だと思う。しかし、良くも悪くも、いつも本当に微妙な世界に於ける話なんです。仮に、あるキーからほんのわずかの漏れがあれば、途端に表現に不自由を感じてしまう。私は技術者ではないから、その原因がどこにあるのかは判りません。
昨日(大阪でのリサイタル)のリサイタルの直前にもこんなことがありました。とても蒸し暑い日だったのですが、ホールの中はエアコンが効きすぎるくらいに効いていた。リハーサルを終えて何だかキーに問題があるように感じ、ケイスケにそのことを相談したら、彼がキーのロッドをほんの少し絞めて一時問題は解決しました。しかし、今度は響きがわずかに失われてしまった感じがしたんです。
田中 パッドをアジャストするためにキーのロッドを締めたら、響きが若干タイトになったんですね。どちらを取るかの問題に迫られました。それが開演5分前のこと。それにしても、昨日は室内の温度が低いのに湿度が高かったので、楽器から水がボロボロと垂れ、デュフォーさんが「まるでツナミのようだ」と。

デュフォー フルートはエアコンを嫌います。特に日本はホールの内と外とで湿度や温度の差が激しく、楽器を傷めやすい。日本で演奏するときは、いつもケイスケがいてくれるので助かります。ミニチュアでいいから彼のクローンをヤマハが作ってくれないものか(笑)。そうすれば世界中どこにいても私は安心して演奏できる。
温度差では、冬の寒さもフルートには大敵です。気温が低いほど足部管側は冷えて低音域がフラットになり、頭部管側は息で温められて高音域がシャープになる。それを調整しながら吹くのは大変です。
ベルリンフィルに入って驚いたこと
──デュフォーさんは昨年、シカゴ響からベルリンフィルに移籍されました。演奏環境が大きく変わったのではないですか。
「あなたを採用したのは、あなたの個性がオーケストラに新しい風を入れると期待したからだ」と。
デュフォー どちらも素晴らしいオーケストラですが、ベルリンフィルは少年の頃から大好きなオーケストラでしたし、そこで吹くことは昔からの夢でした。 ベルリンフィルに入ってみて感じたのは、メンバー一人一人のアイデアがとても豊富で、サウンドは輝かしく、非常に柔軟なスタイルを持っているということ。何しろ、弦楽器のどのプルトの一人に至るまで全員がヴィルトゥオーゾなんです。フルートの同僚のエマニュエル・パユは、言うまでもなくソロイストとしても最も活躍している一人ですし、彼のような人たちが集まって一つのオーケストラを作っている。それにもかかわらず、彼らがオーケストラで演奏するときは、全員が真剣に音楽に奉仕するんですね。そこが一番印象的です。
──それまでよりも、より自発的に演奏できるようになった?
デュフォー ええ。ベルリンフィルは、言うならば大きな室内楽団です。実際、オケの中にはたくさんの室内楽グループが存在し、世界中で活動している。どんな指揮者が来ても、まず最初にやることは、お互いを聴き合って演奏するということ。その上で指揮者を見る。もし合わない部分があるとしたら、それはまず自分たちのせいだと考え、合わせるにはどうしたらいいかという会話が必ず行われる。ですからベルリンフィルでは、よそのオーケストラのように指揮者への不満を聞くことはあまりありません。
──ご自身のサウンド感は変わりましたか?
デュフォー ホールの響きがまず違います。それにアメリカとヨーロッパでは、隣りにいるオーボエのサウンドが異なります。シカゴ響という素晴らしいオーケストラでの体験が長かった分、ベルリンフィルではいまだチャレンジが続いていると言ってよい。でもそれは楽しくエキサイティングなチャレンジです。
そうは言っても、私はベルリンフィルの中で決して受け身でいるわけではありません。ここではいつもクリエイティブな演奏をするように仕向けられます。最初は自分を強く出すことにためらいがあったのですが、周りから「いや、もっとあなた自身を出していいんだよ」と。「あなたを採用したのは、あなたの個性がオーケストラに新しい風を入れることになると期待したからだ」というわけです。そうした彼らの姿勢に一番驚きましたね。
例えばオーボエの二人の首席は、一人はドイツ人(アルブレヒト・マイヤー)、もう一人はイギリス人(ジョナサン・ケリー)でサウンドも音楽もそれぞれに異なります。しかし方法は違っても、二人の行き着く先はいつも同じなのです。二人とも、私をどう演奏すべきかと導くのではなく、一緒に演奏するように仕向けます。ベルリンフィルでは、一つの「音」に融合するようにみんなが合わせるのではなく、一つの「音楽」に融合するように合わせ、そこに至る方法はそれぞれのやり方でいい。そうやっていつも、自分たちの新しい音楽や伝統を作ろうとしています。
田中 感動的なお話ですね。デュフォーさんがそうやって未来に向かって行くところに、私たちは道具としてついて行くだけだ、ということを改めて感じました。先へ先へと進むアーティストの希望に応えられるものを、私たちはひたすら追求し、作り続けていく。そのためには、両者の会話がもっともっと必要になるはずです。
デュフォー 音楽を演奏することは、進化し続けることと同じだと考えています。人間である限り、音楽家である限り、演奏は変わりつづける。私が今まで何度となく楽器を変えて来たのもそのためです。サウンドに対する自分の考えがいつも発展し続け、満足するということがなかった。
しかし、ヤマハのイデアルを手にしてからは、楽器を変えたいという欲求は無くなりました。なぜなら、楽器にとても自由度があるからです。楽器がどう吹けと指示するのではなく、自分が望むように楽器を操ることができる。私のアイデアが先にあり、楽器がそれについて来てくれる。もちろんイデアルには個性がありますが、その一番の個性というのが「フレキシビリティ」なんです。コンクールなどで審査員を務めると、演奏からどのメーカーのフルートを吹いているのかを判断できることが多いのですが、ヤマハだとそれが判りづらい。それがヤマハのとても優れた特質だと私は思います。
田中 ヤマハを使っていただいて、私たちはヤマハの音を聴きたいのではなく、デュフォーさんの音を聴きたいんですね。作る側の望みはそれだけです。演奏家が思う存分に個性を発揮できる「器」を用意するのが私たちの役目ですから。


*この対談は2016年10月~12月に管楽器の専門月刊誌「PIPERS」に掲載されたものです。
Mathieu Dufour
1972年パリ生まれ。8歳からパリの音楽学校で本格的にフルートを学び、14歳でゴールドメダルで卒業。その後、リヨン国立音楽院でマクサンス・ラリューに師事し満場一致の首席で卒業。1993年ランパル国際フルートコンクール2位、1994年ブダペスト国際音楽コンクール3位、1997年神戸国際フルートコンクール2位。1993年トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団首席、1996~1999年パリ・オペラ座管弦楽団スーパー・ソロイスト、1999~2014年シカゴ交響楽団首席を歴任し、2015年9月にベルリンフィル首席ソロ奏者に就任した。ソリストとして数多くのオーケストラと協演し、室内楽でも各国の音楽祭で著名な音楽家たちと共演している。CDはオクタヴィア・レコードから「フランス作品集」をリリースしている。
田中啓祐
「ヤマハ株式会社アコースティック楽器開発部B&O 開発グループ フルート担当 アトリエ駐在」として内外のフルーティストたちのサポートを行う。デュフォー氏のサポートは、米国ミシガン州のグランドラピッズにあるヤマハ・コーポレーション・オブ・アメリカに勤務していた時代から始まった。