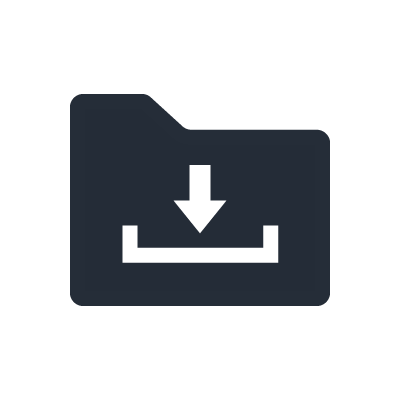アーティストたちから学んだ 大切な設計コンセプトとは?
ヤマハフルート[アルティザンとアーティスト交流の軌跡]
ヤマハフルートはルイ・ロットの系統を 目指したタイプ1に始まり、後にタイプ4と タイプ7の計3つの基本設計が生まれた。
──前号で原さんに、ヤマハ・ハンドメイドフルートの歴史は、ランパルに始まるフランス系のフルーティストたちとの交流から始まった、という話を伺いました。製品として見ると、原さんが最初に関わったハンドメイドフルートは、品番がまだ2桁だった時代ですね。
原 ヤマハが最初にハンドメイドフルートを発売したのは1975年で、その品番はYFL|81/83というものでした。その後1981年にモデルチェンジを行いましたが、そこから品番が3桁になり、現在に続いています。
タイプ1からタイプ4が生まれ、 ドイツでも広まった
田中 ヤマハの3桁の品番の末尾は基本設計の違いを表します。原さんの時代の「1」、その後スケールの異なる「4」が追加され、イデアルの「7」が加わります。「4」と「7」でスケールはほぼ変わりませんが、他の要素が大幅に変わっており、ヤマハ・ハンドメイドフルートには3つのタイプの基本設計がある事を意味します。
原 私はタイプ4まで関わっています。
──タイプ1というのは、ランパルとの出会いに触発されたルイ・ロットの系統になりますか。
原 ルイ・ロットを中心としたフレンチスクールの系統です。ハンミッヒなどのドイツ系を範とするメーカーもある中で、我々ははっきりとフランス系の楽器を意識して開発に取り組み、フランスの演奏家たちもそれをどんどん使ってくれました。しかし中にはアドリアンさんのように、フランスで勉強しながらドイツのオーケストラで活躍されているような方もいらっしゃる。そうした人たちからは、ランパルさんたちとは方向の異なる意見を頂いたわけです。営業サイドも、フランスだけでなくドイツでも売れる楽器が欲しい。それで新しく開発したのが「EC]という頭部管を持つタイプ4のモデルです。この時はアドリアンさんだけでなく、パウル・マイゼンさんの意見もずいぶんと取り入れました。
田中 ちなみに、タイプ1に付いていた頭部管は「CY」という頭部管です。
原 タイプ4の楽器はミュンヘンを中心にドイツでも広まり、神戸国際コンクールで最高位を取った方や、現在ドイツのオケで活躍されている方々が多くいらっしゃいます。ただ、アドリアンさんは年齢を重ねて趣向も変わって来ました。また新しいものを一緒にやろうということで始まった開発が、田中さんの時代につながって行くわけですね。
田中 はい。それで生まれたのがイデアルです(2011年)。ただしアドリアンさんは、音程についてはタイプ4に満足されていましたから、イデアル(タイプ7)の音孔の位置はタイプ4とほとんど変えていません。頭部管、本体共に大きく変わりました。アドリアンさんが望んだのは、もっとパワフルでふくよかな音が出ないかということ。どんなに息を吹き込んでも破綻せず、幅広い表現を可能とする楽器としてのキャパシティの大きさを求めました。それを実現させたのがイデアルです。
「牧神の午後」のC♯
原 タイプ1とタイプ4では、音孔の位置はかなり変えています。タイプ4はアドリアンさんの希望で、より平均律に近いスケールで、且つ、表現や音色に変化がつけられるようにしてあります。
──タイプ1はどんなスケールなのですか?
原 ルイ・ロットなどのフランス系のフルートは、例えばドビュッシーの「牧神の午後」の冒頭のC♯などを高めにとり、微妙な音色感を得る表現に向いているんですね。「牧神の午後」のC♯を平均律でとったら、彼らには面白くも何ともない。作曲家もこうした楽器の特性を知って書いています。
3オクターブ目のDの音もそうです。モーツァルトのコンチェルトにはDがたくさん出て来ますが、この音もフランス人は、音色感を出すためにやや高めにとる。日本のコンクールなどでよく、モーツァルトの第2楽章の3オクターブ目のDの音程が下がっちゃう演奏を聴きますが、どうしても音楽的には聞こえません。
フランス系の楽器だと、こうした音が音楽的なんです。フランス系とドイツ系とでは、音孔の位置に対するコンセプトが違います。基本的に昔のフランス系は全体のスケールのピッチは低かったと思います。それに対して、ドイツ系のヘルムート(ハンミッヒ)なんかは測ってみると442くらいあり、全体の寸法が詰まっている。ドイツではオーケストラでの演奏を重視しますから、ピッチが低いとオーケストラでは困るわけです。これに対してフランスではソロ重視というか、ピアノとかヴァイオリンと同じように、一人でどこまで表現できるかを目指します。グラーフさんがよくおっしゃったことですが、「ドイツ系の楽器だと、絵画のようにいろんな音で表現しにくい」と。反面、ドイツ系の楽器は、ドイツ音楽などの重厚な演奏には適しているわけですね。
田中 ただ、以前に比べれば今は、より平均律的な「音程重視」の方向に向かっていますね。作品のスタイルが昔よりも本当に拡がり、さまざまな拡張奏法なども使わないといけないわけですから、まずは確実にきちんとした音程が出ることが以前よりも強く求められていると思います。
原 その通りですね。
田中 音程が少しずれただけで仕事を失うリスクがあるとすれば、バシッと音程がはまり、安全に吹けるような楽器の方が良いと。でも、そうなると原さんがおっしゃった……
原 面白さがなくなるんですよ。色合いとかが。微妙に高めに吹いたり、低めに吹くことで音に色合いを添える、これは今までのソリストと呼ばれる人たちは意識的にやっていたことです。でも、現在はソリストという人は少ないじゃないですか。活発にソロ活動している人でも、皆さんオーケストラにポジションを持っている。ランパルさんにしてもラリューさんにしても、若い頃にオケには入っていましたけど、基本はソリストで、そうなると求めるものがやはり違うと思うんですね。華麗に、いかに音楽に色合いを付けて表現するかという。今はそうした人たちがほとんどいなくなったと思います。
ビジューの発売はセンセーショナルだった!
──工藤重典さんと一緒に開発した「ビジュー(Bijou)」(1997年)は、いま原さんがおっしゃったような典型的なフランス系のモデルですね。
原 そうです。タイプ1よりもフランス系の楽器です。
田中 ビジューは当時からセンセーショナルな商品だったと思います。他社さんからも「よく出せたね」と今も言われます(笑)。
原 ヤマハじゃないと出せなかったと思いますよ。
田中 本当にそう思います。普通なら、もっと楽に吹けて、音量も出て、という方向を目指すところを、ある意味、昔に戻るということでもありましたから。分かっていらっしゃる方には、この楽器をしっかりと吹き込んで行けば、その先に素晴らしいゴールが待っていることが見えているんですが、結果がすぐに欲しい人たちには、ビジューはとても難しい楽器に見えてしまう。でも、「今の時代にこうした楽器を出せるのはヤマハしかないよね」という誇りが私たちにはあるんですね。
──ビジューをもう少し吹きやすくしたものとして、2007年に「メルヴェイユ(Merveille)」が出ました。
田中 ビジューのコンセプトを受け継ぎつつ、より豊かな響きと、吹きやすさを両立させたモデルになります。
原 工藤さんが「音大生でも楽に取り組めるビジューのような楽器を作りたい」とおっしゃったんですよ。ビジューはある意味、ルイ・ロットに近い理想的な形を持っているんです。ところが音大生などには難しくてなかなか吹きこなせない。音大生は4年間のうちに結果を出さないといけませんから、楽器を吹きこなせずに終わってしまうのはまずい。それで、ビジューをもっと楽に吹ける形にしたのがメルヴェイユです。工藤さんにしてみれば、音大生にも音色の変化が得られるモデルをどんどん使ってもらいたかった。

入門機でも妥協しない!
──ハンドメイドからずれますが、ヤマハの初級モデル(スタンダードシリーズ)も品番の末尾が「1」でしたね。これはつまり、初級モデルにもそうしたフランス系の要素が入っているということですか。
田中 はい。初級モデルは2016年8月にモデルチェンジして末尾番号が「2」に変わりましたが、音孔の位置や、「CY」という頭部管はタイプ1と全く同じです。教育的な意味でも「この素晴らしい組み合わせを変えないで欲しい」という声が今でも大きいものですから。
原 ニコレさんが私たちにおっしゃったんですよ。「フルートの低音域などはお腹の圧力を使って出さないといけない。そうした基本を学べるような楽器が初級モデルにこそ必要だ」と。
ただ吹いただけで低音が楽に鳴ってしまうような楽器で始めると、身体全体を使って吹くことが学べなくなり、困ってしまうということです。世界にこれだけ普及しているモデルだからこそ、ヤマハはそこをしっかりと見極めて守って欲しいと。
もちろん初級モデルですから、歌口などは吹きやすいように若干カットしてあります。ヤマハの初級モデルは世界に何十万本と出ていまして、特にヨーロッパでは圧倒的なシェアを誇っています。それだけ作る側の責任も大きいわけですね。
──こうしたことはフルーティストたちに理解されていますか?
田中 指導される方々はよく理解して下さっていますね。自分がそれで育ち、演奏家になって教えたりするようになると、なるほどこれはとても良い頭部管だと。楽にポンと音が出るフルートを作ることは簡単なんです。しかしそれをやると、フルートたる魅力を持たない、ただボーボー鳴るだけの筒になってしまいます。そうなったらフルートの文化はお終いです。
原 歌口が大きくなるほど、ピアニシモが難しくなります。そうした楽器だと、密度のないつまらない音にしか聞こえない。常に同じ感じの音が「鳴りっぱなし」のように聞こえるわけですね。そうした演奏は、海外のコンクールでは特に評価されないと思います。昔はヤマハの頭部管は、スタンダードモデルからハンドメイドモデルまで、すべてこの「CY」だけでした。その後、バリエーションが増えて行き、ちょっと多すぎるということになって、今の7種類にまとまった。
田中 「A」は、当時の在欧R&D技術者とアドリアンさんが一緒に開発したもので、イデアルの頭部管。「Y」は「CY」と同じ。「H」はビジュー、「M」はメルヴェイユの頭部管です。「K」は僕がアメリカにいた時代にジェフリー・ケナーさん(フィラデルフィア管弦楽団首席)と一緒に開発したもの。「E」は「EC」と同じ、「C」は「CC」の派生バージョンです。
イデアルの発売のインパクト
──「イデアルでは他の頭部管を選ぶ必要がない」とアドリアン氏は言っていますね。
田中 イデアルは頭部管と本体を一体で設計していますので、まずはこの組み合わせで試して頂きたいと思います。イデアルの金製の頭部管は0.43ミリとかなり厚く、それに合わせて本体を、音孔の管の厚みを増やすなどしてバランスをとっていますから。
──イデアルはフルーティストたちにどんなインパクトを与えたと思いますか。
田中 ヤマハフルートに対する評価が確実に変わりました。変な話、「ヤマハらしくないね」とよくいわれるんです(笑)。アメリカにいた時代、オーケストラ奏者たちに「ヤマハは2番吹きには良い楽器だけれど」といわれたものですが、そうしたイメージが覆ったという声をたくさん耳にします。
──20万円台から50万円台までのプロフェッショナルモデル「フィネス(Finesse)」もタイプ7なんですね。ということは、イデアルの設計が取り込んである?
田中 イデアルの成果を下のモデルまで落とし込みました。フィネスの頭部管「Am」はそのグレードに合わせて歌口形状を最適化していますが、Aのような音の艶があり、きれいな響きを持ちます。同時にこれは、スタンダードモデルのCYの頭部管とも共通した要素を持っていますから、スタンダードモデルで始めた方が、無理なく自然にハンドメイドのイデアルまでステップアップして行けることになります。
世界的な人気を持つヤマハの木製フルート
──ヤマハの木製フルートはどのようにして開発されたのですか。
原 当時の試作室のスタッフが勉強のために作った木管があったんです。あるとき工藤重典さんが、サイトウ・キネン・フェスティバルで小澤征爾さんとマタイ受難曲のリハーサルをしていて、小澤さんから「工藤さんの音は幸せ過ぎる」と指摘され、そこでこの試作した木管フルートを実験的に使ってみた。結果、小澤さんが「そう、その音!」ととても気に入られたということで、「ぜひ本気で開発しませんか」と工藤さんに勧められたのが始まりでした。工藤さんは木管フルートについて、「多くの若いプレイヤーが14金製を使っているが、硬く鋭い音で吹いている人が多い。木管フルートで木製という原点に戻り、フルート本来の柔らかい音色を知ってほしい」とおっしゃっています。
田中 ヤマハはオーボエやクラリネットを作っていますから、木材についてのノウハウと加工技術は半端なくある。木管フルートをこれだけ薄く作れる(3.2ミリ)のもその現れです。
──木が薄いとどんな特長が?
田中 よく響いて軽やかに音が遠くへ飛んで行きます。木が厚いと、レスポンスはもう少し悪くなります。軽いですから持ち替えも楽ですし。音孔も他社ではできない埋め込み式になっています。ヤマハの木管フルートはアメリカでもヨーロッパでも、実は隠れたベストセラー機なんですよ。
原 コンセルトヘボウ管も購入してくれましたね。
田中 人気は「もの凄い!」と言っていいと思います。ただ、良い木を選別して使っていますので材料の確保が頭の痛いところなんですが。二重の責務を担いながら……
Our significant responsibilities…
──同じフルートの設計に携わりながらも、お二人は異なる時代のアーティストたちと密に接して来られたわけですが、そうした時代の違いはそれぞれにお感じになりますか。
原 私が密接にお付き合いさせて頂いた方々は、ランパルさんやニコレさんは亡くなってしまいましたけれども、皆さんすでに高齢になられている。一方、田中さんはマチュー・デュフォーさん(シリーズ第1回参照)のような若い世代と一緒に仕事をしているわけで、当然のことですが、私がやっていた時代とはいろいろな面で別の方向を目指しているのだと思いますね。

田中 先ほども話に出ましたが、ヤマハのスタンダードモデルがこれほど世界中に普及していると、製作に携わる人間として、まずは「フルート文化をしっかりと支えていかなければいけない」という責任を強く感じます。そのスペックや歴史……もう「文化」と言っていいと思いますが、それを作って来たのは原さんなどの先人の皆さんのおかげなんですね。僕らはその上で仕事をさせてもらっている。まずはそうしたことを感じます。
もう一つ、ますます厳しい時代に直面する中で、今のフルーティストたちはこれまでの世界をこの手でさらに拡げよう、今までになかった新しい表現が出来ないかと、絶えず懸命に模索しているように思えます。演奏スタイルや表現もどんどん幅広くなっている。そうしたプレイヤーたちの要求に、楽器も当然のことながら追いついていかないといけないわけです。そうした責務もひしひしと感じます。
フルート文化の裾野を拡げると同時に、その最先端にいるアーティストたちの様々な要望にも応えていかないといけない。そうした二重の責務を同時に担いながら、私たちも絶えず前を見て進んでいくしかないわけですね。それが今の時代なんだと思いますね。
*この対談は2016年10月~12月に管楽器の専門月刊誌「PIPERS」に掲載されたものです。
原嘉靖(はら・よしやす)
東京音楽大学卒、1971年4月ヤマハ株式会社・管教育楽器技術部管楽器設計課入社。長年にわたるフルート・ピッコロの研究開発、改良業務を通じてヨーロッパ・アメリカの著名なフルーティストから信頼を得ている。管楽器設計課長、フルートセンター長、管楽器設計課主査を経て2003年9月に定年退職後、アドバイザーとして研究開発・改良業務へのアドバイス、専門家・レスナーへの対応を行っている。フルート工房HARA主宰。代官山音楽院講師。
原嘉靖さんは、2024年9月24日に逝去されました。 心よりご冥福をお祈りいたします。
田中啓祐
「ヤマハ株式会社アコースティック楽器開発部B&O 開発グループ フルート担当 アトリエ駐在」として内外のフルーティストたちのサポートを行う。デュフォー氏のサポートは、米国ミシガン州のグランドラピッズにあるヤマハ・コーポレーション・オブ・アメリカに勤務していた時代から始まった。