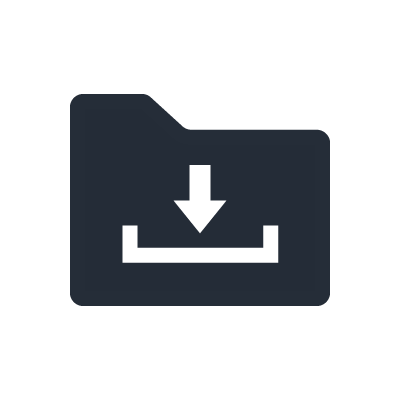ハンドメイドモデルの歴史は ランパルとの出会いに始まった。
ヤマハフルート[アルティザンとアーティスト交流の軌跡]
浜松でコンサートを行ったランパル氏が、 挨拶を兼ねて持参した試作品を、その日の プログラムの後半でいきなり使用!
──原さんは2003年に定年でヤマハを退社された後も、アドヴァイザーとしてフルートの設計や内外のフルーティストたちへの対応に関わっていらっしゃいます。ヤマハに入社される前は、東京音楽大学でフルートを専攻されていたのですね。
原 ええ、1年のときに川崎優先生、2年目から植村泰一先生に師事しました。数学とドイツ語で引っかかったものですから5年で卒業しています。
──卒業後すぐにヤマハに?
原 はい。4年生のときに川崎先生から電話を頂きましてね。ヤマハに豊岡工場という新しい工場ができるから、そこで働いてみないかと。でも卒業出来なかったものですからその話は消え、前から希望していた通り、中学校の音楽の先生になるつもりで教育実習を受けたりしていました。
ところが5年目にまた川崎先生から、「ヤマハはいま高級モデルの開発を進めていて、演奏家と交流できる人材を育てたがっている。働いてみないか」と電話を頂いたんですね。これはチャンスだ、ヤマハに入れば世界をこの目で見られるかも知れないと思い、5年生の夏に工場で実習を受け、重役面接などを経て、翌年(1971年)入社しました。
──最初はどんなお仕事を?
原 フルートの設計課に回ったのは2 年目からで、1年目は製作の現場でフルート作りを一から勉強させてもらいました。フルートの設計は3人の先輩たちが担当していましたが、ちょうどハンドメイドモデルを発売する直前で、その製作に工場から5人ほどが選ばれ、そこに私も加わったわけです。設計をやる人間が現場で一からフルート作りを学ぶというのは初めてだったようで、高級モデルを作るに当たっては最初からフルート作りを学んだ方がいいという配慮でした。この時の経験が私のすべての根源になっていますので、今でも本当に感謝しています。
2年目から設計に回りましたが、ハンドメイドモデルの本体の設計は終わっていましたから、私は頭部管を担当しました。設計と言っても、現場でさまざまな試作品を作り、それをいろんな演奏家の方々に試奏してもらい、結果の良いものを図面に落としていくという作業の連続です。
ランパル氏との幸福な出会い
──で、すぐにランパルさんとの出会いがあった。

原 入社して1年目の10月か11月かに、ランパルさんが浜松でコンサートを行った。良いチャンスだと思い、試作品の楽器を持って訪ねて行ったんです。マネジメントを通じて面会のOKは取り付けてありましたが、怖いもの知らずでした。休憩時間にランパルさんが現れたので、「よろしければ一度試してみて頂けないでしょうか」とお聞きしたら、その場でパパッと吹いて「ちょっと借りていいか?」とそのまま消えてしまった。なんと、コンサートの後半でその楽器を使って下さったんです。あれには本当にビックリし、同時に感激しました。
あとでお聞きしたら、「今まで吹いた日本のフルートはどれも吹きやすいけれど、私には面白さが感じられなかった。しかしヤマハは違った。歌口が大きくなく、良い抵抗感があって自分で音楽を作れる楽器だった。だから使ってみたのだ」と。そこからですね、ランパルさんとのお付き合いが始まったのは。
ただ、私自身は浮かれてばかりいたわけではなく、客席で冷静にランパルさんの演奏を聴くと、氏がその日お吹きになった楽器とはやはり何かが違うと感じました。その日使われたのはヘインズの金でしたが、ヘインズの方が低音から高音まで朗々と聞こえ、音楽的なんです。私が持っていった試作品はタイトで音の幅が狭い感じがしました。
終演後にランパルさんに御礼を申し上げたら「自分のために使ったことだから」とおっしゃり、ご自分の18金のルイ・ロットと14金のヘインズを「好きなように見てもいいし、吹いてみてもいいよ」と言って下さった。
この18金のルイ・ロットというのは、ルイ・ロットがただ1本作ったと云われる金のフルートです。ランパルのお父さんのジョゼフ・ランパルさんがパリの古物商でバラバラになっているのを見つけて購入し、組み立ててみたら、ネジ1本まで全部揃っていたという曰く付きのものです。それをランパルさんが譲り受けて愛用していた。ランパルさんが当時「黄金のフルーティスト」と呼ばれていたのは、実はこのことです。単に金のフルートを吹く人という意味ではなく、世界にただ1本の金のロットのフルートを吹く人、ということですね。
氏が愛用したもう1本のヘインズの14金は、そのロットを参考にしてヘインズに作らせたものです。通常のヘインズの金は440.450グラムですが、400グラムしかなく、非常に軽い。ロットに似せて特別に軽量化して作ったんですね。調べてみると、60年代のランパルさんの録音はすべてロットの18金、60年代後半から70年代にかけてはヘインズの14金で録音しているようです。よく聴けばその違いが分かります。
──その世界に1本のロットを、ランパルに頼まれて原さんは大修理することになった……。

原 その2年後くらいでしたか、ランパルさんがまた来日されたとき、マネージャーが電話で「すぐに東京まで来て欲しい」というんです。「18金のロットを落としてしまったから診てくれないか」というんですね。すぐに滞在先の帝国ホテルに駆けつけて楽器を見たら、巻き管で作ってある本体の継ぎ目部分がパックリ割れてギザギザになってるんですよ。「修理にどのくらい時間をいただけるか?」と聞くと、日本滞在の1週間しかないと。「完璧には直らないかも知れませんが何とかトライします」と返答し、すぐに楽器を浜松に持ち帰りました。
問題は、楽器と同じ金の材料がすぐに手に入るかどうかです。楽器を蛍光分析にかけてみたら、材料は18金でした。ヤマハはまだ金のフルートを作ったことがない。試作室に相談しても「難しい」と28いう。そこで思案して、歯医者さんならあるだろうと。案の定、18金の板を分けてもらうことが出来まして、それを叩いたりローラーで引いたりして薄く延ばし、ロットと同じ厚さにしていく……これだけで2日間かかりました。何とか修理を終え、1週間後に持って行ったら、ランパルさんは大喜びされました。
──その後も、来日のたびに調整を依頼されたとか。

原 ええ、毎回ほぼ必ず。演奏会場に行ったり楽器をお預かりしたり、10数回はやらせて頂いたと思います。ロットを修理したことでこちらを信頼して下さったんですね。
余談になりますが、ロットはピッチが低いんです。楽器がやや長くて、音孔の間隔も開いており、計算では435くらいしかない。ランパルさんが使っていらした古いヘインズも、ピッチの基本設計は438程度。それを当時440として発売していました。そうした楽器を使い続けていることについてランパルさんは、「何十年も使い続けて来て、もう一心同体のようなもの。もし上手く行かないことがあったとしても、それは自分のコンディションの問題であって楽器のせいではない」と。442のヘインズもお持ちでしたが、それはウィーンなどピッチの高い地域で演奏する場合や、楽器を私に修理に預けたような時の「緊急用」だったようです。
もう一つ忘れられないのは、「私はこのヘインズを自分の音にするのに8年かかった」とおっしゃったことです。ランパルさんにいわせれば、「今の若い人たちは簡単に鳴ってしまう楽器を使おうとする。それだとみんな同じ音になってしまうじゃないか。音楽や音色は自分で苦労して作りあげて行くものだ」と。
銀のヤマハが生んだつながり
──そのランパルさんとの出会いが、アンドラーシュ・アドリアン氏や工藤重典さんなどとの出会いに繋がっていくわけですね。
原 そのきっかけは、浜松で最初にランパルさんがお吹きになった例のヤマハです。2度目にお会いしたとき、「あの銀のヤマハがとても気に入ったから持って帰りたい」とおっしゃった。ランパルさんはそれをニースの夏期講習会やパリ音楽院のレッスンなどでお使いになったんです。
アドリアンさんは、ニースでランパルさんにそのヤマハを吹かせてもらい、気に入ってすぐに同じものを注文して下さった。氏がまだ北西ドイツフィルにいらした頃でした。アドリアンさんとはその後もいろんな試作を重ねました。もっと響きの大きな楽器が欲しいということで、ランパルさんとは別の方向でアドバイスを頂きながら今日まで来ています。
ランパルさんが持って帰ったヤマハにはさらに後日談があります。当時、試作品を持ってヨーロッパを回っていた私たちは、ある日ランパルさんのパリの自宅に招待されました。モーツァルト通りという高級住宅地の古い立派なアパートメントを訪ねたら、ランパルさんが「私の生徒のクドウという日本人は必ず世界に名を成す人材だ。今度のパリ国際コンクールを受けさせたいので、お借りしているヤマハを彼に貸してもいいか」というんですね。そのとき工藤重典さんのことを存知上げなかったんですが、「もちろん自由にして頂いて結構です」と答えました。それで工藤さんはパリ国際コンクールで見事1位になり、その後もミュンヘンのコンクールで1位なしの3位になられた。
工藤さんにお会いしたのは、1978年に氏が凱旋コンサートを東京文化会館小ホールで行ったときでした。工藤さんはそのコンサートでもランパルさんから借りたヤマハを使ったのですが、私の印象では、楽器が若い工藤さんのエネルギーに負けている感じがしたんです。そう思ったものですから、終演後に楽屋で初めてお会いしたとき、正直にそのことを話し、「もっと工藤さんに合った楽器を作れると思いますので吹いて頂けますか」と申し上げたら「喜んで」とおっしゃって下さった。
そこから試作がいろいろ始まり、出来上がったものを工藤さんに吹いていただいたら、今度は第1回ランパル国際フルート・コンクール(1980年)で1位と大統領特別賞を獲得されたんです。工藤さんはそれで一躍世界にその名が知られるようになりました。
これも余談になりますが、工藤さんはものすごくテンポの速い方なんですよ。氏の車に乗せてもらうと、鮮やかなハンドルさばきでパリ市内をものすごいスピードで走られる。同じように楽器も、数ヶ月くらいで結果を出さないと満足されません。じつはそうやって、我々を試されるんですね。本気でやってくれるかどうかを。こちらがそれに応えようと一所懸命に努力すれば、たとえ遅れや失敗があったとしても許してくれる。そうやって信頼を得るのに1年かかりました。


ベーカー、グラーフ、ニコレ……

原 当時は工藤さんだけでなく、グラフェナウアー、アドリアン、グラーフ、ラリュー、ラルデといった人たちもヤマハに注目して下さり、そうした人たちの楽器も同時並行的に作っていました。フランス国立管弦楽団のフィリップ・ピエルロさんの場合は、氏のお父さんで有名なオーボエ奏者のピエール・ピエルロさんが草津の講習会にみえたとき「息子をよろしく」というので、初めてヤマハを使って頂いているのを知りました。
当時、私の上司で部長だった梶(吉宏)さんから「原君、自由にどんどんやっていいよ」といわれ、予算もたくさん付けていただいたおかげで、試作品を抱えてヨーロッパ中を自由に駆け回ることができた、そんな時代でした。その後はヨーロッパにアトリエが開設され、我々が直接出向かなくてもよくなりました。
──ジュリアス・ベーカー氏もヤマハと縁が深かった人ですね。

原 私が入社する前から、頭部管などについていろいろアドバイスを頂いていましたね。とても細かなところにまで厳しい方で、例えば工場にお見えになると、スチューデント・モデルのラインから1本を抜き出し、持参したゲージを取り出して頭部管の歌口部分の内径を測るんです。厳密に17.35ミリになっているかと。当時は芯金の摩耗などで、たまに数値がずれているものがあったのですが、「これじゃダメだ」と怒られました。おかげで生産管理面でも細かなところまで大変勉強させて頂きました。根はとても優しい方なんですが、こと製作に関してはとても怖かったですね。
グラフェナウアーさんは、楽器の調整については世界一と言ってもいいほどシビアな方でした。
「この音が引っかかるのはパッドが漏れているせいだ」といわれて調べると、その通りどこかが僅かに漏れているんです。初めてヤマハを吹いて頂いた時、すぐに気にいられて2本購入していただきました。1本はAタイプの管体金製モデルと、もう1本はスペア用とのことで、ポストが金、他は金メッキのモデルです。
──使ってもらえるまで時間がかかった人もいたのではないですか。

原 グラーフさんは10年かかりました。試作を持参するたびに「まだだ」と。「日本のフルートには音色感がない」とよくおっしゃいました。「白黒の濃淡だけで表現する墨絵と、西洋絵画の違いと同じだ。楽器は何色もの色を出せないといけない」と。それからというもの、ヨーロッパに行く度に美術館に立ち寄り、彫刻や絵画を見るように努めました。面白いもので、何十回も見ているとだんだん本物の違いが分かって来ます。
グラーフさんは、10年目にしてやっと「これなら使える」と言って本番で使って下さった。ただその時も私には、氏が使っている楽器と比べてまだ何か物足りないものを感じたものですから、「もう1年待って下さい。必ずもっと良いものを作りますから」と申し上げると、「メーカーの人間からそんな言葉を聞いたのは初めてだ。これからは君の言うことを全部信じるよ」と言って、以後はファーストネームで呼び合う仲になりました。アドリアンさんともそうでしたね。
「今のままを維持してくれ」

また、ヤマハを使って頂いたわけではありませんが、ニコレさんの言葉も私の中に強く刻みつけられています。
「日本の若い音楽家たちには、過去の大家の真似をする人たちが大勢いる。自分はどう解釈するのか、どう演奏したいのかが伝わって来ない。若いのならもっと羽目を外してでも冒険すべきだ。同じように、日本の楽器も過去の範疇からいまだ抜け出ていない。音量は出るようになったが、安全を狙い過ぎて表現の幅が狭くなっている」
ただニコレさんは、ヤマハのスチューデントモデルをとても高く評価して下さり、何度も結構な本数を注文して下さいました。ゴールウェイさんも「ヤマハのスチューデントモデルは世界一だ」とおっしゃって、オーストラリアやイギリスで広く勧めて下さいました。ニコレさんはヤマハのスチューデントモデルについて、 「頼むから今のままを維持してくれ。最初から吹きやす過ぎる楽器を使うと、高級モデルにシフトした時に困る事態になる」と。「ヤマハのように世界的に影響のあるメーカーだからこそ、他メーカーのように歌口のライザーの壁を高くしたり吹きやすくしたものを作らないで欲しい」と強くサゼスチョンされました。
同じことはランパルさんもおっしゃったことです。「吹きやすいだけの楽器は作らないでくれ」と。ラリューさんもラルデさんも、もちろん工藤さんも、私がお会いしたフランス系の人たちは皆さんそうおっしゃいましたね。
──個性の異なる多くのフルーティストたちから様々な意見をもらいながら、ご自分の中ではそれをどのように整理なさったのですか。
原 いえ、皆さんおっしゃることには共通点もたくさんあるわけです。それをまとめるのはこちらの自由です。もちろん、自分たちはどんな楽器を作りたいのかという強い意思が、そこに無ければいけません。
その点、僕らにはルイ・ロットという一つのモデルがありました。ロットのようなフランス系の楽器ですね。ドイツの楽器を範とするメーカーが多かった中で、ヤマハはフランス系に的を絞って開発を進めたわけです。
──その辺りは次号で、前号のマチュー・デュフォー氏との対談に登場した技術者の田中啓祐さんも交えてお聞きしたいと思います。
*この対談は2016年10月~12月に管楽器の専門月刊誌「PIPERS」に掲載されたものです。
原嘉靖(はら・よしやす)
東京音楽大学卒、1971年4月ヤマハ株式会社・管教育楽器技術部管楽器設計課入社。長年にわたるフルート・ピッコロの研究開発、改良業務を通じてヨーロッパ・アメリカの著名なフルーティストから信頼を得ている。管楽器設計課長、フルートセンター長、管楽器設計課主査を経て2003年9月に定年退職後、アドバイザーとして研究開発・改良業務へのアドバイス、専門家・レスナーへの対応を行っている。フルート工房HARA主宰。代官山音楽院講師。
原嘉靖さんは、2024年9月24日に逝去されました。 心よりご冥福をお祈りいたします。