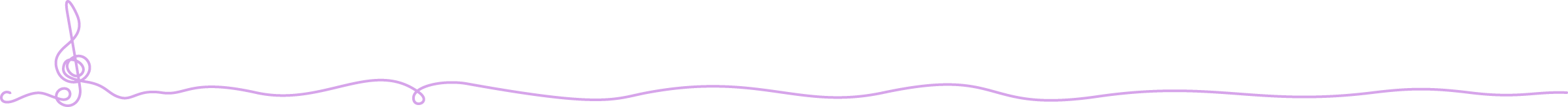名曲について知る
古典派の名曲
音楽史における古典派時代に活躍した作曲家のなかで、現在においても有名な人はハイドンとモーツァルトの二人です。この二人と次の世代のベートーヴェンは、ウィーンを主な活動の場としたために、彼らのことを「ウィーン古典派」と総称することもあります。今回と次回で、「ウィーン古典派」の3人の作曲家の名曲をご紹介します。
フランツ・ヨセフ・ハイドン
- ハイドン:交響曲第45番 嬰へ短調「告別」
18世紀は交響曲が産まれた時代でもありましたが、ハイドンは交響曲を100曲以上も作曲し、「交響曲の父」というニックネームで呼ばれることもあります。彼の交響曲は1750年代から1790年代までという長い期間に作曲されており、ハイドンの交響曲の作曲活動自体が古典派における交響曲発展の歴史でもあるのではないでしょうか。交響曲第45番は「告別」というニックネームで知られていますが、このニックネームの由来は次のようなエピソードに基づいています。

ハイドンが演奏を供したエステルハーザ城の広間
ハイドンが宮廷楽長を務めていたエステルハージ侯爵はハンガリーの貴族でした。侯爵は夏の離宮での生活を好み、宮廷楽団の楽員たちは侯爵の離宮滞在に同行しなければなりません。この滞在が長引くと、楽員たちは家族と会えずに淋しい思いをしていました。楽員たちの想いを侯爵に音楽で伝えようと一計を案じたハイドンが作曲したのがこの交響曲でした。この交響曲は、最後の第4楽章は途中でアダージョになります。このアダージョは非常に伸びやかな旋律をもつ部分ですが、音楽が進むに連れて、徐々にパートの数が少なくなっていくのです。演奏を終えた楽員たちがその場から退場していくと、最後にはコンサートマスターのハイドンと第2ヴァイオリンの主席奏者だけとなり、2人で淋しく曲が閉じられるのです。このパフォーマンスによって、ハイドンの思惑通り、侯爵は楽員たちの想いを悟り、家族のもとへ彼らを帰したのでした。
この有名なエピソードによって、この交響曲はたいへん有名になり、演奏機会にも恵まれています。第3楽章までの音楽も非常に優れたもので、1770年代のハイドンを代表する作品と言えるでしょう。

ハイドンが演奏を供したエステルハーザ城の広間
ハイドンが宮廷楽長を務めていたエステルハージ侯爵はハンガリーの貴族でした。侯爵は夏の離宮での生活を好み、宮廷楽団の楽員たちは侯爵の離宮滞在に同行しなければなりません。この滞在が長引くと、楽員たちは家族と会えずに淋しい思いをしていました。楽員たちの想いを侯爵に音楽で伝えようと一計を案じたハイドンが作曲したのがこの交響曲でした。この交響曲は、最後の第4楽章は途中でアダージョになります。このアダージョは非常に伸びやかな旋律をもつ部分ですが、音楽が進むに連れて、徐々にパートの数が少なくなっていくのです。演奏を終えた楽員たちがその場から退場していくと、最後にはコンサートマスターのハイドンと第2ヴァイオリンの主席奏者だけとなり、2人で淋しく曲が閉じられるのです。このパフォーマンスによって、ハイドンの思惑通り、侯爵は楽員たちの想いを悟り、家族のもとへ彼らを帰したのでした。
この有名なエピソードによって、この交響曲はたいへん有名になり、演奏機会にも恵まれています。第3楽章までの音楽も非常に優れたもので、1770年代のハイドンを代表する作品と言えるでしょう。
- ハイドン:弦楽四重奏曲第67番 ニ短調「ひばり」

ハイドンの時代に描かれた
ひばりの絵
交響曲とともに、古典派時代に確立された器楽曲のジャンルに、弦楽四重奏曲があります。2人のヴァイオリンと1人ずつのヴィオラとチェロで演奏される楽曲です。ハイドンは1760年代から1790年代までの間に、弦楽四重奏曲の作曲を続けました。通し番号で83番までを数える作品が残されており(第13番から第21番までは、現在では他人の作であることが判明しています)、交響曲と同様に、ハイドンは弦楽四重奏曲の父でもあるわけです。ハイドンの作品によって、弦楽四重奏曲は室内楽のなかで最も重要なジャンルとして認められ、その流れはベートーヴェン以降の作曲家たちにも受け継がれています。
1790年に作曲された「ひばり」のニックネームは、ハイドン自身が付けたものではありません。第1楽章で第1ヴァイオリンが最初に弾き始める流麗な旋律が、ひばりのさえずりを真似しているように聞こえるため、いつからか「ひばり」という名で呼ばれるようになったようです。第1楽章は「ひばり」の名の由来となった旋律ばかりが注目されていますが、充実したソナタ形式で書かれている点も聞き逃してはならないでしょう。第2楽章のアダージョは、落ち着いた雰囲気のなかで美しい旋律が流れていきます。非常に繊細な和音の使い方は、円熟期のハイドンならではと言えます。第3楽章のメヌエットは軽快なリズムが特徴的です。最後の第4楽章は非常に短いのですが、第1ヴァイオリンが休むことなく動き続け、スリル満点の音楽となっています。
70曲を越えるハイドンの弦楽四重奏曲はどの作品も素晴らしいものばかりではありますが、人気のある作品はニックネームをもつ作品(「皇帝」「五度」など全部で9曲)に集中する傾向があるのはたいへん残念なことではないでしょうか。「ひばり」を聴いてハイドンの弦楽四重奏曲に興味を持たれた方は、ぜひともすべての弦楽四重奏曲を聴くことをお薦めしたいと想います。
1790年に作曲された「ひばり」のニックネームは、ハイドン自身が付けたものではありません。第1楽章で第1ヴァイオリンが最初に弾き始める流麗な旋律が、ひばりのさえずりを真似しているように聞こえるため、いつからか「ひばり」という名で呼ばれるようになったようです。第1楽章は「ひばり」の名の由来となった旋律ばかりが注目されていますが、充実したソナタ形式で書かれている点も聞き逃してはならないでしょう。第2楽章のアダージョは、落ち着いた雰囲気のなかで美しい旋律が流れていきます。非常に繊細な和音の使い方は、円熟期のハイドンならではと言えます。第3楽章のメヌエットは軽快なリズムが特徴的です。最後の第4楽章は非常に短いのですが、第1ヴァイオリンが休むことなく動き続け、スリル満点の音楽となっています。
70曲を越えるハイドンの弦楽四重奏曲はどの作品も素晴らしいものばかりではありますが、人気のある作品はニックネームをもつ作品(「皇帝」「五度」など全部で9曲)に集中する傾向があるのはたいへん残念なことではないでしょうか。「ひばり」を聴いてハイドンの弦楽四重奏曲に興味を持たれた方は、ぜひともすべての弦楽四重奏曲を聴くことをお薦めしたいと想います。
ヴォルフガング・アマデーウス・モーツァルト
- ピアノ・ソナタ第11番 イ長調 K.331「トルコ行進曲付き」

モーツァルトが使用していた
ハンマーフリューゲル
(アントーン・ヴァルター製作)
モーツァルトは作曲家としてだけでなく、当代一流のピアニストとしても知られていました。とくにウィーンで活動した1780年代では、モーツァルトは基本的にはフリーランスの音楽家でしたから、ピアノの演奏と教授も重要な仕事の一部だったのです。このソナタはウィーン時代の初期に作曲され、モーツァルトのピアニストとしての能力をウィーンの人々に知らしめるために出版も行われました。なお、このソナタは第3楽章が「アッラ・トゥルカ(トルコ風)」と題されているために、「トルコ行進曲付き」というニックネームで呼ばれることがあります。
このソナタは3つの楽章からなっていますが、楽章の配列は非常に変わっています。第1楽章は通常のアレグロではなく、アンダンテのテンポによる主題と変奏曲です。素朴な民謡のような主題が巧みな変奏の技術によって、多彩な表情をもつ音楽に生まれ変わっていきます。とりわけアダージョにテンポを落として繊細な装飾が付されていく第5変奏、溌剌とした4拍子のアレグロに変貌する最後の第6変奏はたいへん印象的でしょう。第2楽章は、モーツァルトのピアノ・ソナタでは珍しいメヌエット楽章です。中間部のトリオも含め、モーツァルトが書いたメヌエット楽章で最大規模を誇ります。第3楽章は先述したように「アッラ・トゥルカ」です。18世紀のオーストリアはいくたびかトルコと戦争となり、トルコの軍楽隊はウィーンの人々にも身近なものだったと言われます。トルコを舞台としたオペラなどもたくさん書かれましたが(モーツァルトの「後宮からの誘拐」もその一つです)、トルコ風な音楽の模倣は当時のヨーロッパで大いに流行していたのです。当時のヨーロッパ人が「トルコ風な音楽」の特徴としたことは、短調と長調が交替すること、トライアングルやシンバルなどの打楽器の使用などでした。この楽章は短調で始まりますが、途中で長調の部分が現れますし、その部分では左手のパートが打楽器的な音型を模倣しているようにも思えます。
このソナタは3つの楽章からなっていますが、楽章の配列は非常に変わっています。第1楽章は通常のアレグロではなく、アンダンテのテンポによる主題と変奏曲です。素朴な民謡のような主題が巧みな変奏の技術によって、多彩な表情をもつ音楽に生まれ変わっていきます。とりわけアダージョにテンポを落として繊細な装飾が付されていく第5変奏、溌剌とした4拍子のアレグロに変貌する最後の第6変奏はたいへん印象的でしょう。第2楽章は、モーツァルトのピアノ・ソナタでは珍しいメヌエット楽章です。中間部のトリオも含め、モーツァルトが書いたメヌエット楽章で最大規模を誇ります。第3楽章は先述したように「アッラ・トゥルカ」です。18世紀のオーストリアはいくたびかトルコと戦争となり、トルコの軍楽隊はウィーンの人々にも身近なものだったと言われます。トルコを舞台としたオペラなどもたくさん書かれましたが(モーツァルトの「後宮からの誘拐」もその一つです)、トルコ風な音楽の模倣は当時のヨーロッパで大いに流行していたのです。当時のヨーロッパ人が「トルコ風な音楽」の特徴としたことは、短調と長調が交替すること、トライアングルやシンバルなどの打楽器の使用などでした。この楽章は短調で始まりますが、途中で長調の部分が現れますし、その部分では左手のパートが打楽器的な音型を模倣しているようにも思えます。
- 交響曲第40番 ト短調 K.550
1788年に、モーツァルトは最後の3曲の交響曲、第39番、第40番、第41番「ジュピター」を作曲しました。第40番はとりわけ有名ですが、それはなぜでしょうか。おそらく短調で書かれていることが要因だと思われます。古典派時代は長調の音楽が偏愛された時代でもありました。とくに交響曲のジャンルではその傾向が強かったようです。そのような時代にあって、短調の交響曲は非常に特殊なものだったと言えるでしょう。ベートーヴェン以降になりますと、短調の交響曲は特殊なものではなくなっていったため、モーツァルトの第40番が名曲として愛好されるようになったのではないでしょうか。しかし、テレビのコマーシャルでも使用されることもあるほど有名な曲にもかかわらず、この作品は難しい作曲技術を執拗に盛り込んだ点が、実は非常に特徴的なのです。

交響曲第40番の自筆譜
第1楽章は、余りにも有名な旋律で始まります。美しいけれどもどこか悲しげなその表情は、短調の交響曲を始めるのに相応しいものと言えます。第2楽章はアンダンテです。アンダンテの楽章は古典派時代にあっては、民謡調の素朴な旋律に基づくことが多かったのですが、モーツァルトはここで非常に深遠な世界を切り開いています。第3楽章はメヌエットです。しかし、ここで使用されるリズムはあまりメヌエットらしくありません。中間部のトリオは長調となり、ホルンを中心とした木管楽器の活躍が印象的です。第4楽章は激しさと静けさが絶妙なバランスで同居する楽章です。展開部では、モーツァルトの高度な作曲技術が駆使された個所で、とりわけその冒頭には驚いてしまいます。最初の8小節で、12の半音のうち11半音がすべて現れるのです。20世紀前半に生まれた「12音技法」にも通じる音の動きは、古典派時代の常識を破るものだったのではないでしょうか。

交響曲第40番の自筆譜
第1楽章は、余りにも有名な旋律で始まります。美しいけれどもどこか悲しげなその表情は、短調の交響曲を始めるのに相応しいものと言えます。第2楽章はアンダンテです。アンダンテの楽章は古典派時代にあっては、民謡調の素朴な旋律に基づくことが多かったのですが、モーツァルトはここで非常に深遠な世界を切り開いています。第3楽章はメヌエットです。しかし、ここで使用されるリズムはあまりメヌエットらしくありません。中間部のトリオは長調となり、ホルンを中心とした木管楽器の活躍が印象的です。第4楽章は激しさと静けさが絶妙なバランスで同居する楽章です。展開部では、モーツァルトの高度な作曲技術が駆使された個所で、とりわけその冒頭には驚いてしまいます。最初の8小節で、12の半音のうち11半音がすべて現れるのです。20世紀前半に生まれた「12音技法」にも通じる音の動きは、古典派時代の常識を破るものだったのではないでしょうか。
- セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

セレナード(ナハトムジーク)の
演奏風景
この作品も、モーツァルトの代名詞とも言えるほど、よく知られたものです。「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」とは、モーツァルト自身の命名で、ドイツ語で「小セレナード」という意味です。非常に有名な作品であるにもかかわらず、この作品の成立は多くの謎に包まれてます。たとえば、モーツァルトが作成していた自作品の目録では、メヌエット楽章を2つ持つ5楽章構成とされているのに、現存する楽譜はメヌエット楽章が1つしかない4楽章構成です。おそらくもう一つのメヌエット楽章は紛失してしまったと思われますが、おかげでこの作品は交響曲のように4楽章構成で知られるようになりました。もう一つの大きな謎は、楽器編成に関することです。弦楽合奏で演奏すべきか、弦楽四重奏曲のように各パート一人ずつで演奏すべきか、モーツァルトははっきりと指定していないのです。そのためか、この作品は弦楽合奏や弦楽四重奏、または弦楽四重奏にコントラバス奏者を加えた五重奏など、様々な形態で演奏されています。
第1楽章はモーツァルトらしい、溌剌とした音楽になっています。交響曲第40番のような複雑さはあまり見られず、簡潔さを旨とした古典派音楽の最上の例と言えるのではないでしょうか。第2楽章は「ロマンス」と題され、ゆっくりとしたテンポで美しいメロディが流れていきます。第3楽章はメヌエット楽章です。生き生きとしたリズムが印象的な主部と、流麗な中間部のトリオが対比されています。第4楽章は「ロンド」と題されていますが、実質的にはソナタ形式で書かれています。軽快で楽しげな第1主題は、18世紀には愉快な気分をもつべきとされていたロンドの楽章にぴったりです。
第1楽章はモーツァルトらしい、溌剌とした音楽になっています。交響曲第40番のような複雑さはあまり見られず、簡潔さを旨とした古典派音楽の最上の例と言えるのではないでしょうか。第2楽章は「ロマンス」と題され、ゆっくりとしたテンポで美しいメロディが流れていきます。第3楽章はメヌエット楽章です。生き生きとしたリズムが印象的な主部と、流麗な中間部のトリオが対比されています。第4楽章は「ロンド」と題されていますが、実質的にはソナタ形式で書かれています。軽快で楽しげな第1主題は、18世紀には愉快な気分をもつべきとされていたロンドの楽章にぴったりです。