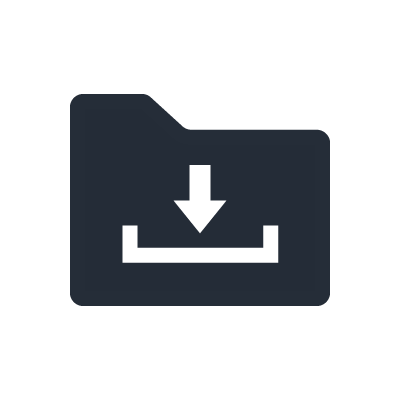Xeno Behind Stories
時空を超え、受け継がれる情熱 — Xenoシリーズトランペット開発ストーリー
第3章Xenoシリーズ誕生
このニューカスタムトランペット発売に先立つ1978年、社内では当時のトレンドをとらえ、多くのプレイヤーのニーズに応えるための「ヘビーモデル開発プロジェクト」が立ち上がろうとしていたが、当時、アトリエ東京にいた川崎の元にロサンゼルス・フィルハーモニックの首席奏者トーマス・スティーブンス氏から願ってもない依頼が舞い込んできた。「愛用の(他社製)トランペットが事故に遭い、復元を求めたが満足できない。ヤマハに作ってほしい」というものだ。実は、多くのプレイヤーが使っていたメーカーから、それに代わる楽器をヤマハに求めるプレイヤーも多くなっていた
スティーブンス氏の要求を満たすことは、川崎らプロジェクトメンバーにとって他社を研究するまたとない機会であった。細部にわたる寸法の計測や材料分析を行い、日本で入手できない材料は米国から輸入するなどあらゆる方策を探った。ヤマハが管楽器づくりを教わったシルキー氏の設計思想とは相いれない要素を解明するのには相当の時間がかかり、川崎は1983年に本社設計課に戻った後も、今岡、試作室の鈴木正男、入れ替わりでアトリエ東京に赴任した岡部と共に研究を続けた。ベルだけでも何百本作っただろうか。金属の加工法やベル成形後の熱処理方法を手探りで試すうちに、音の響きに影響する重要な発見をすることもあった。
試作品をスティーブンス氏に届け、その評価を受けることを繰り返し、10年もの歳月を経た1988年、遂に氏に満足してもらえるトランペットが完成した。この時には、「ようやくできたね」という氏の言葉と共に、ロサンゼルス・フィルのセクション全員がヤマハトランペットに切り替えるという“ご褒美”も付いてきた。開発者の情熱が実を結んだ瞬間であった。

(左)ようやく完成した楽器を手に喜びを露あらわにしたトーマス・スティーブンス氏(1988年撮影)
(右)その後30年に渡りヤマハを愛用し続けた(2018年撮影)
この間、蓄積したノウハウを反映し、Xenoの前身となるヘビーモデルYTR-8335Hを国内限定で発売した。1986年にヤマハが初めて支柱を二本付けて発売したYTR-8335Hは、目指していた“重く、しっかりした音”の実現には成功したが、それと引き換えに、長時間吹くとプレイヤーが「きつい」と感じる問題を生み出した。この「きつさ」を理由に、ヤマハから離れるプレイヤーも出始め、開発陣はもどかしい思いを抱きながら改善策を練り始める。
そこで、営業的にもインパクトが期待できるニューヨークのプレイヤーの協力を仰ぎ、開発を急ぐことになった。スティーブンス氏と同様に、老舗メーカー製に代わる楽器を探していたニューヨーク・フィルハーモニックのフィル・スミス氏や、メトロポリタン歌劇場管弦楽団のマーク・グールド氏である。同時に、川崎は米国に再度駐在し、設立されたばかりのニューヨークのアトリエ「ヤマハコミュニケーションセンターNYC(YCC)」で次期モデルの発売に向けて動き始めた。
この時の開発チームメンバーは、YCCの川崎と東京・ドイツのアトリエに駐在していた今岡・岡部、鈴木、そして今岡の後任として1987年に本社の設計課に配属された庭田俊一 である。彼らは支柱だけでなく、プレイヤーに違和感を覚えさせる数々の原因を探り、それらを一つひとつ解決していった。評価においては、欧米日の多くのプレイヤーに何度も試奏してもらった。彼らの水準をクリアしたという確かな手応えを感じた時、ようやく、新モデルの発売が決まったのである。

YCCでXenoの最終評価を行うジャズ奏者のランディ・ブレッカー氏(1988年撮影)
満を持して新モデルを送り出すに当たり、営業からは「フラッグシップにふさわしい愛称を付けてほしい」というリクエストがあった。自分たちの情熱の軌跡を示す良い言葉はないかと、英字辞書をAから順に辿たどっていた川崎は、辞書が終わりに近づいた頃、ようやく一つの言葉に目を留めた。「Xeno」。“外来の”という意味を持つこの言葉ほど、米国を中心とした海外プレイヤーとの二人三脚の挑戦を的確に表す言葉はないだろう。1990年、ヤマハ管楽器で初めて、作り手の思いを愛称に込めたXenoシリーズが誕生した。
このように、Xeno誕生の背景には設計、プレイヤー、試作・生産、アトリエの4者が効果的に連携するユニークな仕組みが存在した。他のメーカーでは、1人の担当者が4つの役割を全て担っていたが、ヤマハはそれらを分担制にし、設計担当とアトリエ担当を数年ごとにローテーションさせる仕組みを生み出したのだ。
製品と向き合う設計とアトリエで奏者の要望を聞くアーティストリレーション、両方の仕事を経験することで、開発者は管楽器製作の本質を理解する。このような手法の開発こそが、Xenoシリーズで結実したヤマハ管楽器製作のイノベーションであった。

Xeno YTR-8335U(S)YTR-8335U(S)のカタログ表紙。