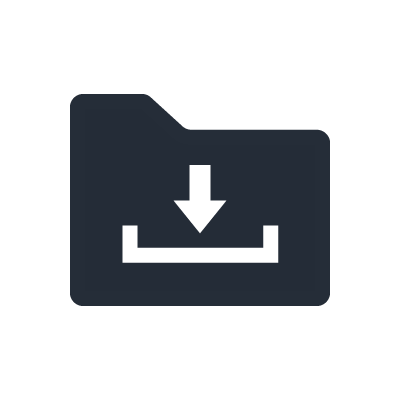Xeno Behind Stories
時空を超え、受け継がれる情熱 — Xenoシリーズトランペット開発ストーリー
第4章現地に根差した開発

ボブ・マローン
だが、このローテーションにも一つ問題があった。担当者は数年で帰国するため、せっかく築いたプレイヤーとの関係が途切れてしまうのだ。言葉の壁による限界もある。そこで、川崎はロサンゼルス郊外の金管技術者、ボブ・マローンにアプローチすることにした。ボブは高い修理技術を持ち、彼が開発した「マローンパイプ」(リードパイプ)は多くのプレイヤーの心を掴つかんでいた。
1988年、ボブの工房を訪れた川崎は、プレイヤーの要望に誠実に応えようとするボブの姿勢に共感を覚えた。ボブの方も「プレイヤーのためにベストを尽くす」という川崎らの思いに共感し、ヤマハからのテクニカル・パートナー契約の申し出を快く引き受けた。2001年、ボブは他社のオファーを断ってヤマハ・コーポレーション・オブ・アメリカの社員となる。そして、これが大きな転機となった。

トーマス・ルービッツ
一方、欧州では1991年、金管楽器製作のマイスター資格*²を持つトーマス・ルービッツがヤマハのアトリエに加わった。他メーカーで製作の経験を積んでいたトーマスは、ヤマハ・ヨーロッパ(現ヤマハ・ミュージック・ヨーロッパ)が開発とアーティスト対応の担当を募集していると知り、即座に応募してきたのである。

庭田俊一
こうして2001年、万全の態勢で次のモデルの開発がスタートした。初代の発売から10年が経ち、Xenoは一定の評価を得ていたものの、多くのトップ奏者から選ばれるレベルには至っていなかった。そこで、世界中の一流オーケストラ奏者が満足する最高の楽器を作るというプロジェクトが始まる。ボブは入社当初より「トップ奏者を協力者に迎え、Xenoの設計を一から見直したい」という熱い思いを持っており、シカゴ交響楽団のジョン・ハグストロム氏に協力を求めた。トランペットへの情熱にあふれ、楽器へのこだわりが強いハグストロム氏こそ、最良の協力者だと考えたのだ。ここからハグストロム氏とボブ、トーマス、庭田らによる新たな挑戦が始まった
庭田は学生時代、楽器修理のために訪れた銀座のアトリエで、白衣を着てトランペットを扱っていた岡部に憧れてヤマハに入社した。「無色透明」「良くも悪くも癖がない」と言われるヤマハのイメージを覆し、トッププレイヤーに選ばれる楽器を作りたいと情熱を燃やしていた。しかし、その取り組みは苦戦続きであった。
そんな庭田に、「ハグストロム氏が納得する楽器を何としても作りたい」と意気込むボブから毎日のように厳しい要求が届いた。最難関は、銘器と呼ばれるトランペットのベルに採用されていた「フレンチビード*³」の製作。「深みのある温かい音を生み出すにはフレンチビードが不可欠」と主張するボブに、「量産は無理だ」と最初は断った庭田だったが、結局はボブの熱意に負けた。技術者として「できない」で終わってしまうのは悔しく、試作室の鈴木に頼み込み、フレンチビードの製作に挑むことにした。だが、どんなに時間をかけても、 成功するのは10本中せいぜい2本。量産化の壁は高く、試作室や生産技術、生産などプロジェクトに携わるあらゆる部門の力を結集し、2004年にようやく商品化にこぎ着けることができた。
こうして生まれた「Xeno Artist Model シカゴシリーズ」は、トッププレイヤーからかつてない高い評価を受けた。中でも、フレンチビード採用とその量産化は画期的で、業界に大きな衝撃を与えた。「簡単なことは何一つなかったが、チームがハグストロム氏の思いに応えようと一つになった」とボブは言う。
シカゴシリーズに続き、2006年には「Xeno Artist Model ニューヨークシリーズ」を発売。庭田やボブと連携し、欧州でプレイヤー対応を担ってきたトーマスは「オーケストラ、ビッグバンド、ジャズやポップスなど、どんなジャンルのトッププレイヤーにもアプローチできる。こんなメーカーは世界中を探してもヤマハ以外にはない」と言い切る。

ジョン・ハグストローム(右)がプロトタイプをテストする様子を見るボブ・マローン
*2 マイスター資格:ドイツの国家技能認定制度「マイスター制度」で与えられる資格。管楽器製作の場合、実務経験に加え、法律や楽器製作実技など4科目の試験に合格すると取得できる
*3 フレンチビード:真円の針金の輪(縁輪)を入れてカーリングする一般的な工法に対し、かまぼこ型の縁輪を入れ、 その形状に合わせてカーリングする高度な工法