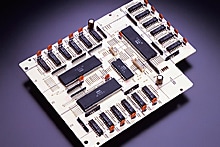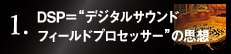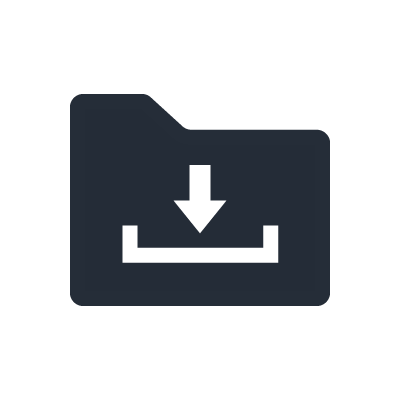エジソンによる蓄音機の発明から百数十年。ロウ管録音からデジタル・マルチチャンネルへと至るオーディオ再生技術の進化は、「より忠実な音を、いつでも好きなときに体験したい」という夢へ近づくための長い道程でした。
周波数特性やS/N、歪率といった再生信号の特性的な忠実度において、現代のデジタルオーディオはひとつの到達点に達したと見ることができます。かつてアナログオーディオで感じた、再生レンジやノイズレベルに対する物足りなさも、もはや過去のものとなりました。しかし、家庭のオーディオシステムで再生される音の多くは、私たちがコンサートホールやライブハウスで実際に体験する迫力や感動と比べて、未だ隔たりがあるのも事実です。
その大きな理由のひとつに、音を聴く空間の「音場」の違いが挙げられます。「音場」とは、ある空間が本来持っている音の響きかたを指す言葉ですが、空間の広さも構造も決定的に違う一般家庭とコンサートホールとではその性質が大きく異なるため、仮にそれぞれの場所で同じ音源の音を聴いたとしても、結果としてリスナーの耳にはまったく違う音が届くことになります。いかに素晴らしいプログラムソースや再生装置を用意したとしても、コンサートホールやライブハウスで味わう迫力と感動を家庭で楽しむことが困難であった理由はここにありました。
この「音場」の違いを克服するためにヤマハが世界に先駆けて提唱したのが、本物のコンサートホールやライブハウスさながらの「音場」を家庭の再生装置で忠実に再現すること。すなわち「音場を創る」という考え方です。『リスニングルームをコンサートホールに』を合い言葉に登場した世界初のデジタル・サウンドフィールド・プロセッサー「DSP-1」(1986年)は、この考え方を市販AV機器として初めて実践した記念すべき製品でした。
「DSP-1」の開発においてもっとも重要なエポックは、世界中の著名なコンサートホールやライブハウスを巡って生の音場データを収集し、それをデジタル化して機器内の専用LSIに直接組み込むという前代未聞の手法を確立したことです。以来、その手法はヤマハホームシアターの根幹をなす技術として進化を重ね、今日の「シネマDSP」へと受け継がれていくことになります。私たちヤマハにとっての「DSP」とは、一般用語としての「デジタル・サウンド・プロセッサー」あるいは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略ではなく「デジタル・サウンドフィールド・プロセシング」、つまり「音場を創る(=音場創生)」という思想そのものを象徴する言葉なのです。
それでは、なぜヤマハが「音場創生」という考え方を具現化し、他の追随を許さない独創技術として今日まで育てることができたのでしょう。そのルーツは、ヤマハが取り組んできた建築音響の研究にありました。世界的な楽器メーカーでもあるヤマハにとって、それは製造した楽器の音が空間でどのように響くのか、すなわち楽器の性能を評価するうえで欠かせない研究分野です。この経験をもとに1974年からはコンサートホールの設計を開始し、「DSP-1」の発売時点で既に日本国内だけでも82件のホール設計を行っていました。「DSP-1」に活かされた生の音場データも、もともとは完成後のホールの音を施主にプレゼンテーションする音場再現システムの開発の一環として収集を開始したものだったのです。現在この研究成果は、音響支援システム「AFC」(Active Field Control、建築音響に関わる室内の主要な聴感印象を電気音響の支援により自然に変化させることのできるシステム)として結実しています。
いっぽう1971年には、エレクトーンやシンセサイザーに欠かせない、音の質と表現力にこだわった半導体の自社開発にも着手。「DSP-1」の心臓部にあたるLSI群も、設計から製造まですべてヤマハ・オリジナルであったことは言うまでもありません。こうした比類のない技術的背景と、楽器やオーディオ機器の分野で長年にわたり培われてきた音づくりの理念との融合によって、それまで誰も踏み入れることのできなかった「音場創生」の新領域は拓かれたのでした。
生の音を知り、その音が解き放たれる空間の響きを知り、理念を具現化するために必要な技術的背景を持つヤマハだからこそ到達できた「音場創生」の領域。これこそが、すべての再生音に真の迫力と感動を与える確かな道であると、私たちヤマハは信じています。