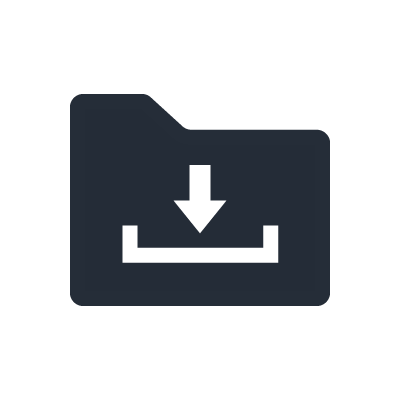【第0章】プロローグ:シンセサイザー開発前夜

ヤマハは、1975年1月にシンセサイザー音源方式を搭載したエレクトーン「GX-1」をリリースし、ヤマハシンセサイザーの2号機として、その名を歴史に刻みました。その容姿はフラッグシップのエレクトーン、まさにドリームマシンといえるものでした。「GX-1」の前身となる試作機「GX-707」は、1973年には完成していたことは第1章でも触れていますが、最高の演奏表現を求めたドリームマシンの切り口で見てみると、GX完成前に壮大なストーリーがありました。現代のシンセサイザーにもつながるさまざまな技術がはるか以前から生まれていたのです。この章では、シンセサイザー開発前夜として、エレクトーンにまつわるヤマハの挑戦に迫ります。
伝説の「EX-21」


ヤマハがオールトランジスタ化の電子オルガン1号機「D-1」を「エレクトーン」と命名し世に送り出したのが1959年。その後、毎年のように新作エレクトーンを発表していた1960年代中ごろ、「日本楽器製造(株)の技術を結集した最高のエレクトーン(世界一の電子楽器)を作ろう!」という川上源一氏(当時の日本楽器社長)の掛け声のもと、4台の試作機が製造されました。これが1968年に開発、翌年には海外でも発表された「EX-21」です。「EX-21」は、同年発売のヤマハ初のステージモデル「EX-42」を市販化するための試作モデルでもあったのですが、1970年の大阪万国博覧会への出品に向けて、開発と評価が繰り返し行われていきました。「EX-21」は、本体・ペダル・ベンチが一体式の鋳物でできており、4台の試作機が完成するまでにいくつもの試作機が割れて壊れてしまったそうです。
また、音源方式は、分周発振方式と独立発振方式の二つからなるハイブリッド方式が採用されましたが、音源回路が本体内には収まらず、音源ラックのような形で外部に設置され、本体と音源ラックが太い専用ケーブルで接続されていました。割れやすい鋳物成型の本体に加え、本体と音源部とトーンキャビネットの総重量は800kgともいわれ、移動には困難を伴いました。しかしながら、1969年5月からラスベガスの楽器ショーを起点に「EX-21」を使用したワールドツアーを敢行。沖浩一氏、桐野義文氏の2名により演奏され、各地でその音色の素晴らしさと表現力の高さに賞賛が集まりました。

ワールドツアー演奏者の一人である桐野氏によると、「EX-21」が自宅に2週間預けられたことがあったそうで、その際に手元にあるレジストボタン(音色プリセットを切り換えるボタン)を押すと、専用ケーブルでつながったまま別の部屋に置いてある音源部から「ガシャガシャガシャ」とものすごい音が鳴り響いたそうです。この音は音源部にあるリレースイッチの音だそうで、「EX-21」が機械式で音色を切り替えていたことが伺えます。一方、その外観は本当に未来的で、まるで宇宙の楽器を彷彿とさせるものだったとも桐野氏は語っています。


デザイン、重量、音色切り替え機構も壮大ですが、1台あたりの製作費も桁外れで、「EX-21」は当時の価格で約2千万円、現在の価値に換算すると約1億円に相当するものでした。また「EX-21」というネーミングは、エレクトーンの最高機種E型の発展形としてXを追加、さらに40年後には訪れる21世紀に込めた想いから命名したと言われています。「EX-21」は当時の最新技術とアイデアを余すこと無く取り入れた最高のエレクトーンであり、「GX-1」に代表されるドリームマシンの原点ともいえます。
独立発振方式と分周方式
シンセサイザーでは、音の基となる発振器(オシレーター)の数と同時発音数が密接に関わっており、例えば4音ポリフォニックであれば4つの発振器が別々の周波数を出すことで和音を奏でることができます。しかし初期のヤマハエレクトーンでは、すべての鍵盤に発振器の音を割り振ることで全鍵ポリフォニックという仕様を実現しており、この方式には独立発振方式と分周方式という2種類の方式があります。
独立発振方式とは、すべての鍵盤ごとに発振器を取り付けて和音を奏でるもので、例えば40鍵の鍵盤があれば40個の発振器を必要とし、莫大なコストがかかるものでした。これに対して、分周方式とは一番高い周波数の発振器を1オクターブ分用意し、この発振器の音を分周器と呼ばれる回路で整数分の1の周波数に変換し、1オクターブ下、2オクターブ下・・・(周波数が半分になると音程は1オクターブ下がります)といった音程を作り出すものです。この方式だと12音分の発振器を用意すればすべての音程を奏でることが可能になります。


初期のエレクトーンでは、どちらの方式も常時発振方式(電源を入れたら発振器が常に音を出している状態)で作られており、鍵盤を押すとアンプの方に音が流れる仕組みなのですが、この方式だと演奏していないときにも発振器の音が漏れることがあり、エンジニアによる調整が不可欠でした。
「EX-21」は独立発振方式を採用した「F-1」(1964年、販売価格220万円)と、分周発振方式のE-1(1962年、販売価格64万円)の2つの音源方式を併せ持ち、ハイブリッド方式を採っていたまさにドリームマシンでした。

初代ステージモデル「EX-42」

「EX-21」の後継機ともいえる「EX-42」は、市販化を念頭に、音源を分周発振方式に絞って開発され、本体重量も180kgまでに収められました。
注目すべきは音色で、オルガンフルート(いわゆるパイプオルガンの音色)の16~1フィートまでの9列のトーンレバーに加え、ブラス系、ストリングス系などの音色も装備、さらにはパーカッション系や、ピアノ、ハープシコードといった減衰系の楽器音も搭載していました。さらにはウェーブモーションと呼ばれる上鍵盤の他のトーンレバーと音程をずらすことができる音色を備えており、この音色を他の音色に重ねると、音に独特のうねりが生じる効果を得ることができます。まさに、シンセサイザーの先駆けともいる機能です。なお、一部の音色だけでしたが、タッチコントロール(タッチレスポンス)にも対応しており、開発へのこだわりが垣間見えます。また、上鍵盤、下鍵盤、足鍵盤にはカプラーというトーンレバーが装備されており、それぞれの鍵盤に用意されている音色を、別の鍵盤に混ぜる(重ねる)という、現代の「レイヤー」に相当する機能も備えていました。
「EX-21」でも搭載されたソロ鍵盤およびポルタメント鍵盤(リボンコントローラー)も装備されおり、ソロ鍵盤ではタッチコントロール(横方向)でビブラート効果やミュートがかけられる単音の音色を4種類、和音が鳴らせるチャイム、ビブラフォン、ベルリラの3種の音色が用意されていました。ソロ鍵盤の左側のポルタメント鍵盤は、いわばそれ自身で発音の可能なリボンコントローラーで、6種類の音色が用意されており、効果音や滑らかな音程変化を表現しながら演奏することができます。さらに、オートミュートやリバーブ効果を加える機能も搭載されており、特にリバーブをかけた状態でポルタメント鍵盤を演奏すると、宇宙的というか幻想的なサウンドを創出することができます。このポルタメント鍵盤は、後の「GX-1」や「CS80」にも搭載されています。
また、エレクトーン初となる13種類のオートリズム機能も搭載し、初代エレクトーンから装備されている4個のボタンパーカッションも装備。現在でいうところのレジストレーションメモリーも上下鍵盤の間に4つ搭載(上・下・足鍵盤の設定をフルで記憶できるのは一つ)し、足でも切り替えができるように足ピストンも4つ備えられています。もちろん、鍵盤間のボタンと連動しており、まさに現在のシーンメモリー機能にあたる機能が搭載されています。


また、引き出し式となっているプリセットボードには、ソロ鍵盤、上鍵盤、下鍵盤、足鍵盤の4種類の鍵盤(音色)別に、ピッチをコントロールできるツマミが用意され、鍵盤間のピッチを微妙にずらすことで、音色の独特のうねり効果が出せるようになっていました(※もちろんコンサートピッチの調整にも使用可能です)。
音源方式こそ分周発振方式でしたが、「EX-42」の備える音作り、音色表現のための機能は半世紀以上も前とは思えない画期的なものであり、このモデルがあったからこそ、「GX-1」が誕生したと言っても過言ではありません。
最後に、当時のカタログに書かれていた「EX-42に込めた想い」を紹介します。
『作曲家、演奏家は時代に先駆けて、それぞれの表現をしたい・・・と常に思うものです。楽器もそうした要求に応えて進歩します。また、その逆の場合もあるでしょう。いずれにしても、新しい楽器の誕生は、音楽の歴史の1ページに新しい表現の世界をプラスします。ヤマハエレクトーン「EX-42」も、こうした新しい表現の世界を拓く、意欲的な楽器です。高度のエレクトロニクス技術と、世界最高水準の楽器創りの技術が見事に結晶、楽器の可能性と表現のジャンルを大巾に拡げました。作曲家やプレイヤーの要求にフルに応えます、その活躍の範囲も、巨大なコンサートホール、放送局、レストラン、録音スタジオ、テレビドラマの伴奏音楽、コマーシャルフィルムの音楽、電子音楽・・・と、まさに多彩です。ヤマハの自信作EX-42に、どうぞご期待ください。』
「GX-1」が拓く新しい音楽表現


「EX-21/EX-42」の完成後、よりナチュラルな音を追求するために、次世代のエレクトーン開発が始まりました。その一つが「GX-1」として結晶します。
「GX-1」の前身となる試作モデル「GX-707」は1973年には完成し、NAMM ShowやMusikmesse、日本国内での各種催しでの演奏会を通じてその評価を確立し、改良されていくことで「GX-1」市販化への確信を固めていきます。


当時、「GX-1」は「生きた音」というテーマを持って設計が進められました。「GX-1」より前のエレクトーンは、持続音の波形を作り出すことによって音色が合成されていましたが、「GX-1」は集団電圧制御方式(いわゆるポリフォニックアナログシンセサイザー方式)を採用することにより、時間の経過に伴う音色の変化を表現できるようにしました。
その結果として、一つひとつの音が艶やかに輝き、生き生きとしたハーモニーが響きわたるようになるのです。「GX-1」には、従来のエレクトーンにあったトーンレバーが無く、あらかじめ音の変化やバランスを記録したプリセット音色を本体にセットし、奏者は曲想にあった音色を、トーンセレクターを推すことで選択する方式になっています。現在のプリセット音色と同じ形式と言えます。
従来のエレクトーンにはない、「GX-1」固有の特徴を挙げると・・・
1. 音源にアナログシンセサイザー方式を採用
2. 合計で18音ポリフォニック(上鍵盤8+下鍵盤8+ソロ鍵盤1+足鍵盤1)
3. トーンモジュールによりプリセット音色を備え、音色エディットも可能
4. ピッチベンド効果、サステイン効果、レゾナンス、リバーブなどの音楽表現機能
5. タッチコントロール(タッチレスポンス)をより強化
といった感じになります。

「GX-1」がシンセサイザーと呼ばれる理由としては、音源部にVCO/VCF/VCAからなるアナログシンセサイザーを搭載し、音色作りの要である時変動(時間の経過と共に音色が変化すること)をコントロールできたことが挙げられます。意外と知られていませんが、本体だけでは、時変動を伴う音作りを行うのが難しく、視覚的に音作りをするためにはTone Boardと呼ばれる専用のEditorが必要でした。
また、プリセット音色は初期ロットの第一基準(通称:黒)と後期型の第二基準(通称:赤)の2種類があります。2018年にオープンしたヤマハの企業博物館「イノベーションロード」にも「GX-1」が展示されていますので、是非ご覧いただきたいところです。ここで展示されている「GX-1」は、電動椅子を備え前後・左右の調整が可能ですが、「GX-1」は本来固定椅子が標準装備でした。電動椅子タイプの「GX-1」は、前述の川上源一社長が、「子どもでも支障なく演奏できるように」と、エレクトーンコンクールや日本国内の音楽教室備品を対象に作らせた限定品なのです。

PASS(Pulse Analog Synthesis System)音源搭載の「EX-1/EX-2」

「GX-1」とほぼ同時期に開発が進行していたのが、PASS(Pulse Analog Synthesis System)音源です。コンサート・シアターモデル「GX-1」に搭載されたアナログシンセサイザーは、システム規模が大きく、サイズ・コスト的にも普及モデルには搭載できないことが分かっていたため、高い音色クオリティと表現力を保ちつつ、当時技術革新が進んでいたデジタルの長所を取り入れた新開発の音源開発が急ピッチで進んでいました。アナログとデジタルのハイブリッド方式のPASS音源は、1977年発売の「EX-1/EX-2」に初めて搭載されます。PASS音源では「GX-1」から続く「生きた音」に加え、「豊かな響き」を実現するために、フルート音源(いわゆるオルガンサウンドの音源)とオーケストラ音源(バイオリンやピアノのように音の時間的変化が重要な音色)の2つの音源を搭載しており、それらを重ねて音作りを行なうことができます。さらにオーケストラ系音色のオクターブをずらす機能なども搭載しており、より柔軟な音作りを可能にしています。また、フルート音源、オーケストラ音源どちらも2系統の音源を重ねて厚みを生み出すセレステ効果が得られるようになっており、より重厚で豊かな音色が出せるようになっています。さらに、シンセサイザー回路の主要部分である「Filter」も搭載され、シンセ的な音色アプローチもできるようになっています。
これらは新開発の音源LSI搭載によるもので、より小型、高機能、低コストで、商品の生産が可能になりました。このPASS音源は主にエレクトーンに搭載され、1978年に発売された新Cシリーズは、エレクトーン史の中で最大のセールスレコードを記録しました。
後述の第2章でも触れていますが、この頃、一方ではFM音源の開発も進んでおり、1981年以降はデジタル(FM)化が急速に進み、結果としてPASS音源は短命で終わることとなっていきます。しかしながら、PASS音源の技術は、1979年から1981年に発売されたシンセサイザーカテゴリの「SKシリーズ」に生かされることとなり、PASS音源の時代に欠かせなかった「Ensemble/Symphonicエフェクト」(3相の”BBDアナログコーラスエフェクト”)も「SKシリーズ」「GS1」「CEシリーズ」に搭載されていきます。

ヤマハは当初より、鍵盤演奏者向けのポリフォニックで発音する楽器を念頭に開発に取り組んでいましたが、音源部だけなく、リアルな演奏性をもたらす鍵盤、リボンコントローラーによる表現、音色メモリなど現在のモデルにもつながる技術が1960年代から存在していました。いわゆる純然たる「アナログシンセサイザー」としては、1974年の「SY-1」の完成を待つ必要がありましたが、時変動(時間軸に沿って音色変化をコントロールする)以外の点においては、すでに1960年代より既存の楽器音の再現にとらわれないシンセサイザー的な音表現の試みが、技術の面からも、演奏の面からも取り組まれていたのです。あらためて先人達の果敢な挑戦に深く敬意を表したいと思います。
1950~1980年代にかけての音源方式の遷移
分周発振方式からAWM音源まで、最先端の音源が初搭載されたモデルは全てエレクトーンであった(シンセサイザーのように音づくりができたかどうかは別として)。