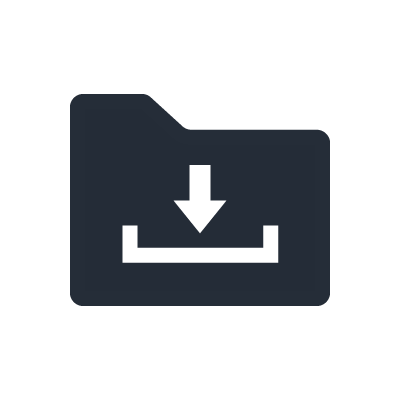【第1章】ヤマハシンセサイザーの原点
それはエレクトーンの進化形から始まった

世界的には1920年頃から電子楽器の原型ともいうべき技術や商品が出始めていますが、ポピュラー音楽と密接に発展した電子楽器は電子オルガンであるといって良いでしょう。ヤマハの電子オルガンの商品名(商標)であるエレクトーン®の1号機「D-1」が発売されたのが1959年。すでに真空管を使用した電子オルガンは発売されていましたが、この「D-1」はオールトランジスターのモジュールを使用した画期的な電子オルガンでした。音色合成という点においてはシンセサイザーの原型を持っていたエレクトーンですが、当時の社長がエレクトーンの音を「音楽オモチャ」と表現したというほど生楽器の表現力とはほど遠いもので、鍵盤を押すとなり始め、離すと「プツッ」と途切れる機械的なサウンドでした。
実はこの当時のさまざまな研究成果によって、楽器の音として認識できる最大の要素は、音の時変動(時間的変化)であるということがすでに把握されていました。この時変動とは、例えばピアノの音であれば鍵盤を弾いた瞬間に出るのは弦を叩いたときの複雑な倍音を含む音ですが、音が伸びている部分では次第に正弦波のような倍音成分の少ない音に変化していき、この変化がピアノの音として認識できる最大の特徴であるのです。生楽器のように自然な音を電子楽器で表現するためには、こういった時間的変化を再現する技術の開発が不可欠でした。実はヤマハのシンセサイザー開発の歴史は、まさにこの音の時変動から始まっており、エレクトーンの音をさらに素晴らしい音にするという挑戦からきているのです。
アナログシンセにデジタル技術?
初期のエレクトーンに搭載されていた音源システムでは、鍵盤それぞれに電子回路による発振器(今でいう音源)が搭載されており、鍵盤を弾くとその鍵盤につながっている発振器が発音するという非常にシンプルな機構でした。鍵盤が40鍵あるなら40個の発振器が存在し、鍵盤と発振器はスイッチとブザーのような関係で作られていたのです。実際にはオクターブ違いの音程を出すのに分周器という周波数を整数分の1にする装置を使用するので、最高音を奏でる12音分の発振器があればよいことになります(分周方式)。しかし、前述のような時変動を搭載した新しい回路を搭載するとなると、当時の技術で鍵盤の数だけの回路を搭載したのでは莫大なコストがかかるだけで無く、大きさも膨大なものになってしまうので現実的ではありませんでした。


そこで、限られた数の回路を有効に使う技術が必要となります。例えば回路が8個あったとすれば、最大8音ポリフォニック(8和音)を同時に発音することができるわけですが、鍵盤が仮に36鍵(3オクターブ分)あったとすると、そのうちのどの鍵盤を押した時にどの回路が鳴るのかという制御が必要です。そこで、押されている鍵盤の数や順序などを認識して効率よく回路に割り振る装置を開発しました。
当時「キーアサイナー」と呼ばれていたこの装置は、現在のDVA(ダイナミックボイスアロケーション)の原型ともいうべき技術で、当時の開発者の話ではこういった機能がすでに世に出ていて模倣したわけでは無く、ヤマハが独自に実装したものです。実はこの「キーアサイナー」という機構は、音源がアナログである1970年代前半においてすでにデジタル回路で実現されており、アナログシンセの時代にデジタル技術が採り入れられていたことになります。
「SY-1」の登場

音の時変動を搭載した音源に「キーアサイナー」を搭載するという2つの大きな壁を乗り越え、1973年にエレクトーンとして発売された「GX-1」の前身ともいうべき「GX-707」(開発コードネーム)という集団電圧制御による試作機が完成します。「GX-707」の見た目はエレクトーンですが、その中身は8音ポリフォニックシンセサイザーそのものでした(上下段の鍵盤がそれぞれ8音ポリフォニックで、ソロ鍵盤、足鍵盤はモノフォニック)。しかし、エレクトーンの最高機種としてコンサートステージで使用するシアターモデルという位置づけの試作機だったため、重さ300kgを越える筐体に加えて本体とは別の音色エディットボードを持った構造など、一般に販売するのは難しいまだ特別な存在の楽器でした。そこで「GX-707」の素晴らしい表現力を持った音源部分を一音分だけ取り出し、既存のエレクトーンのソロパート用キーボードとして商品化したものが、1974年に発売されたヤマハシンセサイザー第1号機のモノフォニックシンセサイザー「SY-1」というモデルです。一般的にアナログシンセサイザーはモノフォニックからポリフォニックに進化するのが自然な流れのように感じますが、ポリフォニックからモノフォニックを商品化するあたりもヤマハらしい独創的な部分といえるでしょう。

「SY-1」にはキーアサイナーこそ搭載されてはいませんが、音の時変動をもたらすエンベロープジェネレーターを搭載しています。シンセサイザーのエンベロープジェネレーターはADSRという4つの要素で構成されているものが一般的です。Aはアタックタイムと呼ばれ鍵盤を押したときの音の立ち上がり時間を調整します。Dはディケイタイムと呼ばれ、鍵盤を押し続けているときに次に説明するサステインレベルに落ち着くまでの時間を設定できます。Sはサステインレベルと呼ばれ、鍵盤を押し続けているときに最終的に落ち着く音量のことで、最後のRはリリースタイムと呼ばれており、鍵盤を離してから音が消えるまでの時間をコントロールします。
このようにADSRのコントロールツマミを用いて鍵盤を押してから離すまでの音の時間的変化を調整するのです。しかし、「SY-1」のコントロールノブを見ていただくと判るとおり、モジュラー型のMoogやMini MoogのようにAmpやFilterのエンベロープをADSRでコントロールするようなツマミが存在せず、AttackとSustainというスライダーでアンプのエンベロープを調整し、ATTACK BENDという機能を使用して音の立ち上がり部分のPitchエンベロープとFilterのエンベロープを調整するという独特のコントロール機構を備えています。
「SY-1」にはフルート、ギター、ピアノなど、それぞれの楽器音を再現するためのエンベロープがプリセットされており、音色のレバーをONにするだけでエンベロープを切り替えられるようになっていました。現在はプリセットをされた音色を呼びだすといった考え方は一般的ですが、アナログシンセ1号機からプリセット機能を持ったシンセを世の中に投入するあたりも斬新さが伺えます。
さらに「SY-1」にはもう一つ画期的な機能が搭載されています。これはタッチコントロールという機能で、現代風に言い換えるとベロシティー機能が搭載されているということです。それまでの電子オルガンではエクスプレッションペダル(ボリュームペダル)を使用して演奏中の抑揚表現をしていましたが、鍵盤を弾く強さで音色変化をコントロールしようという試みが行われ、さまざまな試作が行われました。最終的に鍵盤が押されていない状態の時と押し込まれたときとの時間差を検出してタッチの強さを計測する技術を開発し、これを「SY-1」に搭載しています。
Combo Synthesizer「CSシリーズ」への進化

「SY-1」発売の翌年1975年にはコンサートモデルのエレクトーンとして「GX-1」を発売していますが、同じ技術をエレクトーンとは異なる商品カテゴリで展開したものがコンボシンセサイザーの「CSシリーズ」です。
それまでトランジスタの組み合わせで設計されていた音源やコントロール部分をIC化することで大幅な軽量化と可搬性を実現したのも「CSシリーズ」の特徴です。用途の違いや足鍵盤などの構成の違いもありますが、「GX-1」が300Kg以上、700万円という商品だったのに対し、「CSシリーズ」の最高級モデル「CS-80」では82Kg、128万円というミュージシャン個人が手に入れて持ち運べるものになりました。


この当時のヤマハのシンセサイザーには2つの大きな特徴があります。まず一つ目は音色をメモリーする機能です。現代ではコンピューターでファイルを保存するかのごとく作成した音色をメモリーできるのが当たり前ですが、RAMやROMといったものが存在しない時代には非常にアナログな手法でメモリーを行っていました。次の図は「CS-60」のサービスマニュアルという修理担当の人が扱う資料の1ページですが、(Tone Preset 1)Circuitと記載された部分に音色名と回路図、抵抗値が記されています。シンセサイザーの各ツマミは可変抵抗器という抵抗(電流や電圧を抑制する素子)でできているのですが、そのツマミの値に相当する抵抗値を固定値で埋め込んだもことを示しており、当時は作成した音色の抵抗値をこのように埋め込んだトーンボードと呼ばれる回路を使用していました。
「GX-1」などでは、このボードを物理的に入れ替えることで音色を切り替えており、アナログ版ROMカートリッジともいうべき音色の保存方式をすでに採用していたことになります。「CS-80」では、本体のコントロール素子と全く同じ数だけのメモリー用素子を4系統持っていて、自分で作成したツマミの位置と同じ状態をそこにメモ(同じことを再現しておく)することで、4種類のオリジナル音色を瞬時に切り替えられる機能を搭載していました。


もう一つの特徴は、IL、ALタイプのエンベロープジェネレーターです。IL、ALとはイニシャルレベル、アタックレベルのことで、一般的なADSRタイプのエンベロープジェネレーターと若干異なります。ADSRタイプのエンベロープジェネレーターの場合、アタックの前の音の出始めが0の基準値となります。これをフィルターにかけると音の出始めの音色がカットオフ周波数での設定値となりますが、アタックのピークの音色や音を伸ばした時の音色はカットオフ周波数での設定値にエンベロープジェネレーターの深さやサステインレベルの値を組み合わせたものとなります。複数の設定値が影響しあうため、音色の変化の調整には複雑な操作が必要でした。一方、IL、ALタイプでは音を伸ばした時の音色が、フィルターのカットオフ周波数での設定値となり、音の出始めとピークの音色はILと ALで独立して設定できるため、自由度の高い自然な効き具合に調整することができるのです。これはヤマハ独自の機構であり、開発者の音作りへのこだわりが伺えるポイントともいえるでしょう。

また、「CS-80」にはリボンコントローラーというポルタメントバー(音程を連続的に可変させる装置)や、鍵盤を押し込んだ時の強さを感知して音色を変化させるアフタータッチも搭載されており、現在ではポピュラーな機能が40年も前から考案され、実用化されていたことを考えると、ヤマハのシンセサイザー開発における技術力の高さをあらためて実感できます。
低価格化と小型化、そしてさらなる進化

1970年代後半にはモノフォニックで低価格の「CSシリーズ」を投入し、アマチュアにも手の届くシンセサイザーとして普及していきます。この当時ICの高集積化と低価格化が加速したことも受け、1978年に発売された「CS-5」では重さ7Kg、定価62,000円というモデルを実現しています。
こういった小型で低価格のモデルを開発する過程においても、現在のヤマハシンセサイザーに受け継がれている技術や仕様が確立されていきます。「CS-15D」に搭載されたホイール型のピッチベンドとモジュレーションホイールは、最新機種の「MONTAGE M」にも継承されているヤマハシンセサイザーの特徴的な仕様です。さらに1979年発売の「CS-20M」では音色のメモリーをデジタル化。1981年発売の「CS-70M」においてはアナログシンセで最大の難関ともいえるチューニングを自動化したオートチューン機能やマイコン内蔵のシーケンサー機能など、現在のシンセサイザーに限りなく近い機能を搭載しています。
さらに1982年に発売された「CS01」では、ミニ鍵盤、電池駆動、スピーカー内蔵、ショルダー用ストラップピンの装備など、エポックメイキングなシンセサイザーを開発しており、音源部分だけでなく利用されるスタイルにおいても新たな時代を切り開いていきます。
新たな音源開発へ意欲を…

このように1974年にスタートしたヤマハシンセサイザーの歴史ですが、実は1970年代から平行してさまざまな音源開発を進めていました。1980年代に大ブレークをするFM音源の研究や1977年にエレクトーン音源に採用されたデジタルとアナログのハイブリッドタイプのPASS音源などがこれに相当します。これらの音源を試聴した中で、当時、現実的に商品化できるレベルに仕上がっていたのが「SY-1」に搭載されたアナログシンセサイザー方式の音源だったということです。当時の技術者が数多くの高度な技術に非常に早い段階から注目し、開発を続けてきたという事実に改めて驚かされます。
しかし、エレクトーン1号機「D-1」発売後もその音質に対しては問題点も多く、どのようにしたら生楽器と同じような表現力を実現できるのかというのが大きなテーマになっていました。音色や音量の時間的変動もこのような取り組みから課題となったもので、こういった音へのこだわりを満足させるため、日夜研究と開発を続けてより良い音を求めていったそうです。日本の高度成長期の象徴と言えるのかもしれませんが、当時は「いくら使っても良いから世界一のものを作れ」と社長から指示されていたとのことです。こういった情熱とパワーを持ち、数々のオリジナル技術が生まれていった1970年代のヤマハシンセサイザー開発が、その後のシンセサイザーという楽器を発展させる大きなステップになったことは揺るぎない事実ではないでしょうか。