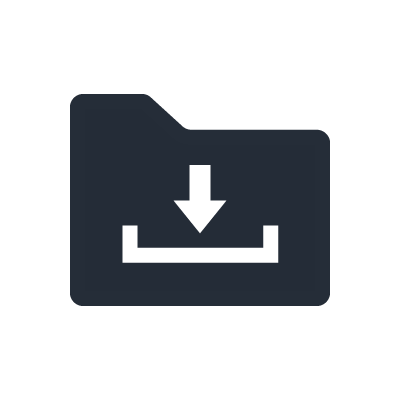【第2章】FM音源の登場と音楽制作時代の幕開け
半導体技術の躍進


1980年代に入ると、半導体を使用した電子回路が急速に普及し、それまでの技術では実現し得なかった電子機器が次々と具体化されていきます。当時LSI(大規模集積回路)という言葉が大学入試の試験に出題されたり、LSIを使った電子ゲームが発売されたりするなど、半導体技術の躍進はめざましいものでした。
この半導体技術の躍進によって商品化にたどり着くことができたのが、デジタル方式のFM音源です。もともとFM音源方式はアメリカのスタンフォード大学で開発されたもので、その可能性にいち早く目をつけたヤマハが1973年にライセンスに関して独占契約を結んでいます。

当初はエレクトーン®のデジタル化という命題のなかでFM音源の研究を進め、「SY-1」が発売された1974年にはすでにFM音源を搭載した試作機ができあがっていました。しかし、当時の半導体技術では多くのLSIが必要となり、大きさと機能の面で満足いくものが得られず、すぐに商品化することはできなかったのです。その後、半導体技術の躍進と共に満足のいく仕様を盛り込むことができるようになり、7年後の1981年4月にクラシックモデルのエレクトーン「F-70」、翌月にはステージタイプのキーボード「GS1」でFM音源が商品化されます。

1982年に発売されたTOTOの4枚目のアルバムでは、全編にわたって「GS1」のサウンドがフィーチャーされ、FM音源独特のアコースティック感のある金属系マレット・サウンドや重厚なブラス・サウンドを聞くことができました。特に、「Africa」は作者のデヴィッド・ペイチ(David Paich)が「GS1」のプリセット・サウンドに触発され、その即興(Improvisation)から作られたという逸話もあるほどです。

FM音源の最大の魅力は、エレクトリックピアノ、ブラス、グロッケンなどといった変化に富んだ複雑な倍音を含む音が非常にリアルに生み出せる点です。現在ではサンプリングという楽器音そのものを録音したものを利用する技術が主体ですので、さまざまな楽器の音がシンセサイザーから出るのはごく当たり前のことですが、当時のアナログシンセサイザーでは、ベル系とも呼ばれる金属系の音を奏でることが難しかったので、「GS1」のFMサウンドはとても衝撃的でした。

「GS1」はシンセサイザーのカテゴリに含められていなかったのですが、その理由の一つとして「GS1」は本体だけで音色エディットができないという点が挙げられます。本体に登録できる16音色を音色カードで入れ替えることはできるのですが、その音色を作成するには開発用の特別な音色プログラマー(写真)で行う必要があったのです。実はデジタルのシンセサイザーを商品にするにあたり、この音色エディットという部分も大きな壁であったのです。
ユーザーインターフェースという考え

アナログシンセでは音源回路そのものに搭載されている電子部品の数値(例えば抵抗値)を変更すると音色が変化するため、その数値を変更する部分に可変抵抗器を用いたツマミやスライダーを装備すれば音色編集が可能です。これらをどのように配置するかがシンセサイザー本体のデザインや大きさに直結していたわけですが、第1章でも紹介した「CS-80」でもすでに膨大なツマミが必要だったのに加え、パラメーターがさらに増えたデジタルシンセサイザーでは、すべてのパラメーターにツマミを設けるというのは現実的ではありません。
また、デジタルシンセサイザーは、コンピューターのソフトウエアのようにすべてプログラムで動作します。単に目的の音を出すだけならプログラムを組み込むだけでよいのですが、パラメーターを自由に可変できるようにするにはそれを考慮した音色編集のためのプログラムが必要となり、さらにパラメーターを入力するためのボタンやツマミなどを搭載する必要があります。コンピューターでいうところのキーボードやマウスに相当する部分と考えるとイメージが湧くかもしれません。
1980年といえばWindowsやMacが登場する前の時代で、キーボードで文字や数値をタイピングするユーザーインターフェースが主流でした。現在のようにグラフィカルな画面にマウスやタッチで簡単に入力できず、音を感覚的に扱いたい音楽家やコンピューターのプログラミングに長けていないユーザーに、わかりやすいインターフェースを提供するというのは、デジタルシンセにおける最大の難関だったといえるでしょう。
前述の「GS1」用音色プログラマーも、そこに至るまでにさまざまな経緯を経ています。「GS1」の前身にあたる「TRX」という試作機では写真のようなプログラマーを採用しており、スライダーボリュームを時間変化に対応して並べているのに加え、同時に複数のパラメーターを視覚的に編集できるようにしました。しかし、モーターフェーダーのような機構を持っているわけではないので、編集を行おうとする値をリアルタイムに表現することはできません。そこで写真のようなランプとボタンを組み合わせたプログラマーを用い、編集前のパラメーターを表示して確認しながら編集ができるという仕ようなども考案されました。
現在のシンセサイザーでは、ごく当たり前のようにシンセサイザー内のパラメーターに自由にアクセスして変更を行うことができるユーザーインターフェースが搭載されていますが、半導体やプログラムの技術が急激に変化する時代の中でさまざまなトライアンドエラーを繰り返し、クリエイティブに音作りができるユーザーインターフェースを模索していったのも、この時代の重要なシンセサイザー開発だったといえるでしょう。
音楽シーンを激変させた「DX7」の登場

FM音源の開発と音色をプログラミング(編集)するユーザーインターフェースの開発という大きな壁を乗り越え、「GS1」発売の2年後に伝説のFM音源シンセサイザー「DX7」が登場します。FM音源の心臓部とも言えるオペレーター(音を発生させたり音を変化させたりするための基礎となる部分)が「GS1」では4オペレーター仕様だったのに対し、「DX7」では6オペレーターに進化させてより複雑な音色を作り出すことができるようにしたほか、「DX7」本体で音色の編集ができること、カートリッジ式の記憶媒体に音色の保存ができること、これらの進化を遂げながら「GS1」のおよそ1/10の価格となったことなど、当時のシンセサイザー業界に絶大なインパクトを与える製品として発売されました。

この頃のヤマハ社内では、複数の部門で複数のモデルが並行して開発されており、前述の「GS1」の試作機が「TRX100」というモデルだったのに対し、「DXシリーズ」の直接的なプロトタイプとなったのは「PAMS (Programmable Algorithm Music Synthesizer)」というモデルでした。実は「DX7」本体にも「DIGITAL PROGRAMMABLE ALGORITHM SYNTHESIZER」とプリントされおり、当初のコンセプトが受け継がれていることがうかがえます。
PAMSはその名の通り、フェイズ・モジュレーション(位相変調)、アプリチュード・モジュレーション(振幅変調)、アディティブ(加算合成)、そしてフリケンシー・モジュレーション(周波数変調=FM)といった計算方法での音作りを行うことができ、かつ当初からプログラムをメモリーできる仕様でした。しかし、音作りの自由度を高くした反面パラメーターが膨大になり、一般ユーザーが音作り可能なレベルのシンセサイザーとしてPAMSをそのまま製品化することはできませんでした。

膨大にふくれ上がったパラメーターをどのように簡略化するかという難題に取り組む過程で、モジュレーターとキャリア用のエンベロープジェネレーター・パラメーターの共通化、アルゴリズムの32種類への絞り込みなどが決まっていきます。こうして第一期「DXシリーズ」である「DX1」、「DX5」、「DX7」、「DX9」が完成しました。当時はDX1/DX2/DX3/DX4/DX5と5つの開発コードでモデル開発が進められていたのですが、DX1はそのまま「DX1」に、DX2/DX3が「DX5」に、DX4が「DX7」に、DX5が「DX9」となって製品化されました。数字こそ違いますが、開発コードがそのまま製品名にも活かされた珍しいケースといえます。

「DX7」は瞬く間に世界中に広まり、そのサウンドと共に80年代の音楽シーンを牽引する力となったのですが、その後のシンセサイザーに多大な影響をあたえるさまざまな要素が盛り込まれていたことも注目すべき点です。
まずは16文字×2行の液晶ディスプレイです。それまでのシンセサイザーではパラメーターをツマミやスライダーで表現していたため、パラメーターを数値で確認したり、音色名を表示したりする機能がありませんでした。これを表示できるようにしたことで作成した音色に名前をつけるという文化が生まれていきます。また、この液晶ディスプレイは各種音色パラメーターを表示する機能を兼ねており、それぞれのパラメーターを一つずつ呼びだして編集していくことで、膨大なパラメーターをシンセサイザー本体にすべて並べる必要がなくなります。これによってあのスマートな「DX7」の筐体デザインが実現することになり、それまでのシンセサイザーと一線を画す存在となったことも大ヒットの要因になったといえます。

次に音色を保存したり読み出したりすることができるカートリッジスロットもデジタルシンセサイザーならではの装備です。「GS1」では磁気を用いた音色カードを採用していましたが、スピーカーなどの強力な磁気にも影響されないメモリーを搭載したカートリッジ方式にしました。「DX7」は本体に32個の音色を記憶することができるのですが、ROMカートリッジを使用するとさらに64個の音色を増やすことができます(RAMカートリッジは32音色を記憶可能)。この音色を増設できるという考え方はデジタルシンセの特徴とも言うべき機能で、取り扱いの容易なカートリッジ式を採用したこともあり、プロの音色を購入できるようになるきっかけとなりました。アナログシンセ時代、プロミュージシャンが奏でている音を再現するには、ツマミの位置をまねして似たような音色を作ることしかできなかったのですが、「DX7」ではプロミュージシャンが使っている音色そのものをカートリッジで購入することができるのです。シンセサイザー本体だけでなく、そこから出てくる音色も全く同じものを手に入れることができるという新しい発想は、アマチュアミュージシャンにとっても非常に魅力的な機能であったことは言うまでもありません。
また、複雑にプログラミングされた音色をコントロールする鍵盤の性能が飛躍的に向上した点も見逃せません。鍵盤のタッチセンスによってさまざまな音色変化をもたらすFM音源を活かすために、当時エレクトーン用に開発されていた「FS鍵盤」を採用。この「FS鍵盤」は、「DX7」以来ヤマハシンセサイザーのフラッグシップモデルに20年以上採用され続け、数多くのミュージシャンに愛されました。
そしてもう一つ忘れてはならないのがMIDI(ミディ)の搭載です。MIDIとは鍵盤を弾いたときの情報をはじめ、サスティンペダルやボリューム情報など、さまざまな演奏情報をデジタルで送受信する規格の一つで、1982年に発表されています。規格が制定されて間もないタイミングに搭載されたことも注目された一つの要因ですが、この機能を使用してMIDIシーケンサー(自動演奏用の機器)による制御を行うと、人の演奏を再現するだけでなく、人が演奏したものとは異質の機械的サウンドや、弾き続けることが困難な速いフレーズなどを演奏させることができるようになります。FM音源特有のゴリゴリとしたシンセベースの音にMIDIによる機械的な演奏を組み合わせることで生まれた80年代ダンス系サウンドやテクノ系サウンドなど、斬新かつ前衛的なサウンドを奏でることができたのも「DX7」が注目された要素といってよいでしょう。
このように「DX7」は、楽器ビジネスから音楽業界までを激変させ、その後のポピュラー音楽シーンやシンセサイザーの方向性に多大な影響を与えたデジタルシンセサイザーだったのです。
変革するシンセサイザー環境
「DX7」発売後、シンセサイザーを取り巻く環境は大きく変わっていきます。MIDIを搭載したことにより、自動演奏だけでなくリアルタイムに鍵盤を弾く演奏においても音源を拡張するという発想が生まれます。例えば同じエレクトリックピアノの音を2台の「DX7」で鳴らし、片方の「DX7」のピッチを少しだけ上げることでコーラス的な効果を得て、リッチなサウンドを得るなどといった使い方です。実際には鍵盤楽器を一人で同時に3台も4台も弾くことはできませんので、拡張するために使用する「DX7」に鍵盤が付いている必要性がありません。そこで考えられたのが鍵盤の付いていない音源モジュール「TXシリーズ」という製品です。
「DX7」発売後、ラックマウント式の音源でリッチなサウンドを再現するために考案された「TX816」や、「DX7」の音源部分をユニークな筐体に納めた「TX7」など、キーボードの付いてないデジタルシンセサイザー(音源モジュール)を発売、音源を拡張することで得られるゴージャスなFMサウンドも当時の音楽シーンにとって欠かせない存在となっていたこともあり、非常に注目を集めました。
その後「DXシリーズ」は、さまざまな変化を伴い進化していきます。「DX7II」ではアルミ素材を使用し筐体の軽量化を図り、可搬性を大幅に改善します。さらに当時は手軽に入手ができた3.5インチフロッピーディスクを搭載。パン機能が備わって出力が2系統になったり、マイクロチューニング機能を搭載しアラビア音階などの平均律とは異なる音律を再現することができるようにするなど、よりクリエイティブなツールとして進化していきます。発売時期は前後しますが、「DX100」というミニ鍵盤のモデルではピッチベンドホイールを左上に配置し、ストラップをつけて立奏したときに、ギターのチョーキングのように使用できるピッチベンド上下反転機能をつけるなど、プレイヤーの立場に立ったアイデアなども積極的に採用していきます。
80年代に一世を風靡した「DXシリーズ」の変遷は、現在のシンセサイザーで採用されているユーザーインターフェースや楽器としての基本機能を確立する原動力になったといっても過言ではないでしょう。
音楽制作という切り口へ
それまではアマチュアが奏でる音楽は生演奏があたりまえで、レコーディングはプロのスタジオで行うものでしたが、80年代はカセットテープの4トラックMTR(マルチトラックレコーダー)が普及した時代でもあり、プロアマ問わず自宅で多重録音を行う人が増えていきます。当初はドラムマシーンで作成したリズムトラックに合わせてベース、ギター、キーボードなどを重ねていくという手法で作成されていましたが、MIDI対応機器が普及し始めるとシーケンサーやドラムマシーンを同期演奏させ、ベースパートやコードを奏でるパートを「DXシリーズ」などのMIDI対応シンセサイザーで演奏させるという手法が普及していきます。しかし、「DX7」では同時に一つの音色しか奏でることができないため、ベースとエレクトリックピアノを自動演奏させるためには2台の「DX7」を用意する必要があります。
そこで考えられたのが音源のマルチパート化です。MIDIにはチャンネルという概念があり、「QXシリーズ」などのMIDIシーケンサーからチャンネル分けした演奏データを送信することにより、チャンネル1はベースの演奏、チャンネル2はピアノの演奏、チャンネル3はマリンバの演奏、といった具合に個別に演奏させることが可能です。音源側はチャンネルごとに指定の音色で奏でることになるのですが、この場合シンセサイザー3台が一つの音源に納められているということになります。こういった発想で製品化された音源モジュールが「TX81Z」で、4オペレーターのFM音源シンセサイザーが8台分入った画期的な製品でした。8台分全てを同じチャンネルに設定して重ねて使用し、重厚なサウンドを得られました。また、オペレーターに初めてサイン波以外の波形を搭載し、多彩な音色を奏でることも可能で、隠れた名器ともいわれた音源モジュールです。
この頃から、シンセサイザー一台でリズム、ベース、コード楽器といった具合にすべてのパートを演奏させる制作スタイルが浸透し始め、ついにはMIDIシーケンサーを搭載したシンセサイザーというものまで登場します。先程の「TX81Z」に鍵盤とMIDIシーケンサー、PCM音源のリズムマシーン、デジタルエフェクターをパッケージした「V50」はこの流れを反映した究極のFM音源シンセサイザーで、この機種を境にシンセサイザーがワークステーション時代に突入していきます。
1981年の「GS1」に始まり1989年の「V50」まで、10年足らずの間にデジタルシンセサイザーからワークステーションへ進化するという、ヤマハシンセサイザーの歴史にとって80年代は激動の時代だったと言ってよいでしょう。