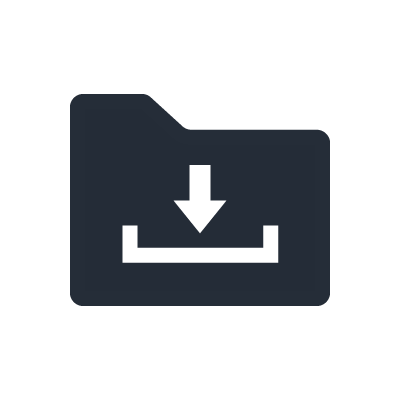【第3章】音源システムの進化と音楽制作へのアプローチ
サンプリング技術を利用した音源へ

80年代はFM音源を軸にシンセサイザーのデジタル化を行い、LSI技術の進化と共にさまざまな機能を搭載した商品をリリースしていきました。この流れの一方で、生楽器の音をサンプリング(デジタルレコーディング)したものを音源として利用する技術も開発されていきます。ドラムやパーカッション、効果音などは、一つの音が短いためにサンプリングが容易で、再生するときに音程や音色の変化をあまりつけなくてもよいため、リアルなサウンドを簡単に再現することが可能です。このため、サンプリング技術を利用した音源は、PCM(Pulse Code Modulation)音源とも呼ばれ、80年代から各社がリズムマシーンなどを製品化していきました。ヤマハではエレクトーンに搭載されていたリズムマシーンなどをはじめ、サンプリング技術を利用した音源をAWM( Advanced Wave Memory)音源と呼んでおり、「RXシリーズ」などを発売していました。
もちろん、ドラムだけでなくピアノやギターなどの長い減衰時間をもつ楽器の音や、オルガンなどの持続音についてもサンプリングされていたのですが、どちらかというとサンプラー(録音した楽器の音をそのまま再生する機器)としての使い方が主体で、積極的に音作りをするシンセサイザーとしてや、自由に演奏表現できる楽器として使うには、まだ多くの課題がありました。
この当時、技術的に課題とされていたのが、アナログシンセサイザーと同じような挙動をするデジタルフィルターの開発です。もちろん原理的な計算式はすでに理解されていましたが、それをデジタル回路で再現しようとするとアナログのように滑らかな挙動にならず、特にレゾナンスと呼ばれるシンセサイザー独特の音にくせを持たせる機能の再現が困難でした。他社からもすでにデジタルフィルターを搭載したシンセサイザーが発売されていましたが、当時はまだレゾナンス機能を搭載していなかったり、擬似的な仕様でレゾナンスがかかったような音を出したりするものなど、不完全なものがほとんどでした。
ヤマハでは当時、すでにアナログ回路と同等の挙動を可能にしたデジタルフィルターの開発に成功しており、1989年に満を持して「SY77」というモデルにこの機能を搭載しました。この「SY77」にはAWM音源とFM音源の両方が搭載されているのですが、どちらもデジタルフィルターを使った音作りが可能になったことで表現力が倍増し、それぞれ「AWM2音源」「AFM音源」といった具合に音源の名称も刷新されました。「SY77」ではサンプリングとFMをハイブリッドで使用して音作りが可能なだけでなく、AWM2音源のPCM波形をAFM音源のオペレーターの波形として使用することもできるなど、かなり斬新な機能も搭載されています。
またデジタルフィルターのカットオフフリケンシーやレゾナンスといったパラメーターを鍵盤のベロシティーやアフタータッチなどでコントロールすることも可能で、当時これら機能を総称してRCMシステム(Realtime Convolution & Modulation)と呼んでいました。デジタルでありながら滑らかな挙動を持つフィルターにPCMとFMという当時の2大デジタル音源を搭載した「SY77」は、90年代を代表する夢のようなシンセサイザーだったのです。

マルチティンバー

90年代シンセサイザーのもう一つの側面は音源のマルチティンバー化です。マルチティンバーとは、複数の音色を同時に奏でることができる機能で、音楽制作にとって欠かせない機能です。
ライブでキーボーディストが演奏する際にはあまり重要視されない機能ですが、ドラム、ベース、ピアノ、ソロ楽器といった具合にさまざまな音を奏でることができるのに加え、80年代後半からMIDIシーケンサーが普及し始めたこともあり、1台のシンセサイザーでアンサンブルを作成してデモ音源を作ったり、伴奏を流しながらキーボーディストが一人でパフォーマンスをしたりするといった使われ方が増えていきます。もちろん、こういったマルチティンバー音源は少し前のFM時代からあったのですが、AWM2音源のように高音質でリアルな生楽器の音を奏でるシンセサイザーが出始めると、マルチティンバーを重視するユーザーが増え、同時に発音するボイス数、同時に奏でられる音色の数、音色のバリエーション、価格などの競争が激しくなっていきます。
それまで複数の音色をMIDIシーケンサーで自動演奏させるためには音色の数だけ数十万もするシンセサイザーを買いそろえなければならなかったのですが、それがたった1台で実現できるのです。
そういった意味では、8パートマルチティンバーの製品は他社も含めていくつか販売されていましたが、16パートマルチティンバーという点では、コストパフォーマンスに優れた音源モジュール「TG55」や、ワークステーションの「SY77」、「SY55」は、音楽制作層を拡大させた画期的なものといえるでしょう。
PCMシンセサイザーとしての進化

サンプリング技術を利用した音源が普及し始めると、各社からさまざまなPCM音源内蔵シンセサイザーが発売され、競争が激化していきます。そこでヤマハでは「SY77」で完成したAWM2音源をさらに進化させてさまざまな方向性を模索していきます。
「SY77」発売の翌年、1990年リリースの「SY55」では、サンプリングした波形を使用して音を発生する「エレメント」と呼ばれる部分を4つまで同時に使用できるように拡張しました。これによって例えば、ピアノのアタック部分だけとフルートの持続音を組み合わせて音作りを行ったり、トランペット、トロンボーン、アルトサックス、テナーサックスを混ぜ合わせてホーンセクション的な音を作ったりするなど、よりクリエイティブな音作りができるようになりました。
またこの頃から、エフェクターの進化も急激に進みデジタル化され、シンセサイザーに内蔵されたエフェクターだけでも、レコーディングスタジオにある専用機に負けないクオリティのエフェクトをかけることができるようになっていきます。
さらに1991年に発売された「SY99」では、AWM2音源の基となるサンプリング波形を外部から取り込むことができるようになるなど、拡張性や音色制作の可能性を拡げる機能を実装し、PCMシンセサイザーとして著しい進化が遂げられています。この90年代前半に進化したAWM音源の仕様は「MOTIFシリーズ」にも活かされており、「エレメント」などの用語も受け継がれています。
時代はワークステーションシンセサイザーへ

80年代後半から90年代になると、それまで利用されてきた「QXシリーズ」のようなハードウェアシーケンサーが、コンピューターベースのシーケンスソフトウェアに移り変わっていきます。スタジオではコンピューターにMIDIインターフェース、ラックに積み上げられたサンプラーやシンセサイザーなどの音源、さらに演奏を入力するためのマスターキーボードといった多くの機器が並べられるようになりました。このような、コンピューターを中心とした音楽制作システムを利用すると、一人であらゆるパートを意のままに演奏し録音することができ、短時間で曲作りができるようになりますが、ある程度コンピューターの知識に長けていること、そして複雑な結線やさまざまなメーカーの音源を使いこなす技術が要求されるため、キーボードプレイヤーには若干敷居が高かったというのも事実です。この辺りからシンセサイザーという楽器に求められる要素に2つの方向性が生まれていきます。
一つは音源としての要素です。もちろんウインドシンセサイザーやギターシンセサイザーの音源として利用するということもありますが、多くは音楽制作における音源という意味で、コンピューターベースの音楽制作システムの中に組み込んで活用するという方向性です。コンピューターやMIDIを使って演奏するのであれば、それまでのシンセサイザーのように音源と鍵盤が一体化されている必要はないので、ヤマハはこの方向性に対して「TG(トーンジェネレーター)」という型番でラックマウントやデスクトップ型の音源を発売していきます。
もう一つの要素はキーボーディストやアレンジャーを満足させるワークステーションシンセサイザーという方向性で、この時代の鍵盤付シンセサイザーはほとんどがこの形を踏襲していきます。コンピューターの知識が無くてもシーケンサーを使った音楽制作ができること、複雑な結線が必要なく一台で完結すること、スタジオクオリティの高音質で創作意欲を沸き立てること、電源を入れて即座に音楽制作ができることなど、いくつかの要素を突き詰めた結果、90年代を代表する究極のワークステーションシンセサイザーとして登場したのが前述の「SY99」です。そして、この「SYシリーズ」こそがヤマハのワークステーションシンセサイザーの原点といっても過言ではないでしょう。
さらなる新音源の探求

90年代になって主流になりつつあったサンプリングやPCM音源は、実際に存在する楽器を録音し再生する技術がベースです。高音質で録音/再生すれば、本物そっくりの音が得られるわけですが、これを楽器にするのは簡単ではありません。楽器は音程や音色を演奏者の意のままにリアルタイムでコントロールできる必要があるからです。例えば、ピアノの鍵盤は88鍵、88の音階があり、MIDIで表現できる音の強さは127段階、さらに音の時間的な変化やつながり、コントローラーなどでの表現など、意のままの音を得るには、それだけ多くのパターンの音を録音しておき、瞬時に相応しいものを選んで再生する必要があります。膨大な録音を処理し、スピードが遅く高価なメモリーやプロセッサーを使って実現するには、当時の技術ではまだまだ課題が多かったのです。
FM音源は少ないメモリーで表現力豊かな音色が得られるシステムでしたが、ヤマハのシンセサイザー開発チームは、さらに楽器らしいリアルで表現力豊かな音源システムの模索を続けていました。そんな中、可能性を見いだしたのが「物理モデル」です。

物理モデルとは実際に起こる物理現象を計算式で導き出し、シミュレートするというものです。例えばサックスを吹くという行為を考えた場合、人間が息を吹いてリードを振るわせ、サックスの中を共鳴して増幅されていく様子を計算し、シミュレートして発音する音源方式です。FM音源同様にスタンフォード大学で研究されていた理論をもとに、80年代から基礎研究を進めていましたが、新音源システムの開発を急務とされた90年代当初、シンセサイザーとして実用的なものに落とし込むため、当時のシンセサイザー開発チームのリソースを最大限に活用して研究開発を進めていきます。
そして世界に先駆けて「物理モデル」を利用した「VA(Virtual Acoustic)音源」を完成させ、これを搭載したシンセサイザー「VL1」を1993年に発売します。「VL1」は「SYシリーズ」のようにさまざまな楽器の音を同時に奏でられる発音数の多いシンセサイザーが全盛の時代に逆行して2音ポリフォニックという異色のシンセサイザーでした。サックスやトランペットなどの管楽器の音やバイオリンなどの弦楽器の音をリアルに再現することができるのが特徴で、「インストゥルメント」と呼ばれる発音部分で発生させた信号を「モディファイア」と呼ばれる楽器の特性をコントロールする部分で味付けしていきます。例えば管楽器の音の場合、マウスピースやリードにあたる部分が「インストゥルメント」で、管の材質や形状などが「モディファイア」ということになります。

これらにシンセサイザー特有のパラメーターをアサインして変化を加えていくのですが、よりリアルな演奏感を演出するためその演奏方法も自由度の高いものになっていました。例えば管楽器の音色ではブレスコントローラー(息を吹く強さでMIDIのパラメーターを可変できる装置)を用いて発音するようになっており、今までのシンセサイザーのように鍵盤を押しただけでは発音しません。管楽器のキーを押すように鍵盤を弾きながら、ちょうど息を吹き込むのと同じよう感覚でプレスコントローラーに息を吹き込むと発音するようになっています。
もちろんMIDI規格に対応したシンセサイザーであればブレスコントローラーで音量を調整することは可能なのですが、「VL1」では息の強さが変わることによる音色や音程の微妙な変化まで、本物のサックスやトランペットと同様に計算されており、よりリアルなサウンドを奏でることができます。この「VL1」の音色は本物の管楽器と聞き間違えるほどのリアルさであったため発売と同時に世界中で注目を浴びました。その後、「VL1」を音源モジュールにした「VL1-m」や廉価版の「VL70-m」なども発売され、現在でもウインドシンセサイザー奏者を中心に愛用されていきます。

VA音源には「VL1」に搭載されていたS/VA(Self oscillation type/VA )音源というものに加え、F/VA(Free oscillation type/VA)音源というのもあり、これを搭載した「VP1」というモデルも翌年に発売されます。F/VA音源では打楽器や打弦楽器の叩き方やはじき方のバリエーションならびに擦弦楽器の擦り方のバリエーションなどを数多くシミュレートできるようになっており、単なる楽器のシミュレートにとどまらずに自然界には存在しないような楽器をシミュレートしてしまうこともできます。しかし、「VL1」も「VP1」も技術的には非常に優れた表現力豊かなシンセサイザーであったものの、ブレスコントローラーをはじめとする数々のコントローラーを同時に操りながら演奏する必要があり、演奏者にも高度なテクニックが求められました。そのため、ごく一般的なキーボード奏者にはあまり受け入れられず、一般的な楽器として広く普及するには至りませんでした。
マーケットの変化に翻弄される90年代

80年代に「DXシリーズ」でデジタルシンセサイザーの確固たる地位を確立したヤマハは、80年代後半から訪れるPCMシンセサイザー時代に追従すべくAWM2音源を開発し、「SYシリーズ」へと移行していくのですが、シンセサイザーメーカーとしてヤマハが置かれた状況は必ずしも順風満帆というわけではありませんでした。
中でも大きな影響を受けたのが為替の変動です。「DX7」が発売された1983年ごろの為替相場はアメリカドル1ドルに対して日本円でおよそ240円。これが「SY77」を発売した1989年には1ドル145円、「SY99」が発売された1991年の年末には1ドル130円を下回り、「VP1」が発売された1994年には、ついに1ドル100円を切るところまで円高が進んでいきます。
「DX7」時代には高性能なシンセサイザーを低価格で世界市場に投入できたヤマハですが、90年代の急激な円高へのシフトに伴い、価格競争力を失っていきます。特にエントリー向けに開発したモデルが海外では中高価格帯の製品となってしまい、ターゲットとしたユーザーに届かないという現象も起きました。

さらに追い打ちをかけたのが日本国内のバブル崩壊です。1991年以降日本の景気は急速に衰退し、高価格帯の電子楽器がほとんど売れない状況に陥っていきます。国内の他のメーカーも同様に苦しい状況でしたが、モデルの絞り込みや機能の共通化、さらに価格を抑えたラインナップで構成するなどの工夫で厳しい時代に挑んでいました。
もともと生楽器と同じような表現力を持たせて本物の楽器に近づけようというのがシンセサイザーの始まりだったのですが、サンプリング技術の進化によって手軽に本物の楽器と同じような音が得られるようになると、音作りに柔軟なシンセサイザー機能より生楽器の代替になるプレイバックサンプラーという要素が重要視されていきます。さらにMIDI音源の音色に関する共通規格として1991年に登場したGM規格や、MIDIによる演奏データの共通フォーマットであるスタンダードMIDIファイル(SMF)などが定義されると、同じ演奏データを使用して各社のシンセサイザーに搭載された音色を簡単に比較することができるようになりました。このため、シンセサイザーとしての機能や演奏性よりも、音色の違いや音楽制作における利便性が注目されてきます。

他社はここに目をつけてハードや機能面の開発を最小限に抑え、PCMシンセサイザーの心臓部ともいえる元波形のクオリティとバリエーション、すなわちコンテンツでの勝負に切り替えて差別化をはかり、次第にユーザーを増やしていきます。ヤマハはこういった時代の潮流の中、技術革新での打開策を図り、パフォーマンス(演奏)志向のモデル「VL/VP」の対極として、ワークステーションとしての音楽制作機能をブラッシュアップし、さらに価格面でもコストパフォーマンスを意識したモデルとして1994年に「Wシリーズ」、翌1995年にはXGフォーマットに対応した「QS300」というモデルを立て続けにリリースしました。特に「Wシリーズ」は当時としては大容量8MBのウェーブ、6系統のマルチエフェクター、常時16パートマルチティンバー、GM対応と正に音楽制作に特化したモデルといえましたが、「SYシリーズ」のように、多くのプロフェッショナルキーボーディストに受け入れられるモデルではありませんでした。

「新音源の開発」「画期的な機能の搭載」「PCM音源の追求」といったさまざまなアイデアがあった中、数多くの商品を企画して出口を模索していました。しかしながら、シンセサイザー市場を取り巻く環境の急速な変化に対応が追い付かず、また顧客のニーズに100%応えられる製品がリリースできずに、ヤマハのシンセサイザーは次第に苦境に追い込まれていきます。
90年代前半には、どこでも音楽制作を行うことを可能にした「QYシリーズ」が大ヒットし、XGフォーマットの推進により誰でも気軽に音楽制作できるようになりました。シンセサイザーの分野では、「SY/TGシリーズ」に続き、「EOS Bシリーズ」、「Pシリーズ」、「VL/VP」、「Wシリーズ」、「QS300」、「A7000」など、商品数にしておよそ30機種以上の商品をリリース/モデルチェンジをしたものの、徐々にステージやスタジオでヤマハではないロゴのシンセサイザーが目に付くようになっていきます。この状況を如何にして打開するか、ヤマハのシンセサイザーは窮地に立たされていました。