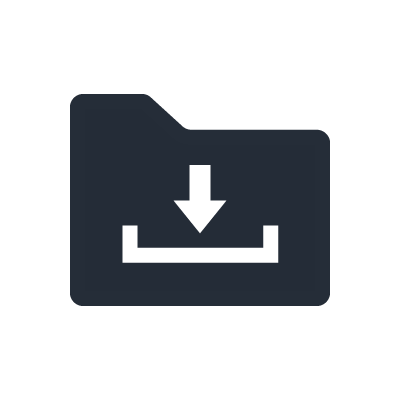【第6章】ヤマハシンセ新章の始まり
「放課後プロジェクト」から始まった「reface」

シンセサイザーに限らず新たな技術が熟成していくと、市場に対してどのような商品が受け入れられるだろうという予測を元に新製品が開発されていくようになります。「MOTIFシリーズ」ではマーケットリサーチを入念に行い、ワークステーションシンセサイザーという方向性の中からDAW(Digital Audio Workstation=Cubase などの音楽制作ソフトウェア)との親和性を求める市場の意見を採り入れた製品作りが行われました。しかし、情報が迅速かつ大量にあふれ出す情報化社会において、市場の意見を採り入れる=成功する、という短絡的な考えは通用しない時代に突入しているのです。そんな中、ヤマハの若い世代の技術者たちが面白い試みを始めます。
「こんな製品があったらいいのに…」という話を普段からしていた3人の技術者が、就業時間外で、いわば「放課後プロジェクト」的に新たなシンセサイザー開発に取り組みます。もともとシンセサイザーで音作りをして遊ぶのが好きだった3人は、「気づいたらツマミを触って遊んでしまう」ものを作ろうと意気投合し、試作に入ります。


まず、モデルになったのが1982年に発売された「CS01」。曲を演奏するツールとしてよりも、音を出して戯れること、すなわち「音と遊ぶ」という新たな価値にたどり着くことになるのです。そしてそれこそが音を創造(生成)する楽器シンセサイザーの原点ではないかと…。
彼らは早速このコンセプトを正式にプロジェクト化するために社内に働きかけを行います。膨大なプレゼン資料を作成し、社内に熱意を伝えることにより「放課後プロジェクト」ではなく、業務時間の一部を使ったサブプロジェクトとしての活動が始まりました。
こうして始まったプロジェクトは、後に「refaceシリーズ」のひとつとして発売される「reface CS」の原型「ES」というシンセサイザーの検討からスタートします。この「ES」はEnjoy Synthesisの頭文字を取ったもので、音作りを楽しむために音源にはアナログシンセ系を採用し、操作子をシンプルにしたモデルでした。

「CS01」のようなミニサイズの鍵盤と筐体を基本に、「こんなデザインで…」「こんな機能で…」を出し合い、「“音の振る舞い”と気軽に遊べるプチ本格楽器」をコンセプトに掲げ、新たなコンセプトを持ったシンセサイザーを模索していきます。もちろんアナログシンセ系の「ES」だけでなく、FM音源の「DX」、エレクトリックピアノ音源の「CP」、オルガン音源の「YC」のアイデアなどもこの時点から検討されていました。
ここから3人は具体的に音の出る試作機を制作するフェーズに入っていきます。ヤマハがすでに開発していたAN(アナログモデリング)音源にソフトウェアと鍵盤やコントローラー素子(スライダーなど)を接続し、プロトタイプを作成していきます。この段階で、「音作りを楽しめるUI(ユーザーインターフェース)はどういうものなのか?」という感性の部分にストレートに切り込んだことが、「reface」を「プチ本格楽器」に仕上げる大きな要素となっていきます。
こうして制作された「reface CS」の原型である「ES」はこれまで市場に投入されているバーチャルアナログシンセサイザー(回路的にはデジタルでありながらアナログシンセを再現したもの)とは一線を画すシンセサイザーへと進んでいきます。まず、スライダーとパラメーターの関係を徹底的に作り込みました。

一般的なアナログシンセでは鋸歯状波や矩形波などの音を発生するオシレーター、音の明暗を変化させるフィルター、音量的な音の出方をコントロールするアンプという3つのセクションがあり、それぞれにエンベロープ(時間的な変化)を調整したり、LFOという低周波発生機で周期的な変化をさせたりすることで音作りを行うため、それぞれのパラメーターを個別に操作できるものが多いのですが、「ES」ではAN音源が持つ多彩な音の変化を、「TYPE」「TEXTURE」「MOD」という3つの操作子で最大限に引き出せるようにし、各スライダーを動かしたときの音の変化にワクワクできる工夫を凝らしました。
試作機で社内評価を幾度も行い、そこから得られた共感は音源、UI、サイズに対する手ごたえに繋がりました。そしてここから「プチ本格」な価値をさらに具体化するためのデザイン検討に取り掛かります。3人の熱意とコンセプトに共感したデザイナーからさまざまなデザインアイデアが提案されていきます。

筐体全体のデザインだけでなく、スイッチやレバーなども触っていて楽しく、見た目にもかわいらしい要素を盛り込み、デザインモックアップを創り上げていきます。具体的な形が見えるようになってくると、プレゼンテーションに対する社内の反応も徐々に変わってきました。そして、次なるステップとして掲げていた、実際に動くワーキングプロトの試作が認められるのです。
ここから彼らは、本業務後の夕方より連日連夜の試作作業を進めていきます。技術者自身が実現したいアイデアを自らの力で具体化していく作業は、まさにクラフトマンシップ。理想の「プチ本格楽器」を目指し、自らの創意と工夫を凝らすことで、ワーキングプロトは完成にこぎ着けます。
実際に音が出て、コンセプト通りに仕上がったワーキングプロトは、より多くの人たちから共感を得て、正式な製品開発を行うことに決まったのでした。

正式な製品開発が決まると、今までの試作とは異なる市場性や生産性などクリアしなければならない課題が見えてきます。特に理想の「プチ本格楽器」を実現するためには、演奏感の良いミニサイズの鍵盤開発について検討しなければなりませんでした。鍵盤の設計陣を交えたチームは、「世界一弾けるミニ鍵盤」を目指して開発を始動させます。参考にしたのはヤマハの教育用鍵盤楽器である「ピアニカ」。「CS01」や「DX100」などに使用されていたミニサイズ鍵盤より鍵盤の奥行きが長くて弾きやすいという部分に注目しました。また、それだけではなく鍵盤を押し込んだ時の感覚やグリッサンド時のフィーリングに重要な鍵盤表面の形状など、細部のディテールにまでこだわった新鍵盤が誕生することになるのです。このモデルを一番知り尽くし、情熱を持って開発している彼らだからこそ、「プチ本格楽器」というコンセプトにしっくりくる鍵盤にたどり着くことができたのです。
こうして「reface」のおおまかな要素がそろい始めたのですが、ここから最終的な製品にこぎ着けるまでにも、多くの課題をクリアにすることが必要でした。まずはデザインを崩さずに小さな内部スペースに部品を収める努力。1mmでも薄くなるような部品選定を行うだけでなく、生産工場のライン上で大量生産が可能な内部構造に仕上げなくてはなりません。さらに音質の肝ともいえるDAC(D.A.コンバーター=デジタル信号をアナログの電気信号に変える装置)の選定や、内蔵スピーカーの設計など…。特に、コンセプトの「気軽に」を実現させる内蔵スピーカーに至ってはゼロから独自設計で行っていきます。

また、最終的な出音のチューニング、すなわちサウンドデザイン面でも妥協を許さず開発が進められていきます。後の「reface CS」になる「ES」ではオシレーターを中心としたパラメーターの追い込みを、「DX」では複雑なFM音源をシンプルに見せるための音源アルゴリズムやUIの見直しを、「CP」ではドライブやトレモロなど音色ごとのパラメーター調整を、そして「YC」では良質のYCオルガンサウンドを求めて新たなサンプリングを行いました。
さまざまなこだわりを持ち続け最後までコンセプトを守りきった結果、2015年7月に「reface CS」「reface DX」「reface CP」「reface YC」の4機種が発売されることになります。「reface」という名前には「re:face=もう一度向き合う」という意味が込められています。
開発者自身が大好きなシンセサイザーと向き合い、情熱を持って開発したシンセサイザー「reface」。この「プチ本格楽器」を手にしたユーザーがもう一度シンセサイザーと向き合ってもらえたら、このプロジェクトの3人も笑顔になるに違いないでしょう。
音楽の進化を見据えたシンセサイザー「MONTAGE」
2001年の発売以降、15年にもわたりヤマハシンセサイザーのプラッグシップモデルとして君臨してきた「MOTIFシリーズ」。究極のワークステーションシンセサイザーを目指して企画され、不動の地位を獲得しました。時代が移り変わって行く中で、「MOTIF」に替わる次のフラッグシップシンセサイザーを望む声も多くなっていきます。しかし、単に「MOTIF」の後継機種を出せば良い、ということではなく、今一度ハードウェアシンセサイザーの価値について問いただすところから企画がスタートするのでした。

「ハードウェアシンセサイザーの価値」という壮大な問いに対し、「DAW全盛の時代において、ハードウェアシンセサイザーがDAWと競い合うこと自体がナンセンスで、シンセサイザーとして音を創造し、コントロールする楽しさを味わえることこそがハードウェアシンセサイザーの醍醐味なのではないか…」という方向性を考えるようになります。では、具体的にフラッグシップシンセサイザーに必要な音を創造し、コントロールする楽しさとは何なのでしょうか?
新シリーズの開発担当者は現在の音楽におけるシンセサイザーの役割や曲の作り方、音のありかたなどに注目しました。そしてそれらは二つの手法でほとんどが表現できるという結論に達したのです。
まず一つ目が多次元の音変化。今までのシンセサイザーでは、例えばフィルターというパラメーターで音を明るくしたり暗くしたりすることで音作りを行ってきました。この他にも音量変化やエフェクトで味付けをするなど多様なパラメーターが搭載されていますが、それぞれ独立して調整を行い、音色づくりを行っています。これらのパラメーターを「複数同時に変化させる」、というのが多次元音変化の基本的な考え方になります。

もちろんそれぞれのパラメーターをノブやスライダーにアサインしてリアルタイムに調整することは可能なのですが、DJのように両手でノブやスライダーを操作すると、鍵盤を演奏することができず、さらに気持ちいい音変化のためには、それぞれのパラメーターの動きに相関関係がある(例えばフィルターのカットオフとレゾナンスなど)ことも重要で、これらを維持しながらコントロールするには既存の方法では不可能でした。そこで、鍵盤を演奏しながら多次元音変化を実現するために開発されたのが「Super Knob(スーパーノブ)」です。
「Super Knob」のきっかけとなったのはDAWにおけるオートメーション(トラックに記録されたオーディオやMIDIデータに対して、音色やエフェクトなどのパラメーター変化を時間的に変化させる)機能でした。しかし、オートメーションではあらかじめ記録したデータを再生するだけでしかなく、ライブパフォーマンスにおいてプレイヤーの感情や観客のボルテージに合わせて即興的に変化させることはできません。このオートメーションの機能をたった一つの操作子でリアルタイムに動かすことができれば…という思いから「Super Knob」が考案されたのです。

そして二つ目の要素は、「リズミカルな音変化」。音楽である以上リズムに合わせた音の変化は当たり前なのですが、現在の音楽では、音程や音の長さなどの譜面にできる情報だけでなく、音色やエフェクトについても楽曲のリズムに同期しているものが多くみられます。そしてこういった音作り(音変化)が重要な要素になっているのです。
このような先進的な音作りにシンセサイザーとしてどのように対応したら良いのかを追求した結果、「Motion Sequencer(モーションシーケンサー)」と「Envelope Follower(エンベロープフォロアー)」そして「Audio Beat Sync(オーディオビートシンク)」という機能が開発されることになるのです。
「Motion Sequencer」はパラメーターの動きをあらかじめ作成したシーケンスで時間的に変化させる機能で、最大16ステップのモーションシーケンスを基本に複数のシーケンスを切り替えたり同時に使用したりして複雑な音色変化をリズム同期して行うことができ、さらに、コントローラーでそのシーケンス自体をリアルタイムに変化させることも可能です。

「Envelope Follower」はADインプットに接続したオーディオ信号のエンベロープ(この場合は音量の時間的な変化)を使ってパラメーターをコントロールする機能で、入力オーディオ信号のビート感をもった多次元音変化を作り出すことができます。また、このオーディオ信号からテンポを検出、追従する機能が「Audio Beat Sync」です。こういった機能はまさにライブパフォーマンスを強く意識したもので、DAWを使用した同期演奏のライブだけでなく、ドラマーがリズムのイニシアチブをとる生演奏においても、楽曲のリズムに同期した音色変化を実現することが可能となるのです。
このように音色をリアルタイムかつ楽曲のリズムに合わせて多次元変化させるというコンセプトは決まったのですが、シンセサイザーの心臓部ともいえる音源部分の決定においてはさまざまな葛藤がありました。
「MOTIF」でも搭載されていたサンプリング音源であるAWM2音源は「MOTIF」より世代が進み、高解像度かつ高機能になり音源エンジンとしての性能は格段に向上しています。さらにサンプリングされる音そのものやそれらを使用して作られた音(ボイシング)に関しても、長い期間にわたり繰り返して調整することで、表現力やサウンドクオリティーが非常に高いものに仕上がっていったのです。その一方で、前述の音色の多次元変化を最大限に活かすには、サンプリング+フィルター+エフェクターという音源方式だけでなく、オシレーターの波形レベルで劇的な変化を実現できる音源が必要だと考えるようになります。ここで、ヤマハ独自の音源方式である、「DXシリーズ」でおなじみのFM音源が浮上することになるのです。
ヤマハではこの少し前から、次世代のFM音源を搭載した音源LSIの開発を行っており、その完成目処が今回のフラッグシップシンセサイザー開発とクロスしました。倍音の少ないサイン波から一気に金属的なサウンドを作り出すことができるFM音源の特性が「Super Knob」や「Motion Sequencer」の可能性をさらに引き出せると考え、AWM2+新FMという心臓部を採用することに決定します。
この新たなFM音源は「FM-X」と名付けられ、8オペレーター(音を発生させたり音を変化させたりするための基礎となる部分)、88アルゴリズムに加え、オペレーターの波形にサイン波以外の波形を設定することができ、さらにサイン波以外の倍音成分を調整できるスペクトルスカートとスペクトルレゾナンスというパラメーターも新たに搭載されています。また、各パラメーターの解像度が圧倒的に細かくなっており、非常になめらかな音色変化が可能になっているなど、「FM-X」は今までのFM音源システムとは比べ物にならないほど表現力が強化されています。

このように新しいフラッグシップシンセサイザーの音源部分は、AWM2+新FMの2本柱に決定します。開発中の製品には開発コードネームと呼ばれる「呼び名」がつけられることが多いのですが、「2種類の音源と多次元変化により、弾き手との間にインタラクションを起こすシンセサイザー」=「Dual Algorithm Interactive Synthesizer」の頭文字をとって「DAISY(デイジー)」というコードネームがつけられ開発が進んでいきます。
音源仕様や「DAISY」の根幹ともいえる「Motion Control(モーションコントロール)」(「Super Knob」や「Motion Sequencer」などの音変化機能)の仕様に並行して、更なる新機能や筐体のデザインを含めたUI仕様の検討を行います。特に「DAISY」は、「MOTIF」のようなワークステーションシンセサイザーではなく、ライブパフォーマンスを意識したモデルであるため、Live Set(画面上に任意の音色を16個まで並べ、ワンタッチで音色を切り替える仕組み)や、SSS(Seamless Sound Switching=発音中に音色を切り替えても音が途切れない仕組み)、Scene(異なる音色設定を瞬時に切り替える仕組み)などがライブパフォーマンスに役立つ機能として「DAISY」に新たに搭載されました。新たに採用したタッチパネル機能付き液晶ディスプレイでのUI設計では、Live Set画面でのボタンの配置や間隔(認識範囲)を広く設定するなど使い勝手に配慮したデザインがなされています。

タッチパネル機能付きの液晶ディスプレイの搭載により、すべてが解決したわけではありません。視覚依存度が高く、物理的な凹凸のないディスプレイ上のボタンは、操作感がないため素早く確実な操作には不向きという問題を抱えています。そのため「DAISY」ではすべての操作を液晶なしでも行えるようにしてあります。この場合、液晶に配置されたボタンと物理的に用意されたボタンとの関係性に一定の統一感がないと操作しにくいため、液晶右側に配置されている音色選択用の32個のボタンを均等に配置し、ライブセットの選択時には左半分の4×4をパフォーマンスの選択に、右半分の4×4をライブセットのページ選択として使用できるようにデザインされています。


ボタン操作のマナーに関する部分も一から見直し、わかりやすく直感的に操作ができるUIを目指しています。結果として「MOTIF」とは若干異なるボタン配置やマナーになっているのですが、このあたりのこだわりが既成概念にとらわれない新しい考え方が反映された結果といえるでしょう。
筐体のデザイン面でもこだわりは多く、「MOTIF」が直線的だったのに対し、曲線を主体としたデザインをコンセプトにさまざまなデザイン案が考案されました。特に背面の逆Rは、今までにない新しいデザインです。また、ピッチベンドやモジュレーションホイールを操作する際に手のひらが当たる部分のカーブや仕上げについても、使いやすさとフィット感にこだわりました。

さらに出音のキャラクターを決定付けるDACおよびアナログ回路についても徹底的に改良されています。CPU性能が上がり、より複雑かつ高解像度の音作りが可能な状況になっても、最終的にはアナログの電気信号にしないと人間の耳に届けることはできません。そのため最終的な音の出口であるアナログ回路は幾度にも渡る試聴会と部品選定を繰り返し、丹念に作り上げました。ソフトウェアシンセサイザーではユーザーが使用するオーディオインターフェースによって音が変わってしまいますが、ハードウェアシンセサイザーでは音の最終的な出口までをパッケージとして提供する責任があります。「MOTIF XF」のさらに上を行く、より音楽的な出音を求めて設計された「Pure Analog Circuit(ピュアアナログサーキット)」は、新音源システムと「Motion Control」を組み合わせた「Motion Control Synthesis Engine(モーションコントロールシンセシスエンジン)」の魅力を最大限に引き出すサウンドに仕上がっています。
こうして全体像が組み上がった「DAISY」は後に「MONTAGE(モンタージュ)」という商品名で市場に投入されることになります。「MONTAGE」という言葉はフランス語の「組み立て」と言う意味で、映画の世界ではさまざまなカットを組み合わせて表現をおこなうフィルム編集技法のことを差します。「Motion Control」によって作り出される音の変化が、新しい音楽表現を創り出していく…そんなことを願って命名され、2016年5月「MONTAGE 6/7/8」の3機種は、「MOTIFシリーズ」に替わるヤマハの次世代フラッグシップシンセサイザーとしてリリースされました。

「MONTAGE」はコンセプト自体が「MOTIF」と異なるので、「MOTIF」でできることがすべて踏襲されているわけではありません。例えばシーケンサー機能については大きく異なっています。「MOTIF」では本体のみで楽曲の作り込みができるようになっていましたが、「MONTAGE」ではDAWが得意な機能はあえて搭載せず、パフォーマンスにフォーカスした仕様になっています。もちろんフレーズのアイデアを記録したり、ライブパフォーマンスで同期演奏やバックトラックとして使用したりできるMIDIシーケンス機能は搭載されています。
なお、「MONTAGE」は2016年に発売されて以来バージョンアップを重ね、さまざまな機能や音色の追加が行われました。音楽シーンが変化して新しい音色や音楽が作り出されていくように「MONTAGE」も進化していったのです。さらに2018年には「MONTAGE」の設計思想を反映しつつ、コンパクト&ライトウエイトの「MODX」がリリースされました。
「MOTIF」とは全く異なるコンセプトで、ライブパフォーマンスにフォーカスしたシンセサイザー「MONTAGE」は、現代におけるハードウェアシンセサイザーの役割は何か? という問いに対するヤマハが出した一つの答えといえるでしょう。
もう一度ステージピアノについて考える

可搬性と大音量を実現するステージピアノとして1976年に「CP-70」を発売してから43年後の2019年1月、ヤマハは全く新たなコンセプトのステージピアノを登場させます。その名も「CP88/CP73」。どこか「CP-80」と「CP-70」を思わせるような商品名です。この最新の「CPシリーズ」がどのようにできあがったのかを少し掘り下げてみましょう。
新しい「CPシリーズ」は、前述した「refaceシリーズ」を手掛けた開発プロデューサーが担当することになりました。自身がステージピアノユーザーではない彼は、ステージピアノを使用しているユーザー層を知ることから始めました。自社、他社関係なく、ステージピアノが使用されている現場に行き、さらにインタビューを行い、ステージピアノのユーザー像を捉えていきました。

この時に彼が感じたことの一つは、ヤマハのステージピアノを使用する人は多いが、「電源を入れてピアノの音を弾く」以外の使い方をしてくれる人が少ないということでした。それにもう一つ、同じステージピアノを使用している人の中でも、徹底的に鍵盤にこだわりを持つ層と、鍵盤タッチや鍵盤数にはあまりこだわらずに可搬性を優先する二つの層がいることにも注目しました。結果的に、可搬性を優先にしている人は、エレクトリックピアノ系を主体に演奏していることや、もう1台別のキーボードをセッティングし、2段鍵盤で演奏している人が多いことがわかりました。「ならば、それぞれの層に最適なモデルがあっても良いのでは?」と考えるようになりました。この考え方は「CP88」と「CP73」で使用している鍵盤の機構を変えている点(単に鍵盤数が違うだけではない)に反映されています。
こういった作業を通じて基本コンセプトが定まると、仕様やUIの方向性をまとめ、さまざまな開発セクションと連携して試作品を作り、具体的な検証を行っていきます。

中でも力を入れたのはUIに関する部分。まずアコースティックピアノとエレクトリックピアノ、そしてストリングスなどのその他の楽器を明確に分けて選択できるようにしました。また、演奏中の誤操作を防ぐためにボタンではなくトグルスイッチにするなど、機能ひとつひとつに適した操作子を選択し、さらには楽器ごとに適したパラメーターを近くに配置するなど、試行錯誤が行われました。また、ステージピアノを使用する層は、シンセサイザープレイヤーのように機械の操作に長けている人ばかりではないので、音色の選択や、レイヤー(ピアノにストリングスを重ねるなどの手法)、作成した音色の保存といった操作がマニュアルを読まずに簡単にできることも重要視しました。
「CP88/CP73」では製品の重量にも着目しました。まず、総重量が20Kgを超えるステージピアノでは、一人で運搬したりセッティングしたりすることが困難であることが挙げられます。加えて都市部では車を自分で運転する頻度も下がっているため、電車などを利用して楽器を運ぶことが多いプレイヤーは、おのずと軽めの楽器を好む傾向があります。このようなステージピアノを実際に利用しているユーザーの声を反映し、軽量化にも力を注ぐことにしたのです。当時すでに「CP4 STAGE」および「CP40 STAGE」で17Kg程度の重量を実現していたのですが、筐体にプラスティックを使用しているため、運搬やセッティング時に左右や角をぶつけてしまい、割れてしまうケースも見受けられました。またプラスティックの質感によりどうしても高級感が出ないため、「愛着を持って長く使用してもらう楽器としては別の素材がふさわしいのでは?」という検討を始めます。

浮上したのはアルミ素材を使用するアイデア。しかしアルミは軽量ではあるものの剛性が弱く、平面部分の多い鍵盤楽器に使用するにはそれなりの補強を行わなければなりません。そこで筺体の設計チームと協力し、徹底した構造検討の結果、現在のアルミ筐体が実現するのです。
また、サイズの面でもシビアに開発を行いました。通常、内部に収まる基板類はそのほとんどが操作面と平行に配置されるのですが、「CP88/CP73」ではアナログ系回路の乗った基板を垂直にレイアウトすることで、奥行きが大きくならない工夫がされています。

ハードウェアだけでなく、肝心のピアノサウンドについても徹底的に見直すため鍵盤とサウンドのマッチングを細かく調整し、評価、検証を重ねました。そして、エレクトリックピアノのサウンドについてはよりリッチなサンプリング波形を搭載するためにサンプリングを一からやり直しました。
このように「CP88/CP73」はUI、筐体、音源、すべて過去の「CPシリーズ」の延長ではない、ゼロベースで開発が進んでいくのですが、鍵盤数の違う2モデルを出すという商品ラインナップの具現化が進められました。前述のユーザー調査の通り、鍵盤にこだわりを持つ層にはグランドピアノと同様なタッチと鍵盤数が必要で、エレクトリックピアノ系音色を主体に演奏し可搬性を優先する層にとっては、もう少しライトなフィーリングの鍵盤で、しかも鍵盤数は88まで要らないということが判っていました。そこで、88鍵モデルにはNW-GH3鍵盤(木製象牙調/黒檀調仕上げ、グレーデッドハンマー)を、73鍵モデルにはBHS鍵盤(黒鍵マット仕上げバランスドハンマー)が採用されることになりました。さて、このように「CP88/CP73」は新しい価値観を持ったステージピアノとしてリリースされるのですが、もう一つ新しい取り組みが行われています。それは楽器に最適化されたソフトケースの開発です。これまでも製品ごとにサイズやクッションなどを調整したソフトケースが作られていたのですが、使用するユーザーを徹底的に調査して作り上げた「CP88/CP73」であるが故にソフトケースの役割は非常に大きく、生地や重さ、収納や取り回しなどを考慮した使い勝手の良いソフトケースに仕上げました。

「reface」、「MONTAGE」、「CP88/CP73」と2015年以降のシンセサイザーおよびステージピアノ開発は、電子楽器でありながら技術の進歩だけに頼らず、音の楽しみ方や新しい音楽表現、さらには楽器としてのあるべき姿を具体化するために、すべてをゼロベースで見直してみる…そんな手法で進んできました。