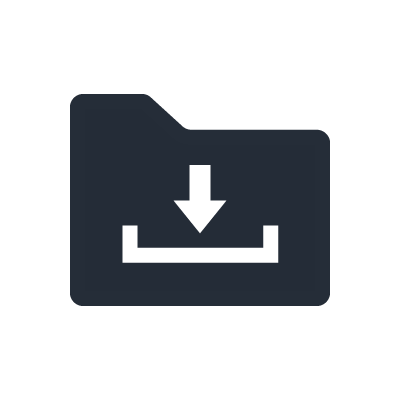【第7章】音を創造する楽器
発音の原点をテクノロジーで突き詰める

2020年2月、ヤマハは新開発のVCM(Virtual Circuitry Modeling)オルガン音源を搭載した「YC61」を発表します。その翌年には、「YC73/YC88」をリリースし、3モデルがそろいます。シンセサイザーというよりはステージキーボードというカテゴリーに分類される商品なのですが、VCMオルガン音源に加え、AWM2音源、FM音源も搭載しており、内部的にはシンセサイザーそのものといった仕様になっています。YCという型番はバンド向けのコンボオルガンとして1969年にリリースされた「YC-10」を筆頭に、70年代のバンドブームを支えたキーボードで、同じ電子オルガンであっても「エレクトーン」とは異なるコンセプトのものです。とはいえ、70年代のYCシリーズの発音方式は、当時のエレクトーンに採用されていたものを応用したものでした。しかし、50年の歳月を経てYCシリーズとして新たな音源方式VCMを搭載することになったのです。
実は、このVCMオルガン音源のベースになっているVCMという技術は、1987年にスタートした「K’s Lab」での研究から始まります。K’s Labとは、情報科学博士であるDr. Kこと国本利文氏が率いるヤマハ社内の研究チームで、FM音源、AWM音源の商品化後の、次世代音源システムを開発するために結成されました。ここで研究されていたのは1993年に「VL1」に搭載されたVA(Virtual Acoustic)音源で、アコースティック楽器が発音する原理(物理現象)を計算式で導き出すという画期的な取り組みでした。ただ、サクソフォンのような円錐管楽器の音響特性を計算で導き出だそうとすると、計算式が膨大な量になってしまい、当時のDSP(Digital Signal Processor)技術では音源として実用化することが現実的ではありませんでした。そんな中、K’s Labが注目したのは1977年に発表されていた「分岐管理論」(注1)という論文でした。これは円錐管の音響特性は2本の円筒管で近似できるというもので、口径が一定な円筒管であれば計算式も単純化でき、音源システムとしても現実味がありました。これがVA音源のリリースにつながっていきました。ちなみに、この「分岐管理論」は電子的なシミュレーションに活用されているだけでなく、ヤマハが2017年に発売、日本ではグッドデザイン大賞を受賞したカジュアル管楽器「Venova(ヴェノーヴァ)」(アコースティック楽器です)にも応用されています。

注1:
「円錐ホーンの反共振周波数の球面波理論による解析-円錐形管楽器の鳴る周波数」(実吉純一、1977年)
さて、K’s LabではVA音源のリリース後もアナログシンセをDSPで再現した「AN1x」(1997年)やハイブリッド音源システムのExtended Synthesisを搭載した「EX5」(1998年)など、さまざまな音源の開発を手掛けていきますが、2001年ごろからアナログ回路の物理モデルを用いたエフェクトの開発を進めることになります。
アナログ回路とはコンデンサーやトランジスターなどを組み合わせたものですが、同じ容量や増幅率をもつ素子でもメーカーや型番ごとに微妙な違いが生じます。特に音の信号のような周波数が変化する電気信号の場合は、素子が持つ周波数特性によって音への影響が大きく変わります。つまり、アナログ回路で作られたエフェクターは同じ機能を持ったものでも使用している部品や回路の組み方によって音が変わるのです。これがミュージシャンやエンジニアがその製品を好む理由、重要な選択肢の一つになっているのです。

K’s Labはこのアナログ回路の挙動を研究し、ヤマハの業務用デジタルミキシングコンソールである「DM2000」(2000年)をはじめ、いくつかのミキシングコンソール向けに物理モデルを用いたデジタルエフェクトを開発します。これがVCM=Virtual Circuitry Modelingと名付けられた最初の製品になります。その後VCMの技術はOpen Deckと呼ばれるテープレコーダーの録音や再生における音質の挙動(回転ムラなども含む)をシミュレートした技術を完成させ、さらにはルパート・ニーヴ氏のRND社(Rupert Neve Designs社)とのコラボレーションによって生まれたPorticoプラグインエフェクトなど、さまざまな製品に活用されながら進化を遂げました。
そんな中、「YC61」の開発者はこのようなアナログ回路、及び物理現象のさまざまなシミュレートをDSPで再現する技術を、新たなオルガン音源の開発に応用しようと考え、トーンホールタイプのオルガン音源をシミュレートする際にVCM技術を応用することに着目します。

そもそもトーンホイールタイプのオルガンとは、電子部品の発振器を用いたオルガンと異なり、金属の歯車を回転させ近くに設置したピックアップとの間に生まれる電磁誘導効果を利用する発音原理を用いたものです。エレキギターを思い浮かべてみましょう。エレキギターの場合はピックアップの上で弦が左右に振動することによって電磁誘導が起き、電気が流れます。そして、弦の振動周波数が高ければ音は高くなります。トーンホイールは歯車のギザギザによってピックアップとの距離が変わるため、歯車が回転し続けている限り、弦が左右に振動しているのと同様の効果が得られます。同じ回転数であれば歯車のギザギザが細かいほど振動周波数が高くなり、同じ歯数であれば回転数が高いほど周波数が高くなるので、音の高さは歯車の回転数か歯の数で調整できることになります。
実際のオルガンでは、音程(音階)ごとに必要な周波数のトーンホイールを用意し、さらに各音の倍音を奏でるトーンホイールを組み合わせ、それらの音量をドローバーと呼ばれるレバーで調整して音を作ります。このようにトーンホイール方式のオルガンは、歯車が回転するという機械的な要素が絡むため、回転ムラや歯車の物理的な形状ムラなども音に影響を与えます。さらに磁石とコイルを使用したピックアップで音を拾うため、使用する磁石やコイルの巻き数、線の太さなど、複数の要素が加わります。これらのパラメーターをDSPで計算させるためにVCM技術を応用し、よりリアルなオルガンサウンドを追求したのが「VCMオルガン音源」ということになります。
また、「YC61」では、VCMオルガン音源以外にもVCM技術を応用しています。オルガンというとレスリーに代表される回転スピーカー(ロータリースピーカー)を搭載したアンプで音を出すのが一般的ですが、「YC61」ではこの回転スピーカーサウンドをVCMロータリースピーカーというエフェクトでモデリングしています。この他にもフェイザーやフランジャーなど、ビンテージエフェクトとしてプロの間でも好まれているアナログエフェクト的なエフェクトとして、「VCMエフェクト」を採用しています。

さらに、「YC61」はFM音源によるオルガンサウンドも搭載しています。もともとFM音源のオペレーターと呼ばれる発振器(あくまでデジタルですが…)からは非常にきれいな正弦波が得られます。これを活用してエレクトーン音源でも使用されていたトランジスター発振器でオルガン音源を再現しています。計6タイプのFM音源オルガンを搭載し、8本のドローバーはキャリアだけでなく、モジュレーターとフィードバックの2つにも対応。伝統的なドローバーを使用して全く新しいFMオルガンのサウンド楽しめるようになっています。VCMオルガンもFMオルガンもデジタル回路によるものですので、「YC61」は50年以上前から使用されてきた電気オルガン、電子オルガンのサウンドを完全にデジタル化して再現したといえるでしょう。
「YC61」の取り組みは、音源部分だけにとどまりません。冒頭に触れたステージキーボードという役割を徹底的に追求し、ユーザーインターフェースにもこだわりました。これまで多くのシンセサイザー/キーボードでは音色を選択したり編集したりするユーザーインターフェースを一つだけ持ち、ボタンやダイヤルなどで音色を切り換えていたのですが、「YC61」ではオルガンセクション、「KEY-A」「KEY-B」という3つのセクションを持ち、それぞれに好みの音色を用意しておいた上で、それぞれをオン/オフできるというユーザーインターフェースを採用しました。視覚的にわかりやすくなったことで、キーボーディストがバンドアンサンブルの中で使用頻度の高いピアノ、エレクトリックピアノ、オルガンといったサウンドをあらかじめ用意した状態で切り換えやすくなり、また、ピアノの音色にエレクトリックピアノを瞬時にレイヤーする、オルガンサウンドで演奏中にスプリットで用意したシンセ音色を切り換えるといったことも簡単に行え、よりライブ向きの使い方ができるようになりました。これは、同時期に開発されていた「CP73/CP88」のコンセプトと同じもので、その後に発売されるステージキーボード「CK61/CK88」にも受け継がれています。

シンセ50周年に先駆けMONTAGE Mをリリース
2016年に発売されたフラッグシップシンセサイザーの「MONTAGE」は、AWM2音源とFM-X音源を搭載したハイブリッドシンセサイザーでした。7年の歳月を経て、ヤマハは2023年10月、「AN-X音源」という新しい音源を追加して「MONTAGE M」をリリースします。AN-X音源を含めて3種類の音源が搭載されることになり、ハイブリッドからマルチ音源への進化という意味を込めてMulti(マルチ)のMが追加され「MONTAGE M」と名付けられました。

新たに追加されたAN-X音源はアナログシンセをデジタル技術で再現するバーチャルアナログモデリングというタイプですが、1997年に発売された「AN1x」に搭載されていたAN音源(こちらもバーチャルアナログモデリング)と比較すると、その中身は大きく進化しており、「MONTAGE」の多彩なリアルタイムコントロールと組み合わせて複雑な音色変化が得られるようになっています。

まず、基本構造として「AN1x」では2つだったオシレーターを3つに増やし、これとは別にノイズオシレーターも搭載しています。LFOも2つから7つに拡張され、フィルターもデュアルタイプに進化しています。フィルターがデュアルになったことで、ハイパスフィルターとローパスフィルターを同時に使用する、ローパスフィルターのピーク部分を2カ所作り、それぞれを独立して動かしたりするといった複雑な音作りも可能になりました。さらにオシレーターごとにフィルターの後ろに直接ルーティングする機能もあるため、特定のオシレーターにフィルターをかけないような音作りも可能です。また、オシレーターのピッチやフィルターカットオフのばらつきなどをシミュレートするVoltage Drift(電圧変動による揺らぎ)とAgeing(機器の古さ、新しさ)というパラメーターを装備するなど、よりアナログライクなシミュレートが追求されています。さらに、オシレーターの位相をキーオンでそろえるのか、あえてずらすかの設定や、各オシレーターのピッチのばらつきをあえて設定するなど、細部に至るまでリアルなアナログシンセサイザーの挙動がシミュレートされており、デジタルシンセサイザーでありながら温かみのあるサウンドを奏でられるように作られています。

また、AWM2音源も初代「MONTAGE」より大幅に進化しており、Element(エレメント)数が8から128に引き上げられています。通常時は8のままですが、Elementを増やす設定をすることで、複数Partを使用しなくても8種類以上の波形を同時にレイヤーして鳴らす、鍵盤ごとに全く異なる楽器音を並べた音色を作成する、鍵盤ごとに異なる和音を奏でられる音色を作成するといったさまざまなアプローチができるようになっており、音作りの自由度が高まっています。
さらにElementsの活用方法も楽器としての表現力を深める鍵となっています。「XA Control」と呼ばれるElementの鳴らし方を設定するパラメーターを使用して、例えば、レガートで弾いたときだけに鳴るElementや、鍵盤を離したときに鳴るElementなどを設定することで、より生楽器に近い演奏時のノイズ的なサウンドなども追加することができます。この他にも同じ楽器音でありながら微妙に異なる波形をランダムに再生させることで音のばらつきを再現させるといったことも可能になります。
「MONTAGE M」では音色の保存方式もこれまでとは異なっています。音色の基礎となるのはAN-X音源、FM-X音源、AWM2音源の中から1つを選択して使用できる16個のPart(パート)とよばれるもので構成されているのですが、これをひとくくりにしたPERFORMANCE(パフォーマンス)という単位で音色を保存しています。「MOTIFシリーズ」まではVOICE(ボイス)モードとPERFORMANCE(パフォーマンス)モードというのが明確に分かれていて、ボイスモードはピアノの音色、オルガンの音色、シンセの音色といった具合に一つひとつの音色を切り換えて使うモードで、PERFORMANCEモードはVOICEモードの音色を複数パート集めて奏でる、いわばレイヤーサウンド的なものという位置づけでした。このVOICEとPERFORMANCEの関係は、音源部がマルチチャンネル(マルチパート)になったあたりから、ボイスとマルチという形で音色を保存する形式が導入されていましたが、「EX5」からは明確にボイスとパフォーマンスという名称を使用するようになり、ヤマハシンセサイザーの音色保存方式の代名詞になっていました。しかし、「MONTAGE」からはボイスという単体パートの保存方式を止め、すべてPERFORMANCEとして保存する方式に変更しました。
「MONTAGE M」では、PERFORMANCEに含まれる各パートの音源をAN-X音源、FM-X音源、AWM2音源の中から自由に選択できるようになっており、例えばパート1をAMW2のピアノ音色に、パート2をFM-Xのエレクトリックピアノに、パート3をAN-Xのパッドサウンドに設定しておけば、アコースティックピアノ+エレクトリックピアノ+シンセパッドのレイヤーサウンドを作ることができます。こうすることで、すべての音源システムをオシレーター的に組み合わせた音作りを実現し、モーションシーケンスやSuperKnob(スーパーノブ)を使用すれば、パートをまたいだパラメーターを同時にコントロールできるため、リアルタイムな音色変化に対しても音源システムの垣根を越えたアプローチを提供することが可能なシステムに仕上がっています。

音色から音色を作る「Smart Morph」
「Smart Morph」という機能(注2)は、2つ以上の音色を「MONTAGE M」が機械学習し、それぞれの音色に含まれる要素をもった新しい音色をつくりだすというもので、その操作もグラフィカルにできるようになっています。
例えば、Aというシンセパッド系の音色と、Bというエレピ系の音、Cというシンセブラス系の音があったとします(FM-X音源のみ、またはAN-X音源のみの選択となります)。これを「Smart Morph」 のEdit画面で登録し、「Learn」というボタンを押すと、XYパッドのような画面にカラーで機械学習の結果を表示します。この画面では、各音色から線と白い四角が表示され、その中で左上に青い四角が一つだけ表示されます。画面をタッチするとその青い四角が移動できますが、Aのシンセパッドから伸びている白い四角の位置に青い四角を持ってくると、シンセパッドの音色が鳴り、Bのエレピから伸びている白い四角の位置に移動するとエレピの音色がなります。A、B、Cの中間点に移動すると、それぞれの音色が持つ要素を加味した音色を「MONTAGE M」が自動的に生成し、鳴るようになります。それぞれの音色の影響は画面上の色で表現されており、エレピの音Bの音色に近い色の方に移動すればエレピの要素が強くなります。
このように既にある音色をベースに新しい音色を作成することもでき、さらにマップ内(XYパッドのような画面)の青い四角の位置をSuperKnobでリアルタイムに変化させることもできるので、より複雑な音色作りを行うことができます。
注2:
「Smart Morph」はMONTAGE OS v3.5以上、およびMONTAGE Mに搭載(FM-X音源のみ)。MONTAGE M OS v2.0以上でAN-X音源でも使用可能。
ユーザーインターフェースの進化
音源システムの高機能化や音作りにまつわる新しい機能が搭載され、これらを組み合わせることで新たな音色を作成できるようになると、一方ではこれらを使いこなすための操作がより複雑なものになってしまうという問題も生じます。もちろん、タッチ機能付きカラーディスプレイを採用することで操作性、視認性の大幅な改善は可能なのですが、「MONTAGE M」ではさらなるアイデアを盛り込んでいます。
まず、本体中央部のメインディスプレイですが、ディスプレイをタッチするだけで音色を切り換えることができるだけでなく、音色の種類を選択して検索する「カテゴリーサーチ」に関しても、プルダウンメニュー式ではなく、パネルをタッチするだけでカテゴリーを選択できるようになっています。また、これらのディスプレイ切り換えおよびタッチボタンが本体右側にある「LIVE SET」、「CATEGORY」、およびその下の16個のボタンとリンクするようになっており、どちらを使用しても切り換えることができ、ボタンのLED点灯とディスプレイのハイライトも常にリンクするようになっています。
また、音色をエディットする際に役立つ工夫も施されています。例えば、AN-X音源の音色を編集する場合、オシレーターセクションだけでも3種類あり、それぞれにピッチやLFOの設定、パルス幅の設定や変調設定など、詳細なパラメーターが存在するため、一つの画面では表示しきれません。そのため一般的には、オシレーターごとの画面になっており、オシレーター間の移動はボタンやプルダウンメニューで行います。さらにフィルターセクションやアンプセクション、エンベロープの設定などを加えると階層も複雑になり、ユーザーが目的のパラメーター画面にたどり着くのが困難でした。その解決策として、「MONTAGE M」では本体右側部分に「NAVIGATION」というボタンを配置し、このボタンを押すだけで編集中の音色ブロック図をメインディスプレイに表示できるようにしています。このブロック図に戻れば、編集したいパラメーターがあるセクションを一目瞭然で確認できるので、メインディスプレイに表示されたセクションをタッチするだけで目的のパラメーターにたどり着くことができます。

さらに、「MONTAGE M」では本体左上にサブディスプレイを設けており、メインディスプレイの補完として機能するようになっています。このディスプレイは上部の8つのボタンと左横の「PAGE」ボタンおよび下部の8ノブと「QUICK EDIT」ボタンで操作できるようになっており、メインディスプレイで選択した音色のさまざまなパラメーターをメインディスプレイと独立して表示することができます。また、サブディスプレイの表示配列にも特長があり、メインディスプレイでは、AWM2、FM-X、AN-X、それぞれに独自のレイアウトで表示されるのに対して、サブディスプレイでは、シンセサイザーの基本的な信号の流れである「オシレーター」「フィルター」「アンプ」の配列が、AN-X音源、FM-X音源、AWM2音源のどの音源システムでも統一されており、直感的な音色エディットができるようになっています。
この他にもパネル上のボタンスイッチに色の変わるLEDを採用しており、ボタンの機能が切り替わったことを表現するなど、多機能、かつパラメーターの多いシンセサイザーを少しでも分かりやすく使っていただくというユーザー目線の開発が施されています。
50年目に「MONTAGE M」は2.0へ
ヤマハシンセサイザー50周年という節目の年に、「MONTAGE M」のOSはバージョン2.0にアップデートされました。このアップデートには、2022年に発表されたヤマハのフラッグシップ コンサートグランドピアノ"CFX"の波形や、近年耳にすることが多くなった「Shimmer Reverb(シマーリバーブ)」エフェクト、これまでFM-X音源にしか対応していなかったSmart Morph機能をAN-X音源でも使えるようにするなど、さまざまなアップデートが行われました。加えてもう一つの2.0をご紹介しましょう。それは、「MIDI 2.0」プロトコルへの対応です。
MIDI 2.0は2019年の発表以降、実にヤマハとしては初めてのMIDI 2.0対応シンセサイザーの登場となります。MIDI 2.0は、これまで8bit転送だったMIDI情報を、32ビットから128ビットのパケットを使用して転送するもので、各データの解像度もMIDI 1.0と比較し大幅に向上しています。例えばボリューム情報などを転送するためのコントロールチェンジというデータを例に挙げると、これまでのMIDI(MIDI 1.0)ではデータエリアを7ビットしかとれなかったため、2の7乗=128段階の解像度でした。ピッチベンドなどのデータでは、7ビットのバイトを2つ組み合わせて14ビットにしてデータをやりとりするのですが、最大の解像度は16,384段階となります。これに対し、MIDI 2.0では32ビットのデータエリアを確保できるため2の32乗=4,294,967,296段階、すなわち約43億段階というとてつもない数字になります。ベロシティーに関しても16ビット=65,536段階なので、表現力が格段に向上します。

ただし、これは規格上再現できる数値の話で、実際の機器ではここまで解像度があるわけではありません。しかし、「MONTAGE M」のSuperKnobの値は0から1023までの1024段階、MIDI 1.0の128段階では「MONTAGE M」のパラメーターを再現できないわけですから、MIDI 2.0への対応は非常に重要な機能といえます。これまで使われてきたMIDI 1.0規格は1982年に誕生し、ヤマハでは翌年の1983年に発売された「DX7」に初めて搭載されました。そこから40年以上もの間、電子楽器の表現力はMIDI 1.0の7ビットまたは14ビットでの表現で十分とされてきました、ついにさらなる解像度を必要とする、次の時代に突入したといえるでしょう。
「MONTAGE M」のバージョン2.0のOSでは、ベロシティー、アフタータッチ(ポリ、チャンネル)、SuperKnob、ピッチベンドホイール、モジュレーションホイール、8ノブ、8フェーダー、フットコントローラー、サスティンといったパラメーターが10ビット=1024段階の解像度に対応しています。つまり、この機能をDAWなどのソフトウエアと組み合わせて最大限に活かす場合には、MIDI 2.0での接続が必要になります。もちろん、「MONTAGE M」本体だけで使用する場合には、クオリティを落とさないまま作業できます。

また、この高解像度MIDIの機能を最大限に生かすため、「MONTAGE M8x」では、新しい鍵盤機構を採用しています。これまでのFSX鍵盤では、鍵盤が押し込まれる間にいくつか感知接点を設けて、その接点間の通過速度を検出することでベロシティー値を算出していたのですが、「MONTAGE M8x」に搭載されているGEX鍵盤では、鍵盤本体と鍵盤下部分の双方にコイルを取付け、2つのコイルの距離によって発生する電磁誘導効果を使ってベロシティーを検出するようになっています。鍵盤が押されればコイルとコイルの距離は近くなり、コイルの両端に発生する電圧に変化(近づくと電圧が下がり強い音が発音する)が生まれるという原理です。これにより、鍵盤位置(垂直方向にどのくらい押し込まれているか)の検出が複数の接点によって滑らかな解像度をもつものに変わり、より微細なベロシティーを表現できるようになりました。また、通常鍵盤を押し込んだ状態よりさらに深く押し込んだ際に検出されるアフタータッチの検出も、鍵盤ごとのコイル間距離で検出できるため、ポリフォニックアフタータッチにも対応しており、GEX鍵盤はまさに解像度が飛躍的に高まったMIDI 2.0時代にふさわしい鍵盤機構といえます。
シンセサイザーは、アナログかデジタルか、AWM2かFMかといった音源システムの構造に注目が行きがちですが、ユーザーインターフェースや鍵盤機構など演奏者に寄り添った商品開発がシンセ誕生から50年経った現在でも脈々と進化し続けているということは、まさにヤマハがシンセサイザーを楽器として捉え、こだわり続けている証しなのではないでしょうか。
ソフトシンセとハードウエアシンセの新しい関係を提案
DAWソフトウエアを使用した音楽制作が主流になって以来、ソフトウエアシンセサイザーとハードウエアシンセサイザーの関係をどう考えていくのか…ということについては、さまざまな変化がありました。
音楽制作の現場においては、DAWを使用した制作スタイルが主流になったため、制作現場でのハードウエアシンセサイザーは、マスターキーボードとしての役割と、作曲者やアレンジャーがモチーフを試すためのアイテムという立ち位置が強く、「MOTIF」というシンセサイザーはまさにこの思想を反映させたものでした。
また、オーディオインターフェース機能を搭載した上で、ハードウエアシンセサイザーの音をソフトウエアシンセサイザーのように使える機能を持たせたエディターソフトウエアを提供するという取り組みもあったのですが、やはりライブはハードウエアシンセサイザー、制作はソフトウエアシンセサイザーという考え方が払拭できません。近年ではコンピューターのスペックが向上し、ライブパフォーマンスにおいてもソフトウエアシンセサイザーを使用するミュージシャンも増えてきており、まさにハードウエアシンセサイザーが窮地に追いやられている感さえあります。

そんな中、ソフトウエアシンセサイザーとハードウエアシンセサイザーの関係を新たな時代へと導くものとして登場したのが、「Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M」、通称「ESP」と呼ばれるソフトウエアです。
これは、「『MONTAGE M』をソフトウエアシンセサイザーにしたもの…」と言ってしまえばそれまでなのですが、ポイントはその戦略にあります。このソフトウエアシンセサイザーは、「MONTAGE M」の正規ユーザーであれば無料で使用できるもので、単体での販売はありません。また、シンセサイザー本体をドングルのように使用するものではないので、「MONTAGE M」がその場になくても動作します。これは、プロミュージシャンにとって非常に重要なことで、次の2つのケースで有効活用できます。
1. 自宅が制作現場で、歌入れやミックスダウンの際にスタジオに移動することが多いミュージシャン
このパターンは非常に多いと思われます。自宅で使用している「MONTAGE M」を持ち出さずとも、全く同じ音をDAW内で使用できます。また、これまではハードシンセをスタジオに持ち込まなくて済むようにオーディオ化したプロジェクトを持ち込む場合が多く見られますが、ミックスダウン時に音色を変えたいとなると大変です。大幅に変えるならば別のプラグインシンセを使用する選択肢もありますが、「ほんの少しリリースを長くしたい…」といった編集には、ESP上で編集できる利点があります。
2. ツアーにも出つつ、レコーディングも行うミュージシャン
ツアー中に同じアーティストのレコーディングに参加するような場合、機材が地方や海外に移動しており、使用できないという悩みを抱えるミュージシャンも多くいます。そのため、ツアー用とレコーディング用と同じ機材を複数購入するミュージシャンもいるようですが、これもESPで解決できます。さらにレコーディングしたばかりの新曲をツアーで披露する際に、レコーディングに使用した音色をそのままツアー用の「MONTAGE M」にロードできるという利点も生まれます。
このように、ESPはハードウエアシンセサイザーとソフトウエアシンセサイザーの利点を融合させ、どちらを使用してもユーザーに利点が出るように考えられています。「MONTAGE Mの正規ユーザーであれば無料」と書くと、オマケのようなイメージになってしまいますが、ハードウエア本体もソフトウエア「Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M」も合わせともに、「MONTAGE Mシンセサイザー」であるという考え方です。これがシンセサイザー50周年を迎えるヤマハが出した、現時点でのハードウエアシンセサイザーVSソフトウエアシンセサイザー論に対する回答なのです。
次の50年へ
1974年の「SY-1」発売から50年、エレクトーンの表現力を増すというプロジェクトから始まり、音源システム、鍵盤機構、ユーザーインターフェース、音響技術など、数多の技術革新を行い、2024年リリースの「MONTAGE M V2.0」までたどり着きました。
理想を現実にするために真摯に粘り強く挑戦し続け、独自の技術を世にリリースする力を持ったヤマハだからこそ作り出してきたシンセサイザーが、この50年間の歴史に詰まっています。「シンセサイザーは音を創造する楽器である」という信念のもと、先人が培ってきた多様な、多彩な技術を継承し、それをその時代にふさわしく、かつ期待を超えるものを革新的に製品化していくヤマハの思想は何なのでしょうか。その一つは「ヤマハの技術で音を創造する楽器を作る」という強い志なのかもしれません。この志を常に持ち続けることが、次の50年、さらにはその先のシンセサイザー史を塗り替えるような技術にたどり着くための原動力になるのではないでしょうか。