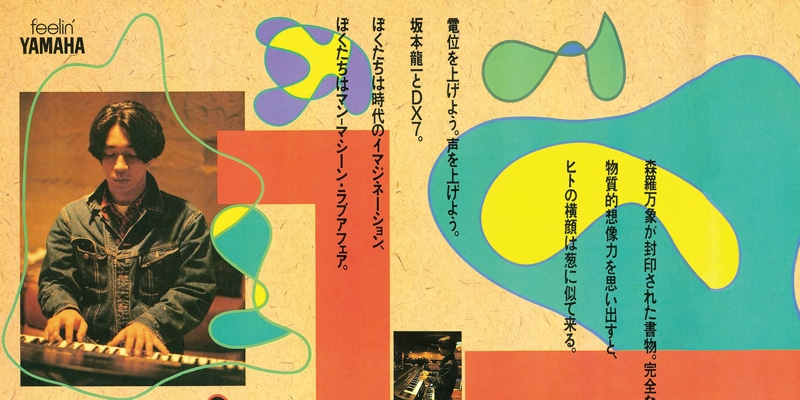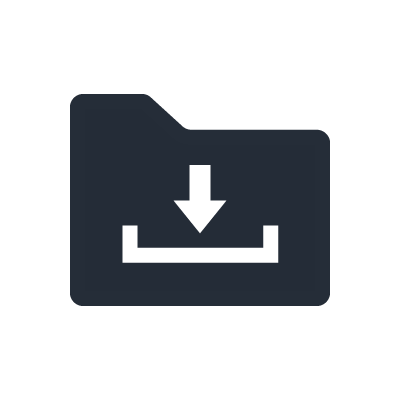MUシリーズ
究極のPCM音源として進化

「SYシリーズ」をはじめとする音楽制作用シンセサイザーが普及しだした1990年代、世の中はPCMシンセサイザーがブームとなり、鍵盤を搭載してないラックタイプやデスクトップタイプのシンセサイザーもPCMタイプのものが数多くリリースされていきます。それまでラックタイプというとキーボーディストの拡張音源としてエフェクトやミキサーなどを入れたラックの中に組み込んで使用するというのが一般的でしたが、生楽器の音がリアルに出せるPCMシンセサイザーが低価格で普及し始めると、コンピューターミュージック用の音源として重宝されるようになります。

90年代はコンピューターメーカーが個人向け(家庭向け)低価格コンピューターの販売に力を入れていたこともあり、特に日本国内では急激にコンピューターが普及していきます。趣味層もコンピューターを用いて音楽制作を行うようになり、机の上で音楽を制作することからデスクトップミュージック(DTM)と呼ばれるなど独特の文化を創り上げました。このDTM市場において、ヤマハは、「SYシリーズ」の音源モジュールである「TGシリーズ」をベースに、「TG100」「TG300」といったコンピューターミュージック用の音源をリリースしていきます。

実はこの当時、「DX7」に搭載されて以来、シンセサイザーには必須とされてきたMIDI規格に新たな動きが生じます。それはGM(General MIDI)です。GMとはメーカーの垣根を越えてシンセサイザーの音色配列を標準化したもので、プログラムチェンジと呼ばれる音色切り替えのメッセージに対して、1番はピアノ、30番はオーバードライブギターなど、音色を規定することで音楽データ(MIDIで作られた楽曲データ)の互換性をもたらすものです。これによりMIDIで作成された楽曲を再生する際に、どのメーカーのシンセサイザー音源を使用してもある程度アンサンブルを保つことができるため、音楽データのみの販売や、アマチュア同士の楽曲データの交換などが流行し、DTMブームをさらに加速させたのです。
しかし、GM規格では幅広い互換性を持たせるために規定されている項目が限定されており、音色数も128音色+1ドラムキット、エフェクトの規定もほとんど無いという内容であったため、表現力という点においては厳しいものがありました。
日本国内ではすでに他社がリリースしていた独自の音源規格が浸透しており、DTMユーザー向けのMIDI楽曲集などはその規格に基づいたものが数多く流通していました。こういった状況の中、ヤマハでもこれらの規格を凌駕した新たな仕様を提案する動きが出始めました。これが1994年に発表された「「XGフォーマット」」という共通仕様です。


「XGフォーマット」は音色およびエフェクトの詳細なパラメーターに至るまで、データと音源の双方を規定したもので、「XGフォーマット」に基づいて制作されたMIDIデータであれば、XG対応音源を使用することでほぼ同じニュアンスで演奏を再現することが可能です。また、高音質な上位機種用に作成されたデータを下位モデルで再生した場合にも破綻しないようになっており、幅広い層に「XGフォーマット」の音楽データを普及させることができるというのも魅力の一つです。この「XGフォーマット」に初めて対応したのが、1994年に発売された「MU80」という音源モジュールです。

「MU80」は高音質のPCM音源という側面だけで無く、内蔵エフェクトを自在にかけることができるA/Dインプット(ギターやマイクなどを繋ぐ端子)を装備するなど、一台でカラオケやギター練習ができる画期的なモデルとして話題となりました。その後、後継機種の「MU90」が発売された後、次世代の本格音源モジュールとして「MU100」を発表します。

「XGフォーマット」は拡張性も備えた共通仕様であったため、音源側も自在に進化させることが可能でした。そこで「MU100」ではプラグインボードと呼ばれる音源拡張のためのシステムを導入し、さらに表現力を増したモデルになっています。

これらの「MUシリーズ」はDTM市場を意識してハーフラックサイズのコンパクトなボディに納められていましたが、音源モジュールをラックに収めて利用する層が多い北米市場を意識し、「MU100R」というラックマウントタイプの音源もリリースしています。この「MU100R」はプラグインボードを2枚同時に使用できる点から非常に重宝され、日本国内に置いても非常に評価の高い音源となりました。

このように「MU80」以来、「XGフォーマット」に対応したDTMユーザー向け音源市場は活性化し、毎年のように新製品を投入していきます。「MU100」の翌年には最大同時発音数を「MU100」の2倍にあたる128音ポリフォニックにした「MU128」を発売。このモデルでは同時に使用できるパート数も64パートになっているほか、筐体をハープラックのまま縦に大きくし、プラグインボードを3枚装着できるようにするなど、大幅な改良がなされています。
さらに翌年には「MU1000」「MU2000」を発売。当時GM規格の拡張版として制定されていた「GML2(GMシステムレベル2)」に対応したほか、「MU2000」は本体を簡易サンプラーとして使用できる機能を搭載するなど、DTM層向け製品とは思えない本格的なシンセサイザー音源に仕上がっています。
「MUシリーズ」はDTM市場の縮小などを受け、2000年に発売された「MU1000」の廉価版「MU500」を最後に終了しますが、DTM市場においては現在でも愛用者の多い音源の一つです。また、「MUシリーズ」で培われた技術は、日本文化の象徴ともいえる「カラオケ」の再生用音源や電子ピアノの伴奏用音源に活用されるなど、さまざまな場面で活き続けています。
「MUシリーズ」の陰の立役者「プラグインボード」

プラグインボードとは、本体内部に拡張用の基板を装着することで音源やエフェクトを増設できる機能で、「MU100」が発売された際に本編でも解説した「PLG100-SG」をはじめ、VL音源の「PLG100-VL」や任意のパートにハーモニーエフェクトを加えたりボコーダーとしても利用したりできる「PLG100-VH」を同時に発売しています。
その後「DX7」と同様のFM音源システムを持つ「PLG-100DX」や「MU50」と同等のスペックをもつ「PLG100-XG」が発売されており、「MUシリーズ」のみならず、1990年代後半から2000年代中盤にかけて、ヤマハシンセサイザーにとっても重要な役割を果たしていきます。
1999年には「PLG150」という型番で刷新され、VA音源の「PLG150-VL」、FM音源の「PLG150-DX」、Analog Physical Modeling音源の「PLG150-AN」がリリースされ、「S80」「CS6x」などのシンセサイザーにも対応しているほか、2001年にリリースされる「MOTIFシリーズ」でも活用できるようになっています。その後、ピアノ音源の「PLG150-PF」および「PLG150AP」、パーカッション音源の「PLG150-DR」「PLG150-PC」がリリースされており、このプラグインシステムはDTMユーザーだけで無く、多くのシンセサイザーユーザーに愛用されました。