
今月の音遊人
今月の音遊人:塩谷哲さん 「僕の作る音楽が“ポップ”なのは、二人の天才音楽家の影響かもしれませんね」
8736views


【クラシック名曲 ポップにシン・発見】(Phase36)武満徹の歌は仮面か素顔か、安部公房「他人の顔」の映画音楽「ワルツ」
この記事は5分で読めます
4513views
2024.11.21
tagged: 武満徹, 音楽ライターの眼, クラシック名曲 ポップにシン・発見, 安部公房
武満徹(1930~96年)は戦後日本の前衛音楽を代表する作曲家だが、親しみやすい歌も書いた。2024年に生誕100年を迎えた安部公房の小説「他人の顔」の映画音楽「ワルツ」は、シャンソン風の哀愁漂う歌。ショスタコーヴィチやハチャトゥリアンら20世紀の妖艶なワルツの系譜も思わせる。前衛音楽とポップソング。武満の仮面と素顔はそれぞれどちらか。旋律という顔を失った現代音楽から調性音楽への回帰だとしたら、作曲家の苦闘はますます「他人の顔」に似てくる。
勅使河原宏監督の映画「他人の顔」(1966年)は、安部公房自らが脚本も書いた。研究室で液体空気が爆発し、顔じゅうがケロイド瘢痕となり、顔を失ったと思い込んだ主人公の男性。彼が他人の顔としてプラスチック製の仮面を作り、他人に成りすまして自分の妻を誘惑するという話。小説では男性が自分で仮面を作るが、映画では精神科医が製作する。医師は男性に仮面を被せて劣等感の穴を埋めてやった後、仮面劇を観察し、精神分析をしようとする。
おどろおどろしい人体の模造品の映像から始まった後、オープニング曲として入る武満の「ワルツ」が清冽な渓流のように美しい。弦楽が憂愁に満ちたハーモニーを繊細に添えながら、世にも美しい旋律が淀みなく流れていく。武満の初期の傑作「弦楽のためのレクイエム」(1957年)が想起される。当時全盛だった無調を徹底しておらず、美しい旋律も感じられるこの曲を、ストラヴィンスキーは「実に熱情的な(intense)音楽」と言って称賛した。「ワルツ」では生死を賭けた熱情をより魅力的な旋律とリズムで表現している。
Face of Another (1966) Waltz
しかしこれは弦楽のためのワルツではない。ビアホール「新橋ミュンヘン」で仮面の主人公が医師と語らう場面では、アコーディオンの伴奏に乗って、店員役の前田美波里が「ワルツ」をなんとドイツ語で歌う。なぜドイツか。日独という2つの敗戦国。「他人の顔」には被爆した女性をはじめ戦争の後遺症が象徴的に出てくる。「ワルツ」の作詞はブレヒト研究の第一人者、岩淵達治。ブレヒトといえば戯曲「三文オペラ」と、その音楽劇を作曲したクルト・ヴァイル。「ワルツ」には決然と歌うブレヒト・ソングの雰囲気もある。
武満はシェーンベルクと同様、独学の人。作曲家の清瀬保二に師事し、音大には進まず、若手芸術家集団「実験工房」に入って活動の機会を広げた。琵琶、尺八とオーケストラのための「ノヴェンバー・ステップス」(1967年)、ピアノ協奏曲「アステリズム」(68年)などの大規模な前衛作品は小澤征爾の指揮で初演され、世界的に高い評価を受けていった。一方で武満は映画やテレビドラマの音楽も手掛け、歌も数多く作曲した。
五木寛之が作詞し、ハイ・ファイ・セットが歌った「燃える秋」(1978年)も武満独自の歌謡曲といえる。これも五木原作の同名小説の映画音楽として作曲された。ただし編曲は武満ではなく田辺信一。武満といえば前衛音楽という印象が強かった当時、ロマンチックでエキゾチックな「燃える秋」は意表を突く歌謡曲だった。
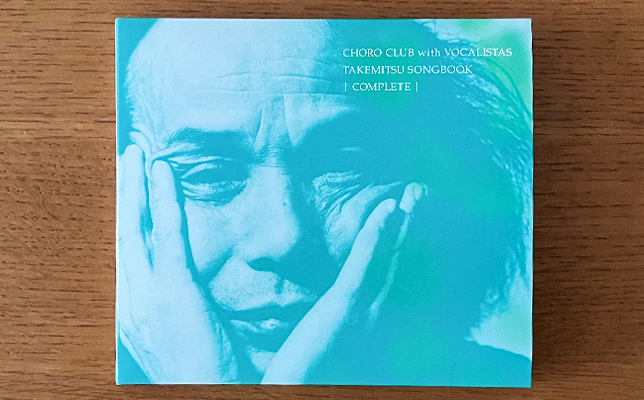
ショーロクラブwithヴォーカリスタスによる「武満徹ソングブック -コンプリート-」(CD2枚組、2020年、日本コロムビア)
武満自身がこうしたソングライティングにどれだけの思い入れがあったかは分からない。ベートーヴェンにとっての「25のスコットランド民謡」のように、ビジネスに徹した創作活動だったのかもしれない。ただ、音楽ビジネスは現代では当たり前すぎることであり、多くの人々の胸を打つ映画音楽や歌謡曲を名曲に挙げないほうがおかしいだろう。ショーロクラブwithヴォーカリスタスによる2枚組CD「武満徹ソングブック -コンプリート-」は、「ワルツ」や「燃える秋」を含め、武満の歌の魅力を独自の編曲で存分に伝えている。
武満の音楽の原体験を調べると、一つは戦時中に聴いたというシャンソンに辿り着く。リュシエンヌ・ボワイエが歌う「聞かせてよ、愛の言葉を(Parlez-moi d’amour)」。フランスのシャンソンは当時、敵性音楽だったはずだが、だからこそ緩やかな3拍子で歌われる甘く切ないワルツ風の歌が心に響いたか。
シャンソンを意識して「他人の顔」の「ワルツ」を聴いてみると、そこには確かにエディット・ピアフが歌った「パダン・パダン(Padam…padam…)」や「群衆(La Foule)」に通じる熱情的な曲調も漂っているのが分かる。憂いを纏ったドイツ語のシャンソンというのが「ワルツ」を聴いて受ける印象だ。
Dmitri Shostakovich – Waltz No. 2
武満の「ワルツ」では主調の嬰ハ短調(C♯m)から半音上のニ長調(D)のコードを挟み込み、半音階の妖しげな雰囲気を出している。こうした半音階への愛着は、ショスタコーヴィチが1950年代に作曲した「舞台管弦楽のための組曲第1番」の中の「セカンド・ワルツ」でも聴ける。ハ短調と変ホ長調の平行調の主題による単純な3部形式だが、半音階を要所に入れた旋律と和声が現代的で洒脱な捻りをきかせる。
調性音楽の仮面を被った伊達者
ショスタコーヴィチが生きた旧ソ連社会では、欧米の無調や十二音技法による前衛音楽が弾圧され、社会主義リアリズムの名の下、人民に分かりやすい旋律や和声を持つ調性音楽が求められた。ショスタコーヴィチも若い頃には前衛手法を駆使した作品を書いたこともあったが、その後は後期ロマン派や新古典主義の作風に近い調性音楽の範囲内で、半音階や不協和音を使いながらぎりぎりの挑戦を続けた。しかし、そうした制約があったからこそ、ハチャトゥリアンの組曲「仮面舞踏会(マスカレード)」(1944年)のような煽情的で聴きやすく洒脱な調性音楽も生まれた。
ハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」第1曲「ワルツ」は20世紀の調性音楽の可能性と新しさ、大衆性を伝える。妖艶かつ流麗に舞い踊る「ワルツ」は、「前衛=優秀」の信仰に縛られた20世紀の舞踏会に、調性音楽の仮面を被ってやってきた伊達者のようだ。スノッブな専門家諸氏の予想に反し、伊達者は一躍、社交界の寵児になるだろう。
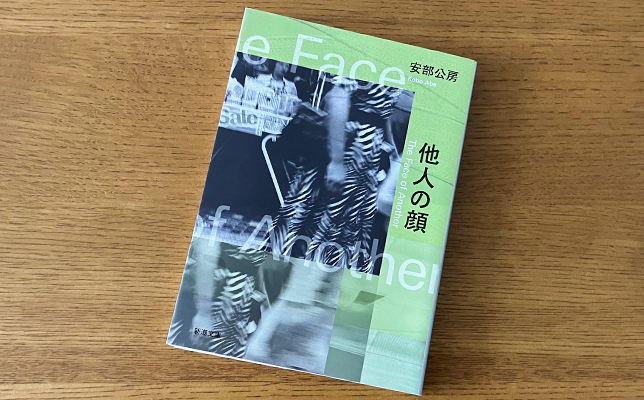
安部公房「他人の顔」(新潮文庫)
「調性音楽の範囲内でも出来ることがまだたくさんあるのではないか」と日本を含む西側世界の現代作曲家が20世紀後半にふと思ったとしても不思議ではない。自由すぎる作曲環境の中で、総音列主義やミュージック・コンクレートなど次々と新手法が登場し、進化を強いられる中で、現代音楽はいつしか袋小路に入ってしまったのではないか。シャンソンを愛した前衛作曲家、武満の「ワルツ」は仮面か素顔か。安部公房の小説「他人の顔」によれば、仮面は新しい素顔に近い。
池上輝彦〔いけがみ・てるひこ〕
音楽ジャーナリスト。日本経済新聞社シニアメディアプロデューサー。早稲田大学卒。証券部・産業部記者を経て欧州総局フランクフルト支局長、文化部編集委員、映像報道部シニア・エディターを歴任。音楽レビュー、映像付き音楽連載記事「ビジュアル音楽堂」などを執筆。クラシック音楽専門誌での批評、CDライナーノーツ、公演プログラムノートの執筆も手掛ける。
日本経済新聞社記者紹介
文/ 池上輝彦
本ウェブサイト上に掲載されている文章・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
tagged: 武満徹, 音楽ライターの眼, クラシック名曲 ポップにシン・発見, 安部公房
![]() ヤマハ音遊人(みゅーじん)Facebook
ヤマハ音遊人(みゅーじん)Facebook
Web音遊人の更新情報などをお知らせします。ぜひ「いいね!」をお願いします!